関連動画
学問の神様=菅原道真
学問の神様(菅原道真)を祀(まつ)っている場所は沢山あり、多くのサイトでも紹介されていますが、人気だからという理由だけで学問の神様へお詣(まい)りするのはちょっと違うかなと。
※神社は「お詣り」、お寺は「お参り」を使います。
とある有名な神社の近くの人は、みんなその神社に合格祈願に行っていましたが、そこの神様は安産祈願ですし。
やはりちゃんと何に対してお願いをしているのか知っておきたいところですね。
そんなわけで今回は蘇我教室の塾生に教えて欲しいと言われましたので、蘇我の地元、千葉県にある学問の神様の1つ、千葉神社について紹介したいと思います。
その前にそもそも学問の神様って何?という方は以前の記事をどうぞ(^^)/
千葉神社の由来とご利益
千葉神社は平安時代末期に関東南部を治めた平良文(たいらのよしふみ)に由来します。
平良文(村岡五郎)は平将門の叔父(父の弟)にあたる人物ですから、知っていても損はないでしょう。
また、彼の子孫はその後の千葉氏のへとつながっていきます。
その千葉氏の祖といえる彼は妙見菩薩(みょうけんぼさつ)を非常に熱心に信仰していたため、その後の千葉氏においても妙見菩薩は信仰の対象となりました。
そこで香取神宮に祀ったのですが、現在の千葉市の方が都合がよくなったため、千葉市へ持って来て千葉神社(当時はお寺)となりました。
この千葉氏の家紋が月と星。
これは平良文の戦の時の伝説(空から星が降ってきて勝利を導いた)により作られたと言われています。
この月と星の家紋が、
- 月 ⇒ つき・運
- 星 ⇒ 白星・勝利
に通じているとして、その縁起の良さから人気になっています。
それゆえ、その家紋が入っているお守りも人気。
白地に黒の家紋にすると、黒星(負け)になってしまうんですけどね(^^;
学問の神様は千葉天神
それはさておき、妙見菩薩(みょうけんぼさつ)は北辰菩薩とも呼ばれ、北極星や北斗七星に対する信仰でもあります。
北極星は空の回転の中心にあることから、国土を守り、災難や敵を除去してくれると考えられています。
そんなわけで元はお寺だったのですが、神仏習合の時代に神社の神輿などの文化と混ざり、さらに学問の神様(菅原道真)も祀られるようになりました。
それが千葉神社の境内(けいだい)にある千葉天神というお社。
これは千葉神社の旧社殿を用いており、千葉県内最大!
そして神仏分離令が出された時には神社の文化が強くなっていたため、神社(千葉神社)へと変更しました。
一度で3度おいしい千葉神社
千葉神社がなぜ学問の神様として有名なのか、おわかりになりましたでしょうか。
まとめておきましょう。
- 千葉神社のスタートは仏教の妙見信仰(妙見菩薩)
⇒ 災難とライバルの除去 - 千葉氏の家紋が月と星
⇒ ツキ(運)を呼び、勝ち星を拾う - 千葉天神(菅原道真)を信仰
⇒ 学問の神様
と一度で3度おいしい初詣ができるわけです。
折角初詣に行ってお寺や神社を身近に感じられる機会があるのですから、少しでも話のネタになれば大きな意味があります。
やっぱり学問の神様に行くべき?
もちろん初詣はどこに行っても構いません。
受験の合格祈願なら絶対ここというわけでもありません。
ただ、願かけや占いなどを気にする方、少しでも心の支えにしたい方は、それなりに学問で有名な所にお詣りしておくといいかも知れませんね。
しかし、あくまで自身がしてきた勉強自体が合格に導くことを忘れずに!
-1024x576.png)





-35-485x300.png)
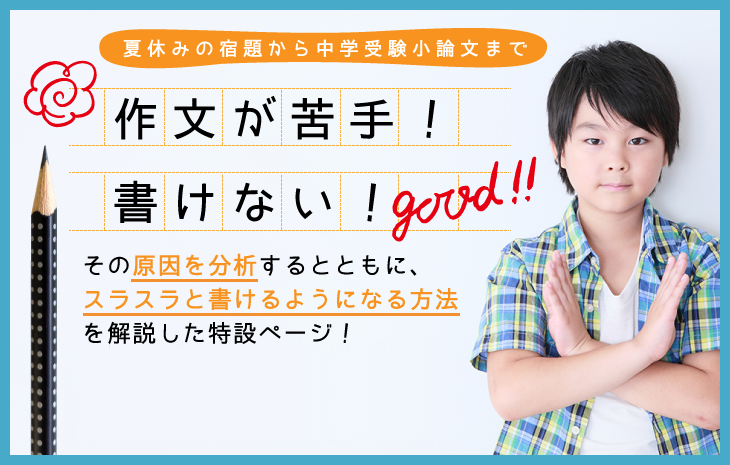
-3.png)

-5-150x93.png)
-33-150x93.png)

-36-485x300.png)



-10-485x300.png)




