はじめに
歴史=暗記と勘違いしている人が多いのですが、歴史は暗記なんかしなくても解けるようになります。
その有効な手段の1つが映画やドラマ。
ここでは中学受験、高校受験という観点からみて、有意義な映画やドラマを紹介します。
選定基準は以下の通り。
- 大筋、もしくは時代背景が史実、実話に基づいているもの。
- 受験に通じてくる単元の背景イメージとして役立つ部分があるもの。
- 感情が揺さぶられる、考えさせられることが期待できるもの。
禁止事項
強制的に見せるのは厳禁!
子どもが飽きていそうなら迷わず中断して下さい。
子ども一人では理解が難しいところも多いので、途中で止めて話しながら、無理せず進めて下さい。
そしてできれば親子で一緒に見て、子どもと話を共有して下さい。
この会話こそが、子どもの使える知識へと発展していきます。
平安時代
逃げ上手の若君
1333年 鎌倉幕府滅亡以降

足利尊氏の裏切りにより、鎌倉幕府が滅亡させられた際、逃げ延びた北条時行を題材にしたお話です。実在する人物が出ていますが、史実とは異なる、デフォルメ化された描写が多くあります。それゆえ、人物や出来事の特徴はとらえやすいでしょう。史実に基づいている部分はナレーションが入っているので、鎌倉時代から室町時代への変遷の雰囲気を感じやすい作品となっています。歴史としては、記録が残っていない部分をフィクションで埋め合わせいるストーリーなので、受験対策として用いるなら、その点は注意して下さい。
戦国時代
火天の城
1500年代 織田信長

織田信長の安土城を築城した時のストーリー。
岡部又右衛門の建築に対する妥協しない情熱は必見!
史実に基づいているとはいえ、安土城に関してはわかっていないことが多く、言い伝えに沿った形となっています。
そのためあくまで一説を映画にしたものと捉えた方がいいと思いますが、信長の考えがぶっ飛んでいた辺りは大体共通。
天守閣、吹き抜けの構想、守りがない城、ライトアップ、観光名所化は、いずれも日本初で史実と言われています。
信長の人物像を頭に入れておくのに一役買うでしょう。
清須会議
1500年代 豊臣秀吉

織田信長の死後、後継者を誰にするかが話し合われた清須会議がテーマ。
豊臣秀吉がどのようにして実権を握って行ったかが面白おかしい描写で描かれています。
史実を基にしつつ、コメディを交えているので、戦国時代を勉強済みの子なら楽しめるでしょう。
のぼうの城
1500年代 小田原征伐・石田三成

豊臣秀吉が天下統一する直前の最後の戦い、小田原城の戦いの時の話。
最後まで戦った忍城(おしじょう)の、のぼうこと成田長親(なりたながちか)と石田三成の戦いを史実に基づいて映画にしたもの。
成田長親がなぜ戦うことを選んだのか、その思いをくみ取れるかどうかで子どもの成長具合がわかります。
この部分自体は入試に出てきませんが、兵農分離前の戦の様子、そして豊臣秀吉の天下統一の道筋がよくわかります。
江戸時代
天地明察

1600年代 暦・徳川家綱(4代将軍)の時代

日本の暦は誰が何のために使っていたのかがわかる、史実を基にしたフィクション。
実在の人物が登場してくるため、時代背景との関連付けがしやすいでしょう。
常識を疑い、新たな常識を見つけていくことの大変さ、その常識を広めていく難しさを感じることができます。
また、暦の役割がイメージできるようになると、国語、算数、理科、社会、全てにおいて役に立つ機会が出てきます。
殿、利息でござる!
1700年代 江戸時代中期・農民と武士の関係・利息

江戸時代中期の、吉岡宿という実在の町で行われた財政政策を史実に基づいて再現した映画。
農民が身分制度の一番下だった社会的構造から脱却するため、農民が武士にお金を貸して、その利息を町の財政に当てるというとんでもない手法を思いつき、実現。
これにより、吉岡宿は現在の価格にして約2000万円程度の利息を手にしたため、江戸幕府滅亡まで存続しました。
利息の話は難しいためイメージしにくいのですが、この話は江戸時代ということもあり、どういう仕組みで利息が手に入るか、を説明するところから始まっています。
経済のイメージづくりに向いているでしょう。
また、通常とは異なるとはいえ、農民と武士の関係が垣間見える映画です。
武士の家計簿
1800年代 加賀藩・武士

江戸後期から明治にかけての実際の武士の家計簿に基づいて、経済的視点から武士の生活を表した映画。
家計簿を基にストーリーを脚色しているので、細かい部分は史実とは異なりますが、武士の生活がどのようなものだったのか、切り合うだけが武士の仕事ではなかったということがわかります。
龍馬伝 ドラマ
1800年代 幕末・坂本龍馬

その名の通り、坂本龍馬の生涯をドラマ化したもの。
登場人物のキャラクター設定が史実とは違う、という話はよくありますが、受験で必要なのはキャラクターではないので問題ありません。
幕末の歴史的な流れと背景に関しては十分史実に沿っています。
坂本龍馬がなぜ敵である土佐と手を組んだのか、なぜこうも許せたのか、争いに対する考え方を学べます。
桜田門外ノ変
1800年代 幕末・井伊直弼

1860年に起きた、桜田門外の変をテーマにした映画です。
どうして暗殺にいったたのか、など幕末の歴史的な流れと背景を知ることができます。
明治から昭和
あさがきた ドラマ

1800年代 女性の社会進出

江戸後期から明治にかけて、女性の社会進出をテーマにしている実話に基づいたドラマ。
モデルとなっているのは日本女子大学を設立した実業家、広岡浅子。
なぜ勉強しなければならないのか、勉強すると何が得なのか、くみ取ってくれるといいなーと思って紹介してます(笑)
江戸から明治への移り変わりは、テキストでは明治維新、文明開化の一言で片づけられており、経済的な視点で世の中の移り変わりを描いたものは珍しいでしょう。
蟹工船
1900年代 人権・労働問題

小林多喜二の小説を原作とした、昭和前期の労働環境に対して問題提起した映画。
プロレタリア文学の代表作として国際的な評価も高く、受験でも国語、社会の題材にされます。
蟹工船とはカニ取り漁船のことで、1日16時間労働かつ人権無視の働かせ方に対して労働者が反乱を起こす物語。
話が通じない相手にどう立ち向かうか。
今では法律が守ってくれるので、その法律をうまく使える人が得するという解釈ができると勉強することの意義につながります(笑)
史実ではありませんが、その時代の労働問題を反映した作品で、小林多喜二はこの作品を発表したことにより、特別高等警察に不敬罪として逮捕、拷問され、虐殺されます。
その辺りの時代背景までくみ取ると、この時代はいかに自由に意見を言えなかったのかがわかってきます。
おしん ドラマ
1910年代~ 第一次世界大戦~太平洋戦争・戦後の発展

第一次世界大戦から太平洋戦争、戦後と、これ一つ見れば明治後期から昭和までの時代背景のイメージ、そして移り変わりがしっかりつくドラマです。
女性視点で描かれているため、生活の様子がよくわかります。
モデルと言われている女性は何人かいて、それぞれの時代のそれぞれの生きざまを取り入れて作った形になっているようです。
生きるために働かなければならなかった世代と、好きなことを仕事にする世代の葛藤を感じ取れるといいなと思います。
おしんには映画もあるのですが、断然ドラマです。
15分×297話とかなり長いドラマなので時間を確保するのも大変ですが、見る価値は大いにあります。
海外、特にイランでは大ヒットし、未だにおしんを知らない人はいないと言われるぐらいです。
出口のない海
1940年代 回天・特攻下における人々

第二次世界大戦中の太平洋戦争を背景とした映画。
回天という潜水艦を使った特攻へ行くことになった青年の話。
守るために死ぬという選択を子供がどう感じるかがポイント。
ストーリー自体はフィクションですが、回天自体にまつわる話は実話。
特攻とはどのようなものだったのか、どんな気持ちで特攻していたのか、それが子どもに伝わるだけでも見る価値はあるでしょう。
男たちの大和/YAMATO
1940年代 戦艦大和・戦争による疲弊

太平洋戦争で日本が作った世界最大の戦艦大和(やまと)をテーマにした映画。
生存者や遺族の取材を通して作られた映画なので、細かな描写はフィクションですが、大筋の歴史の流れは実話に基づいています。
大和がどういう戦艦だったのか、どうして使いこなせなかったのか、なぜ特攻が行われたのか、それらを通して、太平洋戦争時の日本の疲弊具合を知ることができます。
永遠の0
1940年代 ゼロ戦・訓練と特攻の実態

第二次世界大戦中のゼロ戦乗りをテーマにした話。
ストーリー自体はフィクションですが、時代背景や描写はとてもよく、どんな気持ちで特攻に行ったのかが伝わってきます。
映画とドラマがありますが、どちらもおおまかな流れは同じ。
映画でもうまくカットされているので、ポイントはしっかり押さえられます。
なお、ゼロ戦乗りの宮部久蔵が奇想天外な操縦をするパイロットという扱いを受けていますが、当時のゼロ戦は画期的な戦闘機だったため、常識はずれな飛行が可能だったのです。
しかしその性能を引き出す飛行訓練が行き届かなかったのも史実の描写通り。
杉原千畝
1940年代~ 戦時下の外交・ナチスのユダヤ人迫害

第二次世界大戦中にナチスによる迫害からユダヤ人を守るため、独断で日本通過のビザを発行し、6,000人以上のユダヤ人を救った外交官、杉原千畝(ちうね)の実話です。
第二次世界大戦で、日本はドイツと同盟を結んでいたため、この行為がバレれば、杉原自身もただでは済みません。
ドイツにも、日本にもいられなくなります。
そんな中、杉原千畝は独断で自分の持つ権力を駆使し、ユダヤ人を守るために行動しました。
ナチスに目を付けられ、自分が逃げなければ命に係わるギリギリまでビザを発行し続け、アメリカと戦争しようとしていた日本政府を公然と非難しました。
そのため、外務省を追われ、不名誉なレッテルを貼られたまま亡くなっています。
ドイツで一体何が起きていたのか、にも着目したいところですが、教科書には載っていないけれど、こういう日本人もいた、ということは知っておいて欲しいところです。
ちなみに冒頭とエンディング部分の杉原千畝を探し求めてきたけど会えず、その後再会を果たすまでのストーリーまで含めて史実、というのがまた凄いですね。
さらに映画では描かれていませんが、杉原千畝の死後、杉原の発給したビザによって救われた人物が、杉原が外務省を辞めることになった経緯を知って憤慨し、外務省に抗議文を送りつけたことにより、日本国政府として公式の謝罪と名誉回復が行われています。
海賊と呼ばれた男
1910~50年代 出光興産の創業者の功績と石油を巡る攻防

映画では國岡商店の創業者、国岡鐵造という名称で描かれていますが、モデルとなっているのは「出光商会」(現:出光興産)の創業者の「出光佐三」です。大手が牛耳る販売市場を奪っていく手法から、海賊と呼ばれていたようです。登場人物のほとんどは実在の人物をモデルにしており、ストーリーも出光佐三の逸話を基にしています。
注目すべきは、どれだけ批判されようと大手を相手に信念を曲げずに事業を貫いたこと、戦後にGHQの指示により出された燃料タンクに溜まった原油を回収したこと、アメリカやイギリスといった大国を敵に回してでもイランの石油を買い付けたこと、でしょう。
背景として、
- 油には種類があり、精製の仕方によって性能が変わるということ。
- 原油回収は下手をしたら死ぬ可能性がある、非常に危険な作業だということ。
- イランは石油を国有化した(価格が上がる)ことで、アメリカ、イギリスの反発を招き、「イラン産の石油を買った船は撃沈する」と言って、イランが国際的仲間外れにされている中で出光が買い付け、国際問題(日章丸事件)に発展したこと。
は知っておくと理解が深まるでしょう。
また、歴史的事実として出光佐三の功績を知っておくというよりは、出光佐三の功績を通して、日本がどのような状況にあったのか、を感じ取れると思います。最も、今同じ働き方をしたらブラック企業と言われるようなところもありますが、当時誰かがやってくれたから今の日本がある、とも言えます。ちなみに出光は健康経営優良法人2023~ホワイト500~に選出されています。
なお、1949年に石油元売業者として登録された企業の内、
- シェル(世界の石油生産をほぼ独占していた7社の内の一社) → 出光と合併 → 出光の子会社化(現:RSエナジー)
- 昭和石油 → 昭和シェル石油 → 出光と合併
- 日本鉱業 → 新日鉱ホールディングス → ENEOS
- 日本石油 → … → シェブロン傘下 → … → 新日本石油 → … → ENEOS
- 三菱石油 → … → 新日本石油 → … → ENEOS
- カルテックス → … → 日本石油と業務提携 → … → シェブロン
- スタンダード・バキューム → … → エクソンモービル
- ゼネラル物産 → 現エクソンモービルと提携 → ゼネラル石油 → ENEOS
と再編が進んでおり、当時のままの名称はあまり見られなくなりました。
世界史
キングダム アニメ

紀元前200年代 中国(春秋戦国時代)

中国の春秋戦国時代に秦(しん)という国が、中国全土を中国史上初めて統一するまでを描いた漫画を基にしたアニメ。
戦いと主要人物は史実に基づいていますが、キャラクター設定はフィクション。
なにせ日本が縄文時代の時の話ですからね(^^;
でもだからこそ子供も楽しめるマンガになっています。
中国史自体は中学受験、高校受験では問われませんが、この時代の戦い方、戦略、組織の規模とリーダーの役割といったことを学べます。
レッドクリフ
200年代 中国(三国時代)

中国の三国志の赤壁の戦いが舞台。
日本でいうと卑弥呼の時代。
中国史が受験に出てくることはあまりありませんが、中国史を知っていると日本史にも使える部分があります。
テンポが良く、わかりやすいので、印象付けにはいいでしょう。
なお、PartⅠとPartⅡの2部作となっています。
ブレイブハート
1300年代 イギリス(エドワード1世)

スコットランド独立戦争を描いた映画。
日本では鎌倉時代末のあたり。
侵略者であるイングランド王エドワード1世は世界史では重要な人物で、統一したイギリスを目指した最初の王。
入試には直結しませんが、イギリスの歴史を学ぶきっかけになります。
レ・ミゼラブル
1700年代 フランス革命・ナポレオン

フランス革命からナポレオン没落後までの社会情勢を表したヴィクトル・ユーゴーの小説を原作としたミュージカル映画。
日本では江戸時代中期、寛政の改革あたり。
日本人の子どもが描くフランスのイメージは、人形から入っているためか服装やきらびやかな生活のイメージが多く、庶民の生活や社会情勢のイメージが話だけでは入りにくい。
この映画の原作は小学生の教科書にも使われる程平易な文章でわかりやすく、当時のフランスの状況をイメージするのに一役買います。
イミテーション・ゲーム
1940年代 ドイツ(第二次世界大戦)

ナチスドイツが開発した暗号機「エニグマ」を解読したイギリスの数学者、アラン・チューリングについて描いた映画。
アラン・チューリングが世界で初めてコンピューター(計算機)の理論を構築し、実際にそれを作り上げることでエニグマを解読して見せた。
現在のコンピューターは彼の理論を基に作り上げられており、さらに彼は現在のAIの進歩まで予言しています。
この映画を通して、武器や兵器を持たない人が、どのような気持ちでどう戦争に参加していたかを垣間見ることができます。
「ペンは剣よりも強し」を実感できる映画ではありますが、補助なしでは小学生、中学生には難しいでしょう。
高校生が情報という教科で習う程度のコンピューターの原理を知っていれば楽しめますので、チャレンジはしてみて欲しい映画です。
シンドラーのリスト
1940年代 ドイツ(ホロコースト)

ドイツのナチスによるユダヤ人虐殺から、少しでも人々の命を守ろうとして、ひそかにユダヤ人をかくまっていたシンドラーを題材とした、実話に基づいた映画。
これを見て、何を学ぶかは子どもの力量によるでしょう。
武器や兵器をカッコいいと思っている子は、絶対に一人で見せるべきではありません。
塾生に紹介するときも、ちゃんと理解できる力量がある子に紹介しています。
見た子はみんな思い出しただけで泣きそうになっています。
それぐらい重い。
第二次世界大戦でナチスが何をやってきたか、どうしてそんなことになってしまったのか、そういった背景を学べますが、それ以上に、人としてどうあるべきか、自分には何ができるのか、そういったことを考えさせられると思います。
なお、白黒なのは演出です。そこまで古い映画ではありません。
ワルキューレ

第二次世界大戦中のドイツで、国防予備軍を終結する方法として作られた作戦を「ワルキューレ」といいます。元々国内予備軍を沿岸防衛や敵の上陸阻止のために動員するためのものでしたが、国防軍大佐がクーデターに利用するためにワルキューレ作戦を改ざんしました。例えば元々前線に将兵を送るための作戦でしたが、国内で強制労働させられている労働者による反乱に備える必要があるとして、重要施設の確保を作戦に盛り込みました。しかし本当の目的はヒトラー暗殺後にクーデターを起こした際、速やかに重要施設を確保してクーデターを成功させやすくするための作戦変更でした。なお、これらの作戦変更には当然ヒトラーの署名が必要だったため、幹部クラスを巻き込んだ大規模な作戦となり、これら一連のヒトラー暗殺計画を基にした映画となっています。
なお、ヒトラー暗殺自体は確認されているだけでも15回あります。そしてこの暗殺計画の9カ月後にヒトラーは連合国に追い詰められて自決しました。
42 〜世界を変えた男〜
1940年代 黒人差別

史上初の黒人メジャーリーガー、ジャッキー・ロビンソンのお話です。野球を知らない人でも楽しめます。黒人差別がいかに酷いものだったか、どうやって世界を変えたのかを垣間見ることができます。何を言われても、何をされても、徹底して野球のルールの中で勝つことにこだわった、彼の強さを感じることができるでしょう。なお、彼がつけていた背番号42番は、彼の功績を称えて、全球団共通の永久欠番となっています。
グリーンブック
1960年代 黒人差別

グリーンブックというのは、黒人差別が当たり前だった時代に、黒人が利用可能な施設を記した旅行ガイドのことをいいます。
1960年代のアメリカを舞台とした実話で、黒人ピアニストと、その運転手として雇われた白人が、演奏ツアーを行う中で起きた出来事を描いた映画です。
差別については教科書にも出てくるのですが、差別の現実を知っている子はあまりいません。
この運転手の白人も、ハッキリと言わないものの、黒人を差別的な目で見ているシーンが描かれています。
そんな黒人と白人の二人が、お互いに尊敬しあい、友情を深めていく人間ドラマも見ものですが、この黒人ピアニストが、ピアニストとして招待されながらも受ける差別の部分に、感じてもらえる部分があればと思います。
アルゴ
1980年代 イラン革命・中東問題

1979年に起きたイラン革命により発生したイランアメリカ大使館人質事件を題材とした実話に基づいた映画。
中東問題なので、中学受験で難関を目指す子以外には難しいでしょう。
しかしもし理解できれば、なぜ中東問題がこじれたのか、宗教とは何なのか、といった中東問題、外交の難しさを感じ取れるでしょう。
インビクタス/負けざる者たち
1990年代 アパルトヘイト・マンデラ大統領

1990年代、南アフリカ共和国で初の黒人大統領となったネルソン・マンデラ大統領と、南アフリカ代表のラグビーチームの実話です。
南アフリカ共和国は、元々イギリスの植民地で、独立後も白人が政権を握り、強力な人種差別であるアパルトヘイト(人種隔離政策)を行っていました。
それに反対した黒人のネルソン・マンデラと政府との攻防は武力衝突にまで発展し、マンデラは27年間も投獄されていました。
しかしその後、政府が弱体化し、戦争でも負け、内戦でも勝てなくなったため、時の大統領はアパルトヘイトの廃止を宣言、これによりネルソン・マンデラは釈放され、大統領に就任しました。
しかし政府がアパルトヘイトを撤回したとはいえ、今まで差別を国の政策として強いられてきた国民、特に白人は納得がいきません。
南アフリカ代表のラグビーチームも白人で構成されたチームだったため、大統領と度々衝突を起こします。
そんな中でのマンデラ大統領の白人への対応、政策、そして差別の実態と克服の難しさに着目したい映画です。
その他
最強のふたり
現代 偏見

脊髄損傷で体を動かすことができない大富豪と、その介護人として雇われたスラム街の黒人青年の人間関係を描いた実話。
人種、年齢、生き様、全てが異なる二人が信頼し合い、人生を楽しもうとする流れが、差別や偏見といったことをちっぽけに感じさせてくれます。
最後に
映画はきっかけに過ぎませんが、効果は絶大!
全く興味がない、何も知らない状態で授業を受けるのと、すでにストーリーやキャラクターのイメージができている授業を受けるのとでは理解度も積極性も大きく変わってきます。
もちろん見せるだけでは意味がありません。
楽しく見ることが最大のポイント。
そのためには、やはり親子一緒に見て、話をするのが欠かせないでしょう。
また、どんな意見であれ、子どもの意見や考えを否定しないように注意して下さい。
映画の感想に正解も不正解もありません。
あるのはただ、どう感じたかだけ。
自分の考えを持ち、自分の意見を行けるようにする訓練と考えてあげて下さい。
なお、ファイではこのような勉強の仕方から、入試でも通用する学力を育てることに成功しています。
机上の勉強だけが入試のためのになる勉強ではありません。
子どもの興味を伸ばすことも、立派な勉強につながるのです。
何度やらせても覚えられない、点数が取れない方は学習法診断をご利用下さい。
あなたのお子様に合う勉強スタイルがハッキリしますよ!
-1024x576.png)




















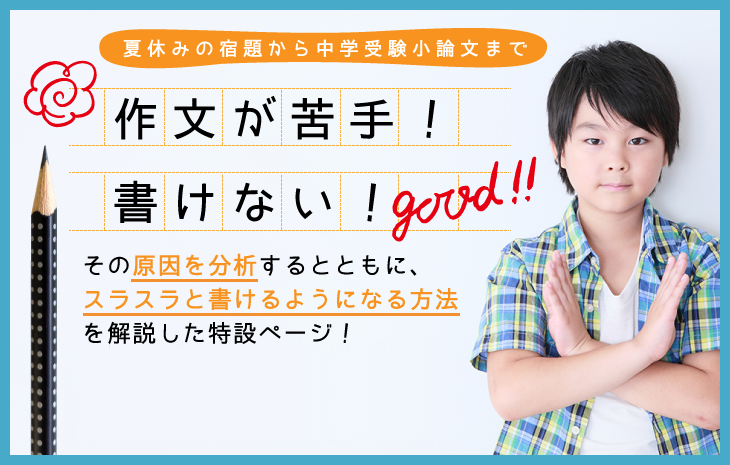
-3.png)


-150x93.png)






-2-485x300.png)





