目次
両立ができない理由
今年は新型コロナウイルスの影響で総体自体がなくなった子も多く、あまり部活が終わったという気がしないかも知れません。
むしろ徐々に日常に戻っていく感じなので、中1、中2なら部活や習い事もこれから本格的になっていくことでしょう。
中3はもう大会も終わって勉強モードに入っていることでしょう。
え?
入っていない?
いやいや、とりあえず受験生もそれ以外も、大部分の子は勉強モードに入ってもおかしくない時期!
一体どうしてしまったのでしょう(笑)
というわけで、今回も相談が多かった、勉強モードへの入れ方のお話を致します。
中2なのに一向に勉強と部活の両立できない
両立ができないという相談は、中2の夏~秋、中3の春~夏に集中しています。
そしてこの手の相談をしてくる方には、ほぼ例外なく進学前の段階で共通点があります。
ハッキリ申し上げます。
この時期、このタイミングで相談をしてくる方は、既に手遅れです。
勝負は進学前に決している
ちょっと思い出してみて下さい。
中学生になる前、小6の1~3月頃にあなたは塾や勉強について何て言っていましたか?

「学校や部活が始まってみないと生活のペースがつかめないから、塾は様子を見てから考えます、と言っていました。」
そうですよね。
学校や部活が始まってから勉強をどうするか考える。
そう言っていたはずです。
しかしよく考えてみてください。
この時点で部活優先の生活が決定してしまっているのです。
だってそうでしょう?
部活が始まって、生活に部活が馴染んでから勉強のことを考える、と言っているのですから。
子どもが部活優先になるのは当たり前ですよね?
あなたがそれを望み、容認していたのですから。
まず親としてこの部分をしっかり認識できなければ、挽回することはできません。
このように育ててしまった以上、両立しろという事自体がおかしいことをしっかりと認識して下さい。
両立できない子を挽回させる方法
進学前・中1になったばかりなら
至極簡単です。
勉強優先の生活を身につけさせてから、その生活に部活を馴染ませる、のです。

「でも先生、勉強優先の生活をさせたら、部活とのバランスが取れなくなりませんか?」
順番の理論だけで言えばそうなります。
しかし現実はそうはなりません。
勉強優先にしていても、簡単に部活優先に傾いてしまうのです。
その要因は、
部活のストレスは半端じゃない!
ということです。
肉体疲労もさることながら、精神的疲労も非常に大きなものになります。
そんな子どもたちにとって、家とはどういう場所でしょう?
くつろぎの場所になりますよね?
それなのに家に帰ると親に「勉強したのか?」「勉強しなさい!」と言われる。
誰の目も気にせずくつろげるはずの家が、ストレスの場所に変わる瞬間です。
そしてますます勉強が嫌になり、やらなくなる。
どれだけ勉強優先の生活を先に講じていたとしても、それを維持できなければ、簡単に部活に振り回されてしまうのです。
だから余程家で勉強する事が当たり前になっていないと、勉強の両立はできない、部活ありきの生活になる前に勉強する事をしっかり優先しておく必要があるのです。

「確かに部活優先の生活を容認してしまったのは私ですね。ではその場合、勉強とのバランスを取ることはもうできないのでしょうか?」
いいえ、そんなことはありません。
確かに先程の方法は、中1になる前だからできること。
既にその時期を過ぎてしまったら、今さらどうしようもありません。
しかし今から何とかする方法がないわけではありません。
でもここからは親も覚悟が必要ですよ!
もし今現在あなたのお子様がまだ中1になっていないのなら、以下の記事をお読み下さい。
部活優先の生活になってしまった場合の逆転法
既に部活優先の生活にしてしまった。
その場合もうどうしようもないのでしょうか。
いいえ、そんなことはありません。
実はこれも簡単な事なのです。
親自身が勉強する時間を確保する事、です。
勉強しなさいというよりも、親が勉強する姿を見せる。
これに尽きます。
勉強と言っても子どもと同じ勉強をしなさいというわけではないですよ?
親は親の思う好きな勉強をすればいいのです。
資格でも自己啓発でも情報収集でも趣味でも、何でも構いません。
ただし、子どもに望む姿勢と同じ姿勢を取るようにして下さい。
子どもに机に向かわせる勉強をさせたければ、親も机に向かう時間を作る。
本を読ませたければ、親も読書の時間を作る。
新聞を読ませたければ、親も新聞を読む時間を作る。
ただこれだけです。
簡単でしょ?

「いやいや、先生。それは難しいですって。私が仕事から帰ってきたときには既に子どもは家でくつろいでいますし、私もかえってから掃除に洗濯、料理に送り迎えとやることがあって、趣味の時間も取れないんです。」
そうですよね。
親は子ども以上にやるべきことが沢山ありますからね。
時間的に厳しいことは重々承知しています。
では、もう一度よく考えてみましょう。
本当に両立させる覚悟はあるのか
先程お話した通り、すでに中2,中3になっている子を両立へ導くのは簡単ではありません。
むしろ現実的に不可能です。
それを成し遂げるならば、それなりの努力と代償が必要になります。
お金をかけないなら、親がその姿を見せればいいだけです。
今あなたを忙しくしているものを間引いて時間を確保することはできませんか?
よく考えると不要な時間があるはずです。
それをかき集めて、子どもと一緒に勉強する時間に使う。
できませんか?
できないなら、別の方法を考えましょう。
その方法とは、時間をお金で買う方法です。
お金はかかりますが、目的は達成しやすくなります。
今あなたがしていること、しなければならないと考えているものを、代行サービスに依頼しましょう。
お金がかかりますが、あなたの時間は浮きます。
その時間を子どもとの勉強時間に費やせばいいのです。
それも難しいですか?
なら、先生をべったりつけましょう。
家庭教師でもオンラインでも構いません。
塾に入り浸らせるという方法でも構いません。
何かしらの形で、常に人の手と管理が入っている状況を作るのです。
お金があるなら、これが一番楽でしょう。
どれもできないのであれば、子どもも両立ができるわけありません。
親が出来ないことを子どもに要求しようなど、虫が良すぎる話です。
現実と向き合って、別の方法を探して下さい。
塾に頼って挽回するなら、選び方が大切!

「今からではキツイことはわかりましたが、少しでも可能性を上げるためには、どうやって塾を選べばいいか教えて頂けますか?」
塾に頼って何とかする方法を模索するのであれば、選び方で失敗すると挽回できなくなるどころか、失速していくこともあります。
先程お話した通り、中2、中3で両立が出来ていない子を両立に導ける確率は1%未満です。
100人いて、99人は失敗します。
その99人がよくやる選び方が、実績と料金だけで決めること。
その実績を出した子が、どれくらい長く通っていて、どういう勉強してきたかお分かりになりますか?
その中にあなたのお子様と同じ状況から挽回できた子は見つけられますか?
見つけられないから99人の失敗組に入ることになるのです。
乗り遅れている以上、実績や料金を追いかけても両立には成功しません。

「体験授業を受けていいなと思ったところなら大丈夫ですか?」
体験授業というのは、実施するだけで8割はそのまま入塾すると言われているものです。
そのまま入りやすいように手を尽くすから、8割もの人がそのまま入ってしまうとも言えます。
つまり、入れるために仕組まれた営業活動に捕まっただけの話であり、塾選びをしたとは言えません。
塾の本質なんて、1個や2個、数時間体験したぐらいではわからないものです。

「友達から話を聞いた塾ならどうでしょうか?」
実はこれが一番成功しやすいのです。
最も、友達に誘われたとか、ちょっと話を聞いた程度で選んでもうまくいきません。
子どもの見ている世界はせまいですからね。
親が実際の声を集め、比較し、その上で決める。
これが大切です。
その際気にするべきことは、両立させやすい塾であること、です。
まず時間の融通が利くかどうか。
わからないところを解決する手段が用意されているかどうか。
「質問室があります」程度では意味がありません。
あなたの子どもが使いこなせるかどうか、が重要です。
そして一番重要なのが、抜けている部分をピンポイントで見抜く力のある先生がいるかどうか。
大学生のバイト講師でも、当たり外れがあるというだけで、いい先生はいます。
これは経験の差と相性によるものですね。
いい先生を見つけるまでめげずに探せるかどうかがカギになります。
最近はプロ講師や正社員とは言っても、AIに頼っているため経験が少ない先生も増えてきています。
塾長が見てくれているから大丈夫とは言えない点も注意して下さい。
特にAIに任せて実施場所が決まる場合は十分注意して下さい。
あれはあくまで一般的にはここをやればいいよね、というだけであり、思考力の育成ではなく、暗記のサポートが強みです。
勉強モードの入り方

「部活も早々に終わり、いざ受験勉強だという時期になっているのに、全くその様子が見えません。今年はコロナの影響もあって、入試がどうなるかわからないのに、親ばかり不安で子供はケロッとしています。どうすれば勉強モードに入ってくれるのでしょうか。」
何度も言うように、既に手遅れなのですが、それでもできないことはないのでお話しましょう。
ただし、簡単に真似できるものではなく、親の覚悟が必要なのは言うまでもありません。
勉強モードの入り方は3通り。
- 自分でスイッチを入れる。
- 環境でスイッチを入れる。
- 勉強スイッチを壊す。
①自分でスイッチを入れる。
これは前々からかなりの布石を打っておかないとできません。
正直、夏以降では難しいでしょう。
布石の打ち方も様々ですが、ファイでは基本何もしません。
何もしないので、本人がやるというまで待ちます。
本人がやると言い出せば応援する。
とはいえ、何もしなければ何もしないので、どこかで当たるように布石を打っておくという感じです。
うまく行けば、夏前には勉強はするのが当たり前という意識改善ができるので、勉強禁止令を出しても勝手にやってくるようになります。
②環境でスイッチを入れる。
2つ目は、勉強するのが当たり前という環境に入れてしまえばいいという方法です。
塾はその典型。

「今から入れても間に合わないのでは?」
そんなことはありません。
個別指導なら、わりといつでも受け入れてくれます。
やらないと思ったら短期間だけ入れておくのも手です。
残念ながら、やりなさいと言ってもやらないので、環境改善から勉強への姿勢を改善するのが一番近道でしょう。
③勉強スイッチを壊す。
環境でスイッチを入れるという方法は、実は諸刃の剣です。
本人の意思を無視して塾に入れようとしたり、勉強計画を立てたりすると、大抵勉強スイッチが壊れます。
スマホやゲームなどの本人の趣味に当たるものを取り上げるというのも、壊すことに値します。
つまり、本人の意思に関係なく、強制的に勉強させようとする行為、これがスイッチを壊すという事です。
さて、スイッチが壊れるとは何を意味しているのでしょうか。
- スイッチが入ったままになる。
- スイッチが切れたままになる。
このどちらかになると言う事です。
大抵の場合、②のスイッチは切れたまま、になります。
そして壊れてから修復するまで3か月から半年はかかります。
そのぐらいの期間壊れていると、それからスイッチが入っても、もはや手遅れという事態になるのが現実です。
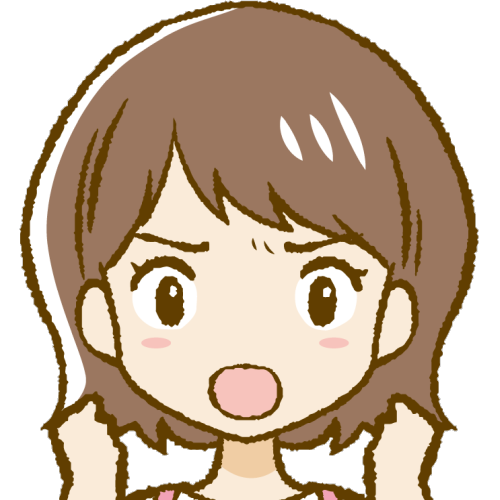
「先生、うちの子のやる気スイッチを入れて下さい!」
この行動がすでにスイッチの破壊への一歩になっている可能性もあるわけです。
実は壊した方がいい場合もある
例外的にですが、何度スイッチが入ってもすぐに切れちゃう子。
こういう場合はあえてスイッチを破壊することもあります。
時間がかかっても新しいスイッチに変えた方がうまくいく可能性が高い場合はそうします。
いわゆるショック療法というやつです。
思いっきりガツーンとダメージを与えて、後はどう考えるか本人に任せて放っておくんですね。
うまくいけば立ち直ってくれますし、その方が結果的に良い結果をもたらす事もあります。
最もショック療法は、どちらに転んでも何とかできる場合にしか使えません。
ご家庭で親がやると、かなりの確率で失敗します。
そもそもおかしいことに、親が気付くべき
夏から勉強させようなんて軽く考えますが、そんな甘くないということです。
夏を制する者は受験を制す!
とよく言われますが、
夏を制する者は、夏前から時間を制している!
こんなの教育業界では常識です。
お客様に話しても理解してもらえないから表立って言わないだけです。
今までろくにやっていなかったのに、夏以降に突然「何とかして下さい!」と言い出す親。
先生はみんな「今さら何を言ってるんだ。」と思っていますよ。
どうしようもないと思っていても、口には出しませんけどね。
適当なことを言って何とかなると思わせれば、お金出してくれますから。
大切なのは受験勉強じゃない
諦めろとは言いません。
しかし自ら選んで苦しい道に子どもを導いた事は認識して下さい。

「そんなつもりはなかったんですけど…」
そんなつもりはなくても、そうなってしまったのは親の責任。
今さら子供に「受験生なんだから勉強しなさい!」なんて言いなさんな、と言う事です。
いいですか?
大切なのは講座のコマ数を増やす事でも、家庭教師をつけることでもありません。
受験は自分のことだと自覚させることです。
そのために必要なのは、環境改善と意識改革。
どういう環境がいいかはお子様の性格によりますから一概には言えません。
しかし勉強させようとする以上に大切なことは確か。
受験はあと半年程度で終わりますが、人生は終わりではありません。
自覚がないまま受けさせられた受験では、進学後もまた同じことを繰り返します。
どのタイミングで自覚が芽生えるかはわかりませんが、長い目で見れば、環境を作って待つ方がいいのです。
例え受験が失敗することになるとしても。
親としてはそんなこと認められないでしょうけどね。
あなたの選択が正しいことを祈っています。
受験を諦めたくないけれど、受験後も捨てたくない方は、月1万円から声かけや持っていき方のアドバイスをしています。
方法がないわけではありません。
ただし楽な道ではありませんので覚悟して下さい。
指導実績に卒業後の話も載せていますので、どれだけ大変かご覧下さい。
-1024x576.png)





-19-485x300.png)
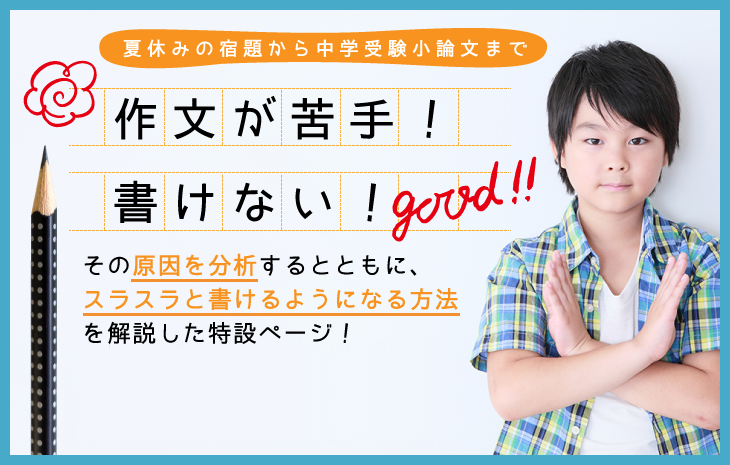
-3.png)

-10-150x93.png)
-19-150x93.png)




-39-485x300.png)








「これから中2になるというのに、一向に勉強と部活の両立が出来ていません。どうすれば両立できるようになるでしょうか。このまま中2になったら、部活に一生懸命で、帰ってきたら疲れて寝るだけという生活が、さらにひどくなっていく気がします。」