放っておく
入試があるということは、合格する子もいれば、不合格になる子もいるということ。
合格しているにこしたことはありませんが、必ず合格できるとも限りません。
むしろ、第一志望に合格できる子は1割もいないとも言われています。
そうなると、ほとんどの方が不合格との向き合い方が必要になるといっても過言ではないのです。
そんなとき、どうするのがいいのでしょうか。
そんな受験に落ちた子供にかける言葉の相談を毎年受けますが、子どもの性格や接し方にもよるので正解はありません。
しかしこの状況に陥るのだけはマズい、というのがあります。
それが、

「お母さんごめんなさい!次は頑張るから!」
となってしまうケース。
もう親のための受験だったことが明白ですね。
こうなるとプレッシャーに押しつぶされてしまう子も多く、まず立ち直れません。
なので、こんな状態にしないのが、一番大切なことと言っても過言ではないのです。
ではどうすればいいか。
基本的には、放っておく。
これが一番です。
気を使って色々と話そうとする必要なんてありません。
落ち込んでいる時間というのは、落ちたという事と真剣に向き合っている証拠です。
あれこれ声をかけたところで響きません。
とはいえ、無関心もよくありません。
関心は持っているけれど、あえて何も言わない。
それが一番いいのです。
認める
もし子どもの方から話して来たら、その時は話を聞いてあげましょう。
ただただ子どもの話に同調して、聞いてあげれば構いません。
どういう反省を口にするかはわかりませんが、とりあえず認めてあげて下さい。
そして毎度の事ではありますが、「頑張ってね。」ではなく、

「期待しているよ!」
の方が効果的です。
期待される方が子どもは頑張りますから。
叱る
基本的には親がやらない方がいいテクニックとして、「叱る」というものがあります。
赤の他人だからできるテクニックです。
そのため、私は叱ります。
特に、やっていなくて落ちた子の場合はお説教です。
なぜ落ちたのか、現実を見なければ次の合格を得られません。
落ちた事がいけないのではなく、受かるだけの努力をして来なかったことが問題なのです。
そこをしっかりと認識させます。
もちろん保護者の方が真似をする必要はありません。
この時期、親として大切なのは、子どもの成長を感じ、支え、見守ることです。
「落ちた=終わり」ではない
中学受験も高校受験ももう始まっています。
しかし試験が終わっても、結果が出ても、勉強が終わりなわけではありません。
「落ちた。終わり。」ではなく、落ちた事をどう次に活かせるか、が大切なのです。
結局のところ、どういう方法を取ったとしても、どうしたら次に向かえるか、これを親として考えてあげることが大切だということです。
最後まで諦めず、受験がゴールだとは思わずに進んで下さいね!
もし進学後を見据えて勉強法の改善を考えているのなら、早めにご連絡下さい。
受験が終わってからよりも、受験前の方が勉強法の改善はしやすいのです。
-1024x576.png)





-38-485x300.png)
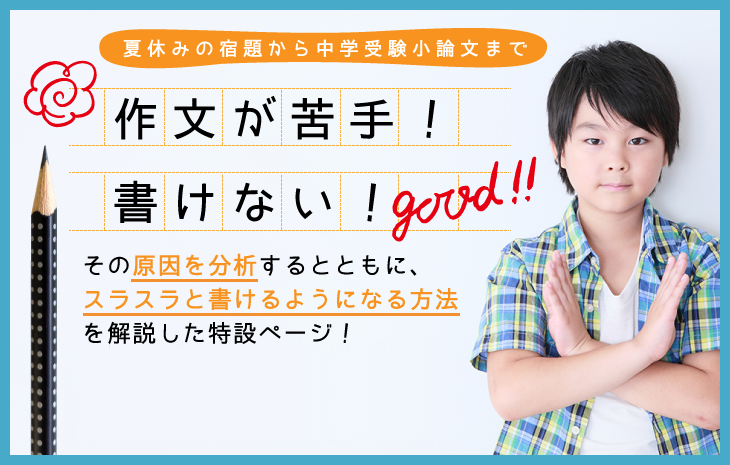
-3.png)

-44-150x93.png)
-14-150x93.png)



-55-485x300.png)


-44-485x300.png)






「残念ながら第一志望は不合格になってしまったのですが、どう声をかけてあげればいいかわからなくなってしまいました。とりあえずまだ残っているから頑張ろうと声をかけましたが、こういう時はどう声をかけてあげるのがいいのでしょうか。第二志望はこれからなので、そっちは合格して欲しいのですが…」