魚を与えるのではなく魚の釣り方を教えよ
老子の書いた淮南子(えなんじ)の中にこんな言葉があります。
「魚を与えるのではなく魚の釣り方を教えよ」
老子 「淮南子」
「授人以魚 不如授人以漁」
この言葉は、
「食糧に困っている人に魚を与えるのは簡単です。ですが与えられたものを食べるだけでは、また魚をもらわないとこの人は生きていけません。」
という意味です。
食べ物を与えてあげれば確かに生きていくことができます。
しかし、与える人がいなくなったらどうなりますか?
与える人がいなくなっても生きていけるようにするにはどうすればいいでしょう?
そこまで考えると、本当に生きていくために必要なことは、与えることではないと気付くでしょう。
魚を与えるのではなく、魚の釣り方を教えてあげるのです。
釣り方を覚えれば、自分で魚を釣って生きていけます。
有名な言葉ですし、言われれば「まぁそうだよな」と感じると思います。
ではあなたの周りの教育はどうなっていますか?
子どもに教える時、
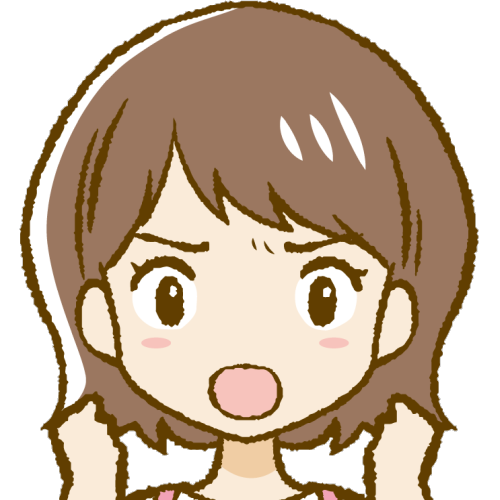
「こうしなさい!」
「こうでしょ!」
「こうやるの。わかった?」
と教えていませんか?
これは先ほどの魚の話にたとえるなら、『魚を与えている教育』になってしまっているのです。
もちろん初めは真似する事も重要です。
しかし「与えなければいけない教育」はそれほど多くはないのです。
ところが現実は保護者の方が子どもに勉強を教える時、このように『与える教育』をしているケースが多く、親子喧嘩に発展します。
子どもは本能的に『自立』することを目指していますから、『与えられる教育』に嫌気がさすんですね。
親からしてみれば「与えられないと生きていけないくせに」って感じなんですけどね(^^;
与えると発展しなくなることが問題になっている

「コンビニにある募金箱って、意味あるの?どこどこに寄付しました、みたいなのは書いてあるけど、その寄付したところがどう使ってるかまでわからないじゃん。」
先日、発展途上国から寄付の話になって、こんな話題が出てきました。
実はこれも「魚の釣り方を教えよ」と共通している問題を抱えているんですね。
コンビニの寄付がいけないと言っているわけではなく、寄付の在り方自体が社会的問題になっているのです。
例えばこのお金が発展途上国の人々にそのまま渡ったとしましょう。
すると彼らは一時的にお金を得ることができます。
しかしお金の稼ぎ方は知りません。
そのため、一時的に生活は豊かになりますが、すぐに手元のお金は無くなって、元に戻ってしまうのです。
こうなるとまた寄付を求め、寄付に依存した生活をするようになります。
結果的に発展途上国のための支援が、発展途上のままで飼殺すための支援になってしまっている、というものです。
勉強も同じなんですね。
塾が知識や時間を与えれば与えるほど、それに依存するようになります。
すると塾がなければ勉強できない子になってしまいます。
でも塾にとっては都合がいいので、こうして塾に依存する子どもたちを量産していくことで塾業界は維持されているのです。
これを養殖教育といいます。
釣り方を教える教育
ではどのような教育をするのが『釣り方を教える教育』になるのでしょう?
簡単です。
教えなければいいのです。
教えなくていいというと、「何のための先生だ」と言われることが多いのですが、教えなくていいというより、今の教育は教えすぎなのです。
本来先生が教えるべきは、「疑問に対する答え」ではなく、「疑問を解決する方法」ではないでしょうか?
釣り方を教える実例
ファイでは実際にこのような授業をしています。

「先生、なんで温暖前線は通過前に雨が降るのに、寒冷前線は通過後に雨が降るの?」

「さぁ?なんでだろ。どこか書いてない?」

「見たんだけど、『こうなる』としか書いてないんだよね。」

「あ、ほんとだ。こっちの図は見た?」」

「うん、見たんだけどよくわからない。」

「わかったところまで説明してみて?」

「えーっと、こっちが温暖前線で、こっちが寒冷前線。」
↑前線ではなく、前線面を指して前線と言っている。

「本当に?これ前線?」

「え?違うの?」

「前線を調べてみて?」

「えーっと…地面と接している部分。あ、前線はここか!」

「そうそう。雲と雨は?」

「雲はここにこうやってできて,雨はここに降る。」

「うん。で、前線はどっちに動くの?」

「こっち。あ、だから温暖前線は通過前に雨が降って、寒冷前線は通過後に降るのか!」
こんな感じで指導していました。
どうでしょう?
「釣るべき魚」と「釣る方法」は教えていますが、「知識」は教えていません。
これを普通の先生が教えてしまうと、大体最後の雨の位置と動く方法で話が終わってしまいます。
実際多くの子がつまづくのはこの部分ですから間違ってはいません。
しかしこの子がわかっていなかったのは「前線と前線面の違い」なので、一方的に大多数がつまづくところの説明をされても、わかった気になるだけなのです。
子どもに与えるべき、本物の財産
先程の方法は非常に時間がかかります。
じっくり時間が取れないとできない指導というのが最大のデメリットではあります。
だから一般的な塾、まして大手ではできないんですね。
しかしこの方法で学んだ子は、自分で調べて学ぶ事ができるようになります。
もちろん一朝一夕でできるようになるわけではないので、何度もこの指導を重ねていく必要がありますが、一度身についてしまえば勉強方法は一生ものの財産になります。
そしてこの指導は親でも十分できます。
わが子であるという感情を抜きにして、時間さえたっぷり取れれば、ですが(^^;
でもできないわけではありませんから、教えていて喧嘩ばかりになるという場合には試して見る価値があるでしょう。
ファイには先程の相談者さんのように、親が教えてうまくいかないという方の相談が多数寄せられます。
その後、ファイに入会し、ファイの教え方で接してもらったところ、

「教えない方が勉強するようになったし、親子関係もうまくいくようになりました!」
というお声を多数頂いております。
やってみたけどうまくいかなかった、という方はファイへご連絡下さい。
ファイでは月1万円からお子様との関わり方までアドバイスしております。
教え方が変わるだけでも、お子様との関係が改善し、成績も変わってきますよ!







-1-1024x576.png)
-3-1024x768.png)
-58-150x93.png)



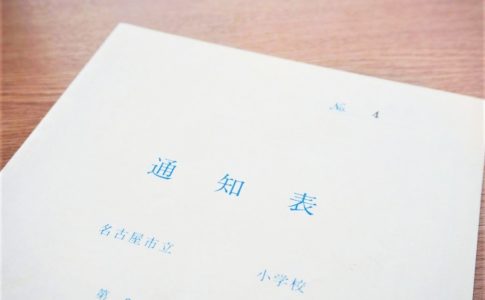
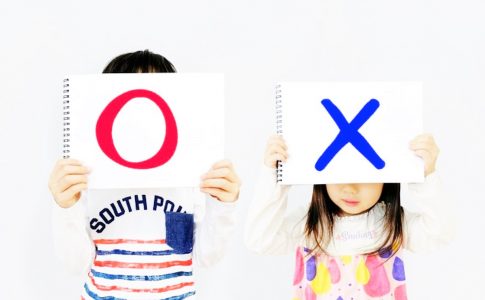









「塾で習ってきたはずのものが、家に帰って来ると全く解けず、つきっきりで教えています。全て教えています。最近は夫に『家事すらしなくなった』と言われるぐらい、家庭教師のように張り付いて教えています。にもかかわらず、結局点が取れません。こんな子でも何とかなりますか?」
東京都 日能研 小4