受験にどう役立つ?
分配法則は小学生でも習う計算テクニックの1つですが,なぜ分配するのか,わからずに操作として覚えている子も少なくありません。
なぜ分配するのかがわからないと,中学生になって展開の公式が出てきたときに,そちらも操作として暗記することになります。
ところが,なぜ分配するのかが分かっている子は,習わなくても,どう計算すればいいかがわかってしまいます。
小さなことですが,なぜその計算ができるのか,はしっかり考えさせたいところです。
分配法則はなぜ分配する?
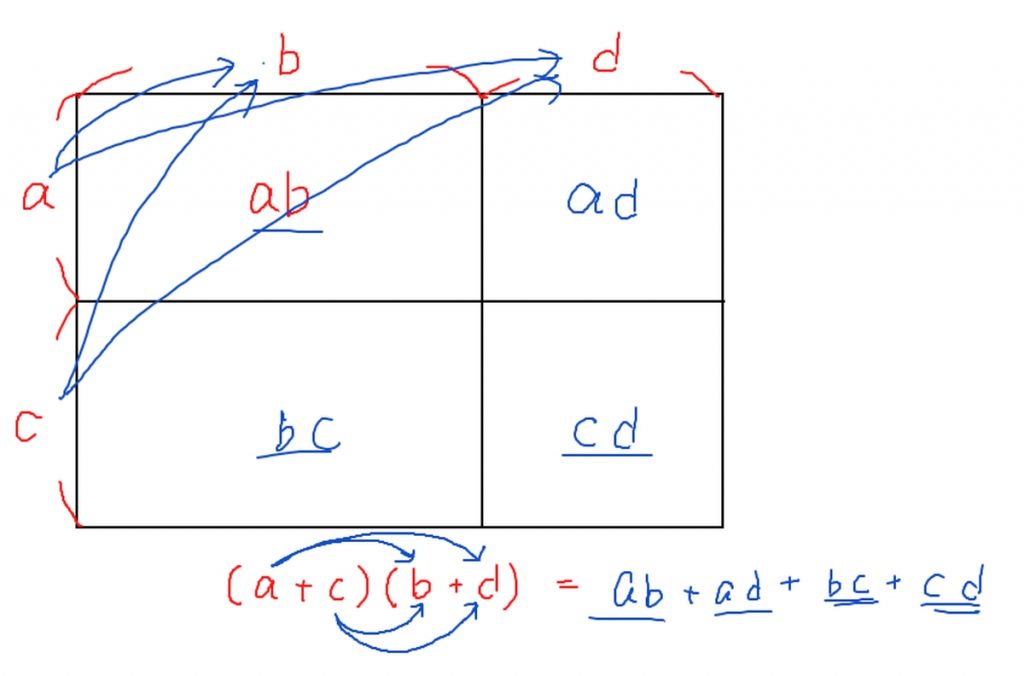
非常に単純で,小学生でもわかるくらい簡単です。
ます辺の長さがa,bの長方形を書きます。
この長方形の面積はabとなります。
小学生ならa×bですね。
次にこの長方形の横の長さをd伸ばします。
すると横の長さはb+dとなります。
この長方形の面積を求めると,
a(b+d)
となります。
さて,ここから分配法則ですが,
この面積は元のa×bの長方形とa×dの長方形に分けることができます。
この長方形の面積をそれぞれ出すと,
ab+ad
小学生なら
a×b+a×d
となります。
これが分配した後の式ですね。
つまり,分配法則とは,面積をバラバラに求めたもの,ということです。
(a+c)(b+d)も計算できるようになる
小学生ではあまり習いませんが,この原理が分かってしまえば,この計算もできるようになります。
要するに4個に分けて面積を求めて足す,ということです。
分配法則はよく出てくる言葉ですが,意味を知らずに解いていると後々困ることがあります。
理解できているか,ちょっと試してみて下さいね(^^)/











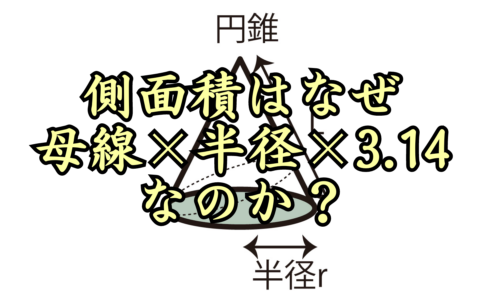









コメントを残す