目次
中学受験での直前対策
中学受験を目指していると、〇〇中対策講座というのをよく目にしますよね。
そしてオンライン授業でも、よく講座の必要性について相談を受けます。
確かに学校ごとに傾向も違うので、直前対策自体には効果があるでしょう。
しかし、それも自身のためにやるなら構いませんが、合格のためとなるとちょっと話は変わってきます。
まずは中学受験で対策講座をやるメリットについてお話しましょう。
中学受験における直前対策講座のメリット
直前対策講座で行われるもの
中学受験における直前対策講座で行われるものは、大体以下の5つです。
- ひたすら過去問
- 中学校側が提示した出題内容を基にした問題
- 塾や先生が独自に予想した予想問題
- 出版社や教材会社が出している予想問題
- その学校の傾向に合わせて寄せ合わせた問題
この中で、一番多いのはひたすら過去問です。
過去十数年分の過去問を集めてきて、ひたすら解かせる。
こうすることで出題の仕方を刷り込みやすいというメリットがあります。
次に多いのが、中学校側が提示した出題内容を基にした問題を使う場合。
実は問題そのものは開示されていなくても、お得意様になっている塾に対しては、ちょっとしたヒントが与えられていることがあります。
私立ですからね。
学校とはいえ、塾と仲良くなっておくことでメリットがありますから、内密にそういうやり取りが行われることもあるのです。
そのため、そういう情報を仕入れた塾は、それを基に予想問題を作り、対策を立てることができます。
この予想問題を抱え込んで、内部生のドーピングに使うこともあれば、外部生も募集して、金儲けに使うこともあります。
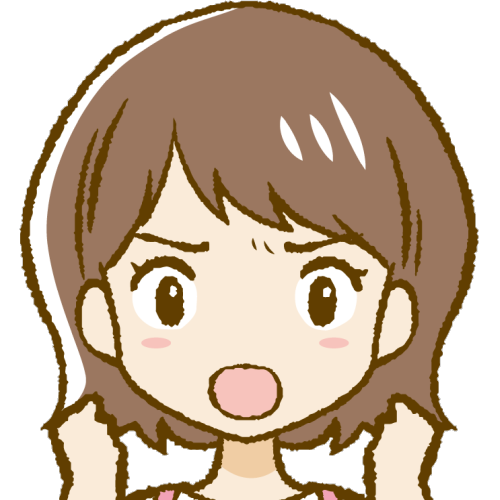
「え!?そんなのズルい!」
と思われるかもしれませんが、そこまで気にするほどの情報は流されていません。
本当に些細なヒント程度なことがほとんどです。
「身近なものに注目、かなぁ。」
とかそんな程度。
でもそんな些細な情報を躍起になって求める親が多いので、塾も学校も餌として用意しているのです。
最近は大体どこの塾にも同じ情報が流されますし、学校説明会でのお土産としてヒントが与えられることが多いものです。
なのでその情報自体を気にする必要はありませんが、その情報を基にして作られた予想問題をやっておけば、気休めにはなるでしょう。
そして対策講座の最大のメリットは、何といっても受験前の大切な時間、目の前に子どもがいて不安になる時間を減らせるといったところでしょう。
塾に行かせておけば安心と思っている親が多いんですよね。
なので、対策講座の料金は、ほとんど親の安心料みたいなものです。
学校の出題傾向に触れることができる。
今年出そうな問題に触れておくことができる。
とりあえず勉強させることができる。
目の前にいないので、親が安心できる。
中学受験における直前対策講座のデメリット
最大のデメリットは、何といってもコストパフォーマンスの悪さでしょう。
この直前期に本当にやるべきことは何なのか。
実は過去問でもなんでもありません。
自信をつけておくことなんですね。
対策講座で安心感を得られるかもしれませんが、それは一時的なものです。
メッキがはがれれば、すぐに自信喪失につながります。
〇〇中対策講座で出来が良ければ自信につながるかもしれませんが、新しいものに手を出して自信がつくことはあまりありません。
かえって不安を増幅させるだけです。
親も、不安の原因(子供)が目の前にいなければ、それが安心感と錯覚してしまいがちですが、根本的な解決にはなりません。
よって、直前講座とは免罪符的な役割でしかないため、家でできるのなら、その方がいいのです。
オンライン授業でも特別講座はやっておりませんが、むしろその方が自分の勉強ができるから効率がいいのです。
なお、私は大手塾にいた頃、塾生ほぼ全員が受ける直前講座を、自分の担当生徒は誰一人として受講させなかったことが3回あります。

「そんなことしたら、合格率が下がるから受けさせろ。お前の査定にも響くぞ。」
そう圧力をかけられ、脅されました。
しかしふたを開けてみると、それでも実績は塾でトップでした。
その結果を突き付けて、

「講座は無駄!廃止するべき。もっと他にやるべきことがある!」
と主張したところ、

「廃止にしたらいくら売り上げが減ると思ってるんだ!余計なことは考えずに売れる講座を増やすことを考えろ!」
と言われました。
もうお分かりですよね。
「直前」と書けば売れる。
みんなやってるからやる。
それが本音なんです。
塾は売上のために受講させたい。
あなたは何のために受講するのか、本当に必要なのか。
その価値があるのかよく考えて!
定期テスト対策として予想問題や過去問を配布する塾がある

「テスト対策として、今までの定期テストの過去問を配ってやらせている塾があるようです。そんなことしたらテストの点数取れるに決まってますからズルいと思います。そんなのってありなんですか?」
都内 公立中 中1母
塾によっては定期テストで点を取らせるために、作成した先生ごとの過去問を収集し、子ども達に解かせている塾があります。
オンライン授業でもよく持ってくる子がいます。
先生が異動になって別の学校に行っても、その地域の子に回して解かせるぐらい、念入りに先生対策を行っている塾もあります。
先生が予想問題を作成して子ども達に解かせる塾もあります。
学校の試験範囲に合わせて先生が1から作ることもありますし、過去の定期テストやワークから切り貼りして作る先生もいます。
いずれも非常に熱心な先生が多く、何とか子ども達に点数を取ってもらいたいと思っているいい先生だと思います。
しかし私はその方針には疑問を感じます。
先程話した通り、予想問題は子ども達自身が考え、作ることに意味があるのです。
先生や親が作り上げてしまえば、ただ単に点数を取ることだけに特化した勉強になってしまうからです。

「点数を取ることの何がいけないの?」
いいえ、いけないわけではありません。
確かに点数と取ることによってやる気を出し、頑張ってくれる子もいます。一時的な起爆剤としては十分効果があるでしょう。
カンニングをしているわけでもズルをしているわけでもありません。
どこぞの大手の塾は著作権法違反で訴えられて、負けていましたが。
大切なのは、あなたが親として何を学ばせたいのか、ということです。
点さえ取れればいいとは思っていますか?
オンライン授業の生徒で、実際にあったとんでもない弊害についてお話致しましょう。
予想問題を信じた子が全員成績が下がった事例
1教科を二人の先生が教えていた事例
恐ろしい実話をお話しましょう。
とある中学校で、同じ学年の同じ科目を、2人の先生が教えていました。
この先生を仮にベテランのO先生と若くて人気のあるY先生としましょう。
オールド(年配)からO先生,ヤング(若い)からY先生です。
テストの問題はO先生が作る事になっていたのですが、Y先生は教えているクラスの生徒から、どこが出るか教えて欲しいとせがまれました。
Y先生は若く人気のある先生だったので、おそらく生徒の気持ちに応えたいと思ったのでしょう。
Y先生は自分で作った予想問題を生徒にあげてしまいました。
その結果、どうなったと思いますか?
平均点が15点も開いた
なんとO先生が教えていたクラスと、Y先生が教えていたクラスで、平均点が15点以上差が開いてしまったそうです。
Y先生のクラスの子の方が点数が高かったと思うでしょう?
実は逆なのです。
実際は予想問題をやらなかったO先生のクラスの方が、平均が15点も高かったのです。
大きな原因はY先生が作った予想問題が大外れしていたこと。
Y先生は公平を期すために、O先生が作製した問題を見る前に予想問題を作って配布していたのです。
一方O先生のクラスは、O先生自身が問題を作成したこともあり、一切ヒントは与えられませんでした。
O先生は年配の先生なので、ルール通りフェアにいく事を重視したのでしょう。
ファイでは予想問題を無視させた
私はO先生のクラスの子も、Y先生のクラスの子も両方教えていました。
Y先生のクラスの子が予想問題を持ってきた時に、O先生が全然ヒントをくれないという話も聞いていたので、

「その予想問題、最後のチェックに使うのはいいけど、最初にそれをやるのはやめておけ。」
と言って、やらせませんでした。
O先生のクラスの子からは

「コピーが欲しい」
と言われましたが、それも

「必要ない。やめておけ。」
と言いました。
最初O先生のクラスの子は、

「ずるい!」
と言っていましたが、

「そんなに欲しいなら〇〇学院でも、〇〇塾でも配ってるから今すぐ転塾しろ。」
と突っぱねました。
大手塾の配布が悲劇に輪をかけた
実際近隣のいくつかの塾では生徒から手に入れたその予想問題を塾生に配布していたのです。
その中には受検勉強を教える大手の塾もいくつか。
個人の塾がやるならともかく、対話型やめんどうみを掲げる大手の塾がやっていたのです。
学校の先生が作った予想問題をコピー配布してドーピングで成績アップさせることの、どこが対話でめんどうみなのか。
学校の中でも先生が作った予想問題、かつ塾で配布している予想問題というインパクトから、ブームの様に予想問題信者が表れました。
学校で友達に
「お前の塾(ファイ)の先生、くれないの?ならやろうか?。」
と言われた子がいたそうですが、

「いや、いいよ。やる必要がないからくれないんだよ。それにこんなのに手を出して点数取れなかったら、切替先生に殺されるよ(^^;」
と話していたそうです。
同じクラスにいた別のファイの子が話してくれました(笑)
結果的にオンライン授業の塾生たちはこの予想問題に手をつけなかったそうです。
そのため、どちらの先生のクラスの子も普通に点数が取れていました。
この時、Y先生のクラスの子は、何人かクラスで1位を取っていました。
そしていつもは点数が取れない子も、この時はクラスで上位に入り込んでいました。
学校ではこの15点以上の平均点の差が騒動にまで発展しました。
塾経由でO先生のクラスの子にもY先生の予想問題が出回っていたことを考えると、予想問題を信じた子と、やってない子の平均点の差は、もっと大きかったことでしょう。
大人の予想を子どもは信じやすい。
この話は予想問題を過信した子としない子の差がハッキリと点数の差で表れた極めて稀な例です。
しかしここまで極端ではないにせよ、小さなものを含めれば割とよく見かける光景なのです。
よく聞くのは「○○塾が作った定期テストの予想問題を手に入れた」という話。
ファイでも世代が変わると毎年1回は耳にします。
もちろんファイではそんなもの使わせませんが、子ども達からしてみると、それをやっておけば点が取れそうな気がして仕方ないのです。
大人だってそうでしょう。
学校の先生が作った予想問題を塾の先生がコピーして配布するぐらいですから。
大人が勝てない予想という魅力に、子どもが勝てるわけもないのです。
そしてそれを信じてしまった結果、それだけに集中してしまい、他をやらなくなる。
だから点が取れなくなってしまうのです。
予想問題を信じてもいい例外事項
予想問題が絶対にいけないのかというと、そうでもありません。
もしテストを作る先生が作った予想問題なら話は変わってきます。
テストを作っているという事は、出題内容を知った上で、勉強させたいところを問題にできますからね。
その場合、先生もハッキリと明言しているはずです。
「ここは必ずできるようにしておけ。」と。
また、検定や資格試験にも効果はあります。
これらはふるい落とすことを目的としているわけではなく、知っておいて欲しい知識を有しているかを確認するテストだからです。
入試や定期試験という意味では、いわゆる下位層の子にとっては、予想問題が効果的な場合もあります。
なぜなら、そもそも今まで勉強していないので、少なからず勉強するきっかけにはなりますから。
予想問題に頼ると、伸び悩みを起こす
平均点を狙っているような子が予想問題を過信すると、伸び悩みを起こします。
また、受験勉強においては問題外です。
よく四谷大塚の組み分けテストや中1の中間テスト、期末テストといった定期試験で予想問題を希望される方が多いのですが、これらの試験を予想問題に頼ると、ほぼ例外なく伸び悩みを起こします。
なぜならいずれ予想問題が通用しなくなるからです。
受験までずっと予想問題に頼るつもりですか?
過去問はあくまで出題の仕方や傾向をつかむためのものであり、予想問題だけをやって乗り切るような勉強をしていては、進学後に落ちこぼれます。
予想問題を中心に勉強するという事は、知識の抜けを沢山放置していく事になりますからね。
起爆剤として使うのはありでも、継続して使うものではないでしょう。
山かけ、予想問題は思考力を殺す
以上の理由から、ファイでは予想問題は作りません。
もちろん教務の参考として、ある程度は予想はしてあります。
しかし予想はしてあっても予想問題は作りませんし、配布もしません。
もちろん「ここから出るよ!」と学校の先生に言われたものに関しては、しっかり練習をして対策を練ります。
もしその単元に抜けがあると思えば、その単元を中心に勉強するように誘導はしていきます。
しかしそれでもあくまで単元までです。
どんな問題が出題されるかまで詳細を話す事はありません。
先程から話している通り、予想問題を作成すると、子どもはそれを過信しすぎ、大きな弊害となるのです。
そこに載っていないものは必要ないものだといって排除してしまうのです。
学校で子ども達が作った予想問題を与えられても、そこから勉強を始めて、それだけを完璧にしようとします。
それでは本質的な力は身に付きません。
方針や絞り込む方法は教えますが、予想問題を与えて「これだけやっておけ!」といった勉強のやり方は教えません。
大人の予想は子供の可能性の幅を狭めてしまいますから。
あなたはどういう子どもになって欲しいですか?
点数さえ取れればそれで満足ですか?
予想問題に手を出したいくらいうまく行っていないのなら、まずは学習法診断をお試し下さい。
予想問題よりも、現実的かつ、長期的に成功しやすい勉強法をご提案いたします。

番外編
中学生のテスト直前の山かけ
テスト直前の山かけ。
経験がある方も多いのではないでしょうか?
勉強が終わり切らなくて、最後に絞り込んで「お願い出て!」と神頼みして試験に挑む山かけ。
人によっては受験前日までやっているという人も。
果たして山かけはした方がいいのでしょうか?
しない方がいいのでしょうか?
もちろんしなくて済むならそれに越した事はありません。
ちゃんと前もって計画的に終わらせておけばいいだけの話ですからね。
しかしそうはいっても塾でやることは多くて復習が追い付かない。
習い事もやっているとなおさら。
さらに中学生なら部活もあってなかなか終わりきらないのが現状。
そんな時はやはり山かけに頼って少しでも点数を稼ぎたいと思うもの。
本当に時間がない、取れない時に限りますが、そんなときは思い切って山かけしちゃって下さい(笑)
山かけはイチカバチカてきな感じがありますが、実はそうではないのです。
当てられる人は当てられますし、当てられない人は当てられません。
つまり「山かけの技術」で大きな差が出るのです。
正しい山かけのやり方とは?
山かけの技術とは何かと言いますと、テストに出る場所が分かっているかどうか、です。
何も考えずに試験勉強をするよりも、出るぞ!って意識して勉強した方が集中力も上がりますし、もし出ればラッキーです。
出なかった時は悲惨な事になりますが…
でもそれはそれでいいんです。
山かけの技術がないということは、人の話を聞いてないという事がわかるわけですから(笑)
山かけが成功する子は、ポイントを押さえられているとも言えるわけです。
そのため、山かけをさせること自体は悪いこととはいえません。
当たったかどうかをしっかりと検証し、あてたことではなく、ポイントを押さえて勉強できたことを褒めてあげて下さい。
もちろんまぐれの可能性もありますが。
ただし、ひとつ禁止事項があります。
親や先生が山かけを手伝ってしまってはいけません!
絶対にです。
大人が山かけに関わった途端、良い点数が取れなかった原因をその大人のせいにします。
自分の責任において山かけさせる事が一番大切なのです。
予想問題は何のために作る?
中学校によっては生徒が予想問題を作り、みんなに配布するという学校もあります。
これは何のためにやっているのでしょうか。
実はこれも当てさせることが目的ではないのです。
予想させることによって、ポイントを意識させる効果があるのです。
問題作成する子はどこが出そうか、真剣に考えます。
その中でポイントを押さえる力が養われるのです。
そして子ども達は、子ども達自身が作製した予想問題を手にすることにより、「予想する」という事自体に刺激を受けます。
「もし私がこれをやらずにこれがテストに出たら、みんなは点数が取れてしまう。」
そういう気持ちも子ども達を焦らせるのに一役買います。
時々先生がアドバイスして作成されるものもありますが、あれは問題作成者を守る意味もあるのです。
あまりに的外れな問題を作って配布してしまったら、後で子ども達から批難されるかも知れませんからね。
そのため、みんなにできて欲しい重要な部分は外さないように、補助をするのです。
もうお分かりですね?
学校で子ども達が作る予想問題は、子ども達自身の成長を促すための一環として行われるものであり、直球で点数を取りに行くための予想ではないのです。
山かけがうまく行かない方は、学習法診断でテストの分析をすることもできます。
どんな勉強をすれば、テストで点が取りやすいか、がハッキリします。






-1-1024x576.png)
-18-150x93.png)
-12-150x93.png)
-18-485x300.png)

-2-485x300.png)


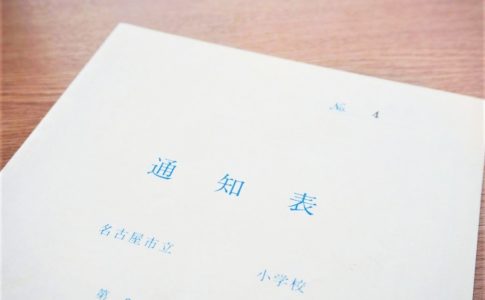

-13-485x300.png)





「今度Y塾ではK中対策講座(NN志望校別コース)をやるみたいなのですが、そのような直前対策講座は受けた方がいいのでしょうか。」
早稲田アカデミー 小6 母