場合の数は公式の暗記からやると失敗する
結論から言うと、ファイのオンライン授業では、場合の数の公式を教えませんし、覚えさせることもしません。
なぜなら、式など覚えずとも解けるようになるからです。
それどころか、基本的に何も教えませんが、勝手にできるようになります。
大切なのは、いかに問題の本質に気付くけるように導くか、です。
オンライン授業ではどんな扱いをしているのか、実例を基に紹介しましょう。
まず場合の数というのは「全部で何通りあるか」というタイプの問題。
中学受験では場合の数までが一般的で、中学生になると、確率になります。
小学校では「並べ方と組み合わせ方」というような単元名でサラッと出てくるだけで、大してやりません。
それゆえ、小学校では基本的に書き出して練習し、中学受験では計算方法を公式として覚えさせて解かせます。
特にサピックス、日能研、四谷大塚、早稲田アカデミーといった大手はその傾向が強く、繰り返して覚えさせる傾向にあります。
しかしこれをやると、場合の数が全く解けなくなるのです。
なぜなら練習する機会も少なく、書き出すのも大変。公式は覚えていれば解けますが、忘れると全く解けません。
そして難関中学では単純に式に当てはめれば解けるような問題は出ません。
つまり、難しくなればなるほど、公式そのままでは通用しなくなる単元なのです。
しかも久々に練習するときには頭がリセットされているので、応用や発展まで入りません。
公式を丸暗記するとそんな繰り返しになってしまうのです。
ファイの子はやらなくても忘れない。
そんな場合の数の問題をオンライン授業で扱ったので、半年以上前に教えた子にも声をかけて解かせてみました。
半年以上前に一度やったきりで、それ以降演習もしておらず、久しぶりに扱ってみたのですが、しっかり解けていました!
しかも教えたといっても、大したことは教えていません。
一方、質問してきたのは、サピックスで扱ってから1か月も経っていない子でした。
サピックスで何度繰り返しても全くできるようにならなかった単元も、ファイでは1度教えただけで長いこと使える状態のまま頭に残っています。
それがハッキリと表れたので嬉しいですね(^^)
ちなみにサピックスだった子が解けなかった原因は、公式に頼ろうとして、思い出せなかったためです。
さて、ではファイでは一体どうやって教えているのでしょうか。
実はそんなに難しいことではありません。
ご家庭でも真似できますので、ぜひやってみて下さい。
上澄みではなく、場合の数の本質を教える
一般的な中学受験の塾でも最初に考え方を教えますが、同時にすぐ公式を覚えさせようとします。
しかも公式の方が圧倒的に早い。
これを最初に経験させてしまうと「公式を覚えればいいや」となってしまうのです。
ではファイではどうするのか。
実はファイも公式を扱います。
しかし中途半端に扱いません。
小学生でも、高校数学であるP(順列:パーミュテーション)とC(組み合わせ:コンビネーション)を教えてしまいます。
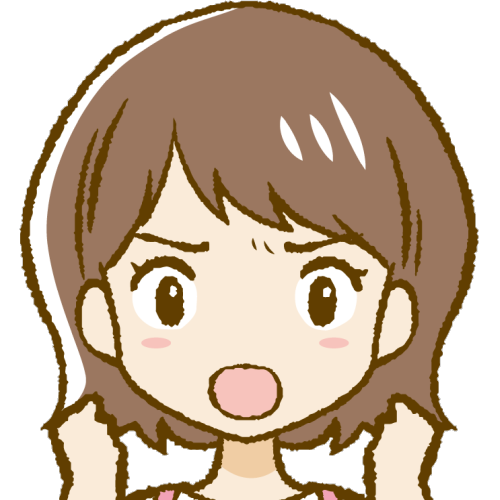
「なんだ、ファイさんだって公式を教えているんじゃないですか。」
いいえ、そこが決定的に違います。
ファイでは教えていません。
高校数学レベルまで、自分で気づいて学んでもらって、その上で「これ、実は高校数学の内容なんだよ。」と教えています。
つまり、自分で到達できない子にはそこまで教えていません。
これにより、どうしてこの計算になるのか、しっかりと押さえることができるのです。
するとしばらく経ってからでも、忘れずに解けるのです。
というより、そもそも公式を暗記させていませんしね。
暗記していないのですから、忘れることもないのです。
その証拠に、解いたものを見ても、PとCは忘れてしまって書いていないことが多いのです。
小学生にとってP、Cはただの記号であり、意味を持っていないためです。
しかし解き方はわかっているから、中学受験程度の問題なら放っておいても解けてしまうのです。
どうやって教えるの?
先程話した通り、小学生にいきなり高校生のP、Cを教えているわけではありません。
手順があります。
実際、小4のときにどんなやりとりをしたのか紹介しましょう。
20人の中から学級委員を2人選ぶとき、何通りの組み合わせができるか求めなさい。

「先生、組み合わせって何?どういう意味?」

「色々な方法で組み合わせたとき、何通りの組み合わせができるかって意味だよ。」

「この問題だったら、誰と誰が学級委員をやるかってこと?」

「そういうこと。」

「どうやって求めるの?」

「どうやって求めればいいと思う?」

「えーっと、書いていけばいいの?」

「そうだね、全部書き出せば出るよね。」

「えーっと、こんな感じで?」

「そうそう。」

「この問題も同じ?」

「そう、数が多くなってるけど同じ。」

「えー!?全部書き出すの!?」

「やなの?」

「ヤダよ。めんどくさいもん。」

「なら簡単な方法でやればいいじゃん。」

「どうやるの?」

「やだ、教えるのめんどくさい。」

「えー何それ!」

「書き出すのをめんどくさがってるんだから、先生だって教えるのめんどくさがってもいいでしょ!」

「じゃあ解くから、そしたら教えてよ!」

「いいよ。」
30分ぐらいかけて、ひたすら書き出しました。
しかもこの間に、何回も書き出し間違いをして、やり直しています。
これだけのために、ノートを10ページ以上使っていました。

「やっと解けた!」

「よく頑張ったね!」

「何かが足りなくて、でも何が足りないのかわからないから探すの大変だった…」

「そうだよね。どうやって書き出したの?」

「こうやって順番に…」

「うん、いいんじゃない?そしたら、ちょっと書き方を整理してこうやって書いてみて。」

「こう?」

「そうそう。何か気付かない?」

「1ずつ減ってる!」

「でしょ?それがわかったら書き出す必要なくない?この問題解いてみて。」

「こんな感じ?あ、合ってる。うわ!めっちゃはやっ!」

「でしょ?この規則をまとめたのを高校ではP、パーミュテーションっていうんだけど…」
という流れでP、Cを教える前段階、いわゆるP、Cの基礎の部分までは自力で持っていかせています。
もちろんここではポイントとなる部分だけを抜粋してやり取りを書いたので、実際にはこの間に似たような問題をあれこれ解かせて、ここまで誘導する流れを作っています。
盛り込みすぎない!
この時、考え方に一貫性を持たせるのがポイントです。
一貫性がないとパターン化し辛く、子どもは公式の暗記に走ろうとします。
そのため、一貫性がない問題は省かなければなりません。
でも中学受験のための塾では、むしろ網羅しようとするため、あらゆるパターンを教えようとします。
これがファイのオンライン授業とは決定的に違う所です。
例えば、選び方は何通りという問題をやっているのに、サイコロの問題を間にはさむというのは避けて下さい。
違う解き方のものを混ぜると混乱してしまうのです。
1つのパターンに集中して気付かせることが大切なのです。
ご家庭で教える時にはここに注意して下さい。
ここでは場合の数を例に出しましたが、ファイのオンライン授業では公式を教えませんし、覚えさせることもしません。
そして何度も同じ問題を解かせて練習させるといった、塾の王道ともいえるやり方も推奨していません。
むしろ、何度も教えなきゃ解けるようにならんような教え方をしているのか、と思っています。
まぁ費用対効果を考えれば仕方のないシステムなんですけどね。
何度やっても解けるようにならないのは当たり前です。
解けるようになっていないのに、同じことを繰り返しているのですから。
ファイのオンライン授業では、月1万円で勉強の効率を上げるアドバイスをしています。
塾のシステムについていけないのであれば、別のやり方を試してみてはいかがでしょうか。






-1-1024x576.png)
-3-1024x768.png)
-54-150x93.png)
-52-150x93.png)




-10-485x300.png)


-8-485x300.png)





「場合の数が何度練習させても、かける場合と足す場合の区別がつきません。どういうときにどんな式を使うのかわかっていないようなのですが、どうすればできるようになるでしょうか。」
SAPIX 小4 母