受験で必須な米騒動
1918年に富山県で起きた米騒動。
「栄養低い、パンより米!」
中学受験でも高校受験でも重要なこの出来事ですが、ただ米騒動が起きたとして覚えている子も少なくありません。
しかしここをちょっと突っ込んで考えるだけで、戦時中の戦略から経済まで、公民で出てくる単元を学べてしまうのです。
先日のオンライン教室で米騒動が出てきたので、その時のやり取りを紹介しましょう。
実はシベリア出兵は直接の原因ではない
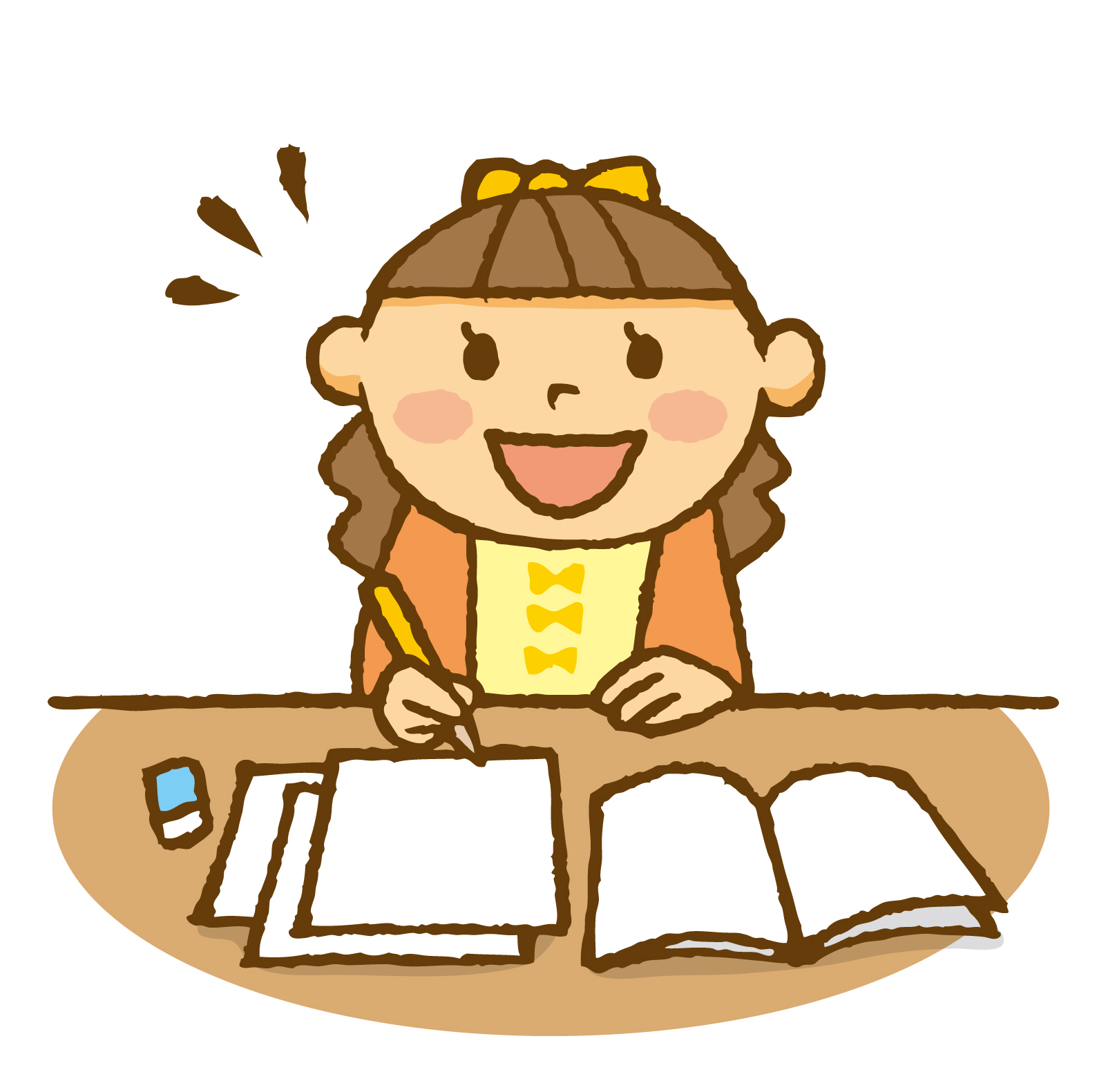
「えーっとシベリア出兵で米を買い占めたから。」

「シベリア出兵で米を買い占めると、なんで米騒動が起きるの?」
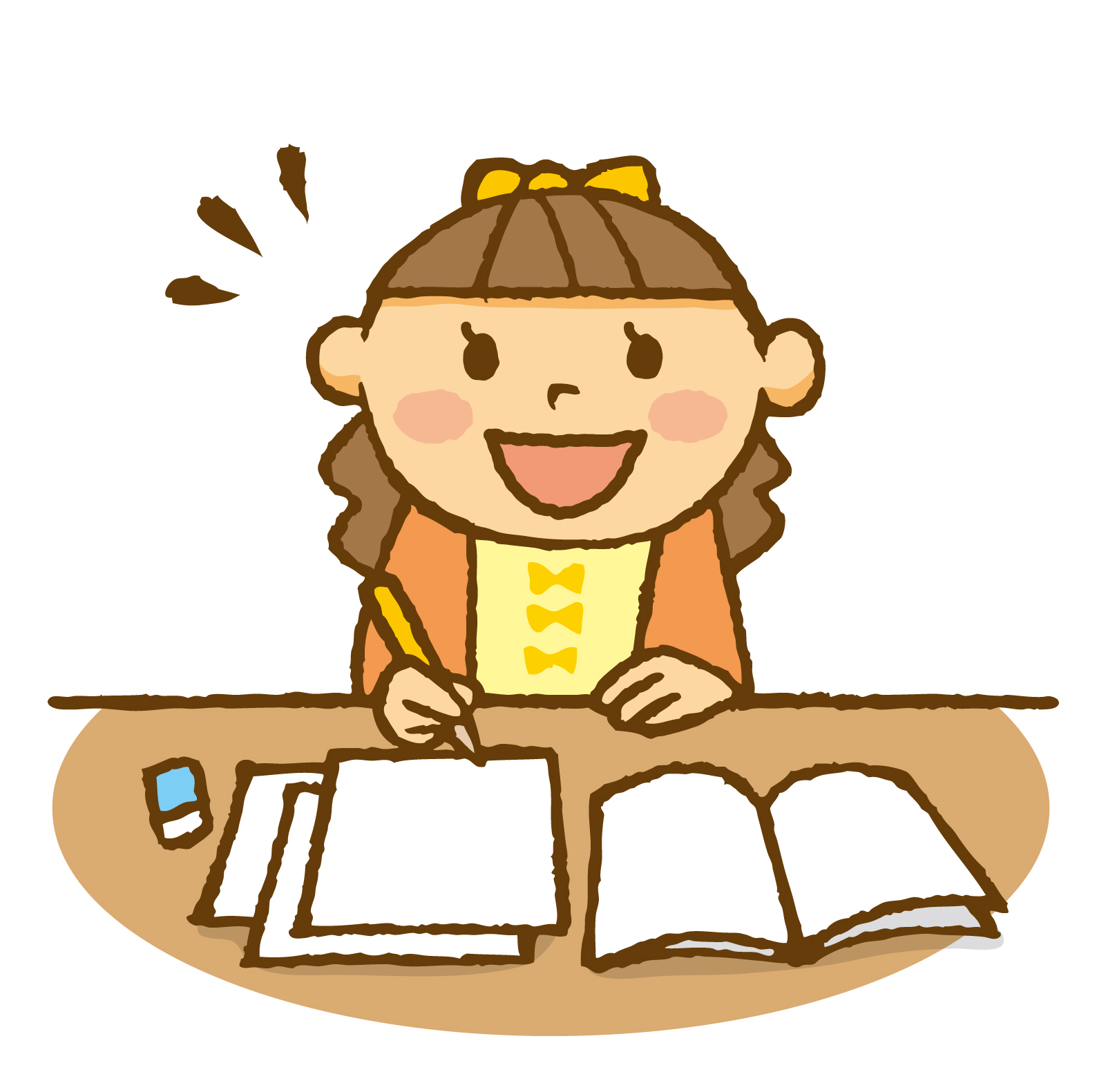
「お米を買い占められて農民が食べるお米がなくなったから。」

「兵隊が食べるお米って戦争に行っても戦争に行かなくても、どの道食料として必要なお米でしょ?なんでそれを買い占めたら米が不足するの?」
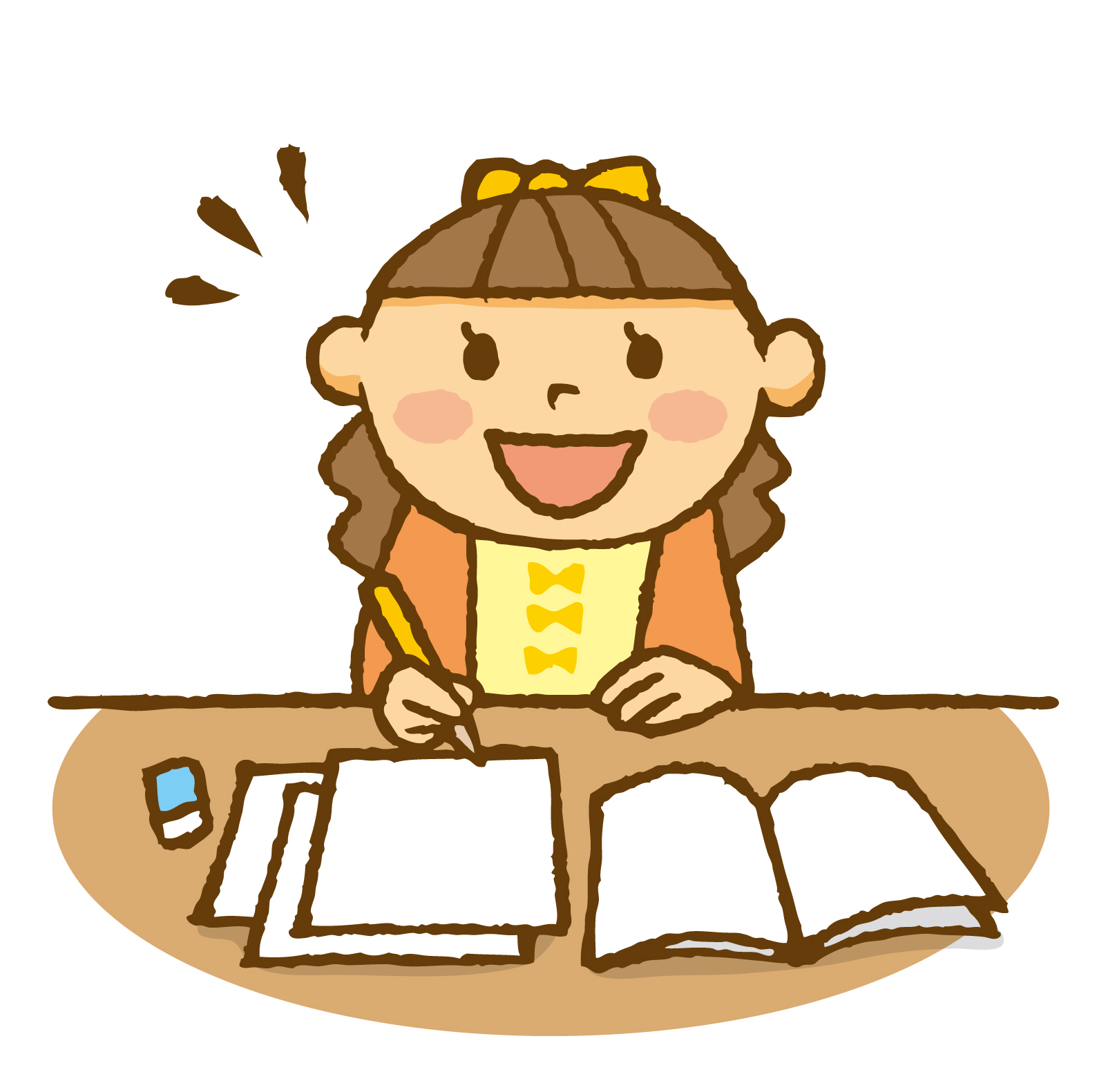
「え?どういうこと?」

「例えば、今日のお昼に食べるお米。それを今日は公園で食べることにしようということでおにぎりにして持って行った。確かにお米は減るけれど、家で食べても公園で食べても消費する量は変わらないでしょ?」
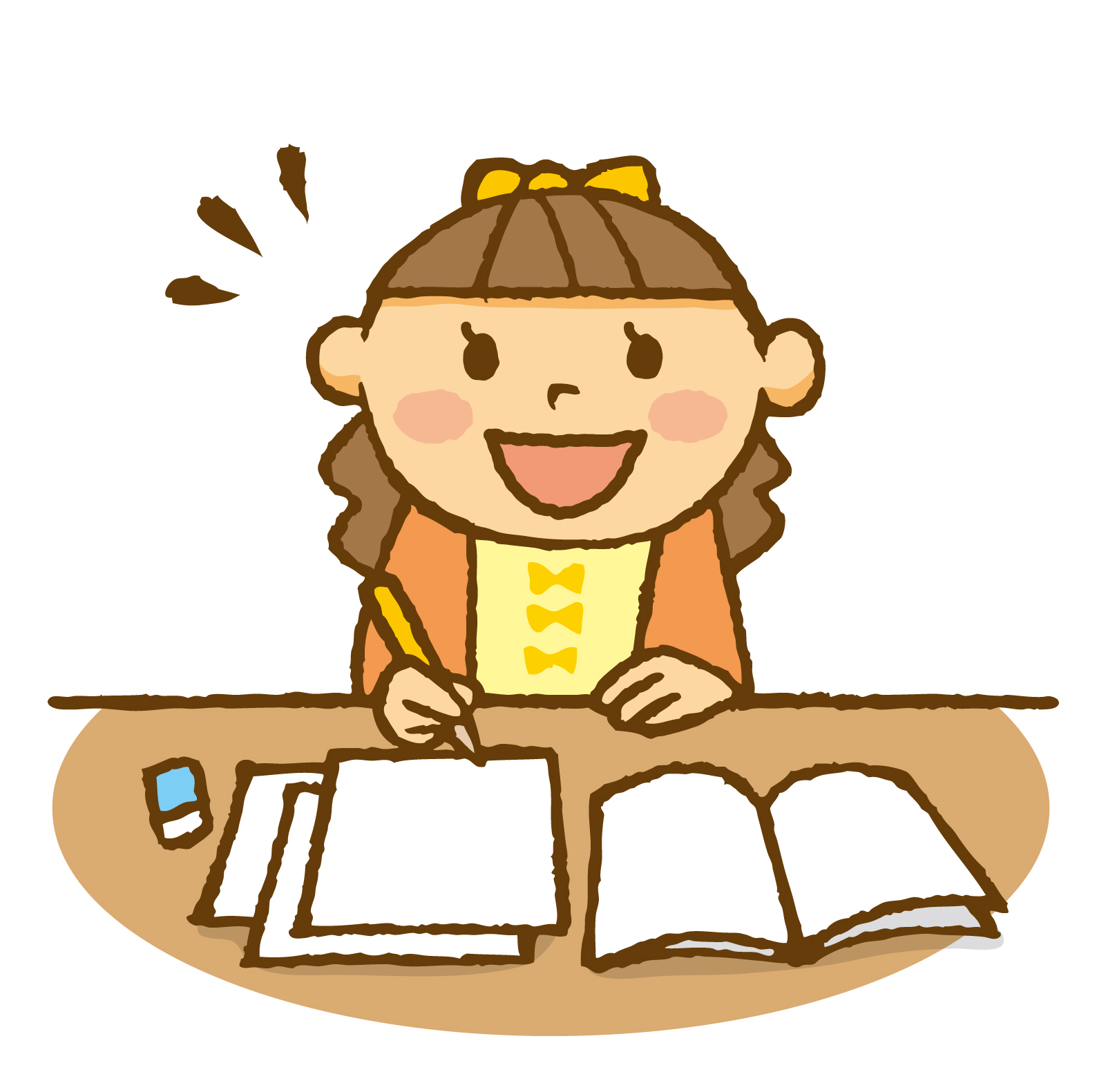
「あ、そうか。なんでお米が足りなくなったんだろう。」

「実はシベリア出兵はトリガーに過ぎず、すでに日本国内では米不足になっていたんだよね。」
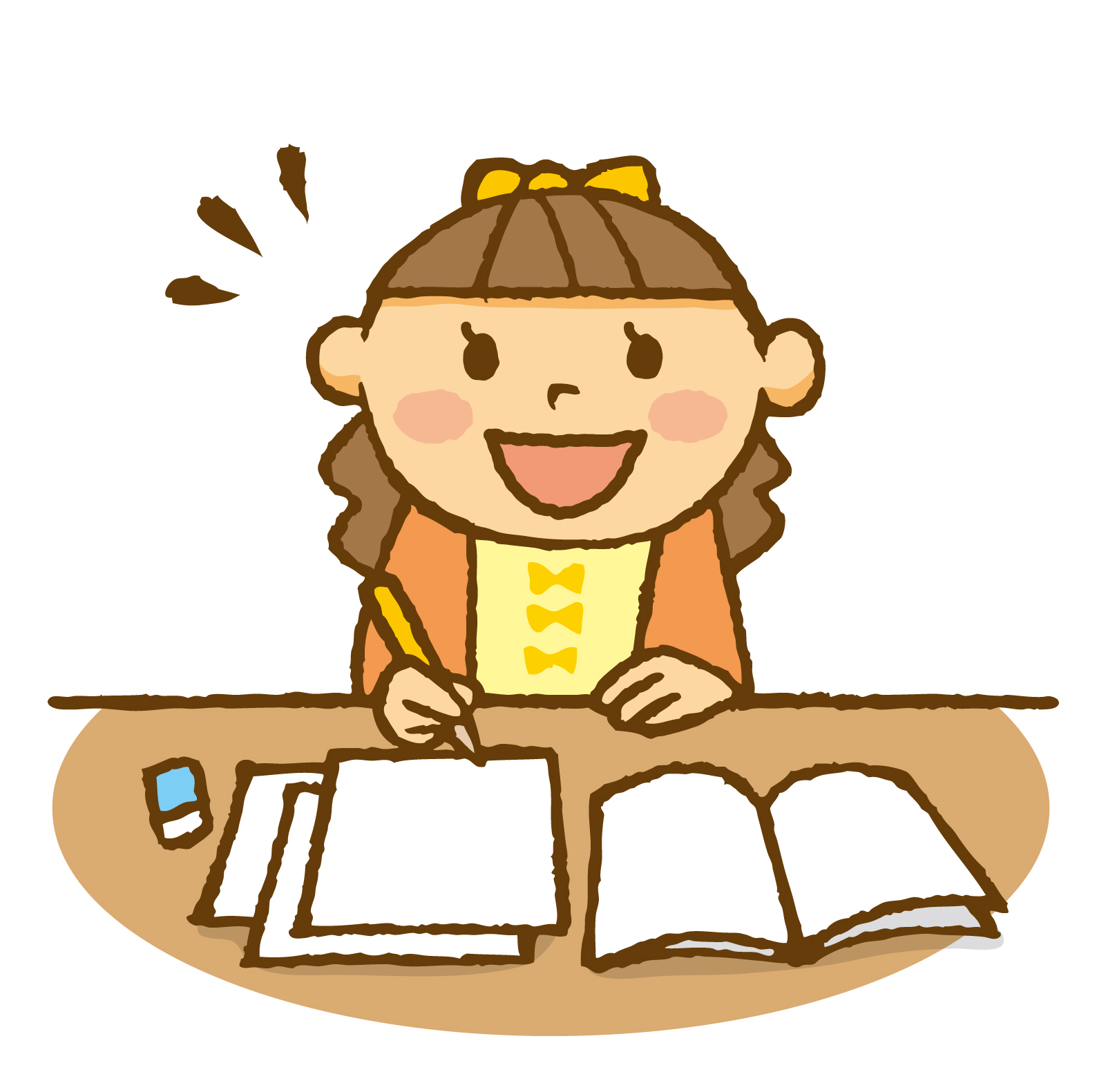
「不作?」

「いや、江戸時代からの食生活の変化かな。」
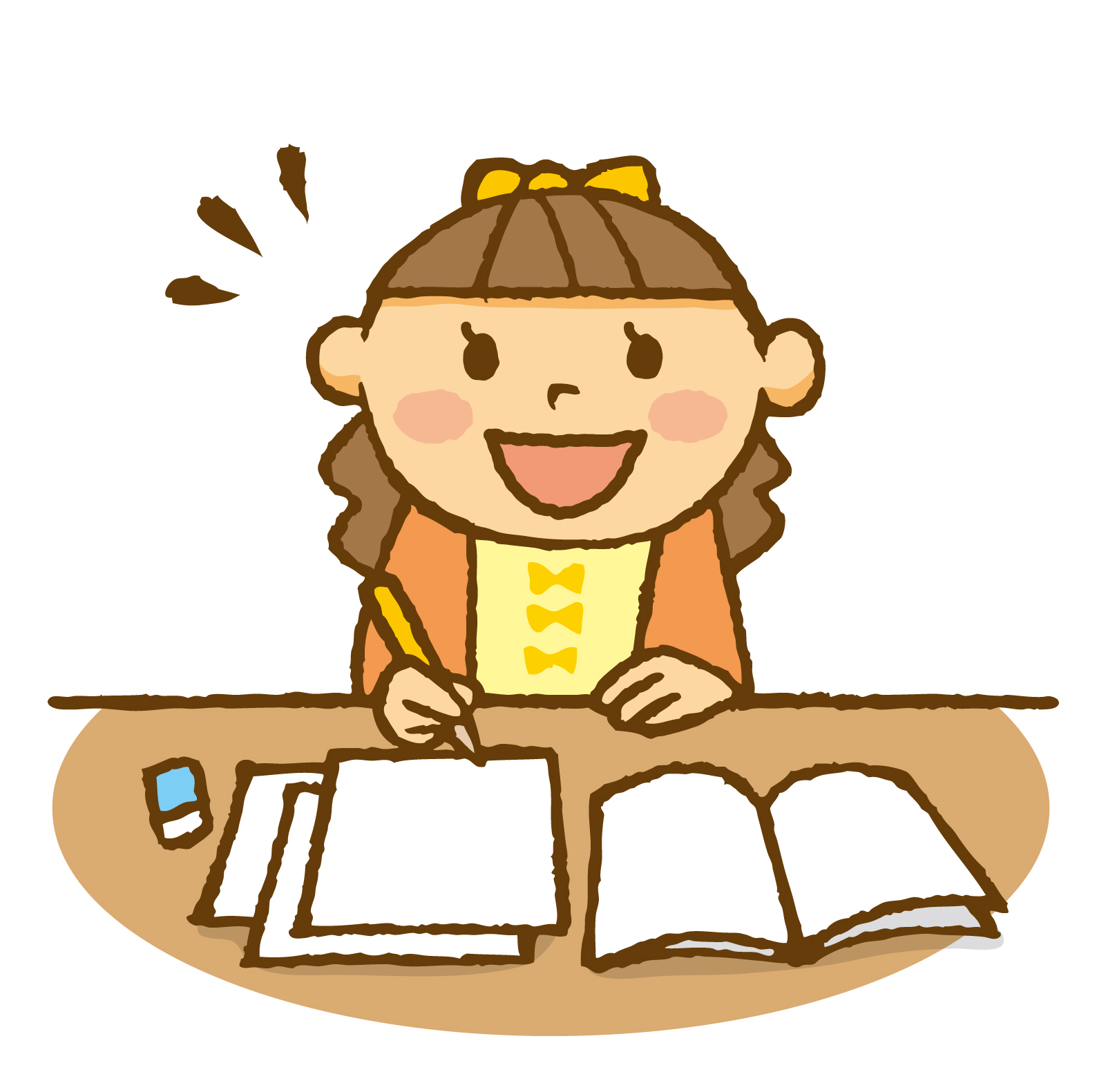
「あ、農民はお米を食べてなかったんだ!」

「そう、何食べてたの?」
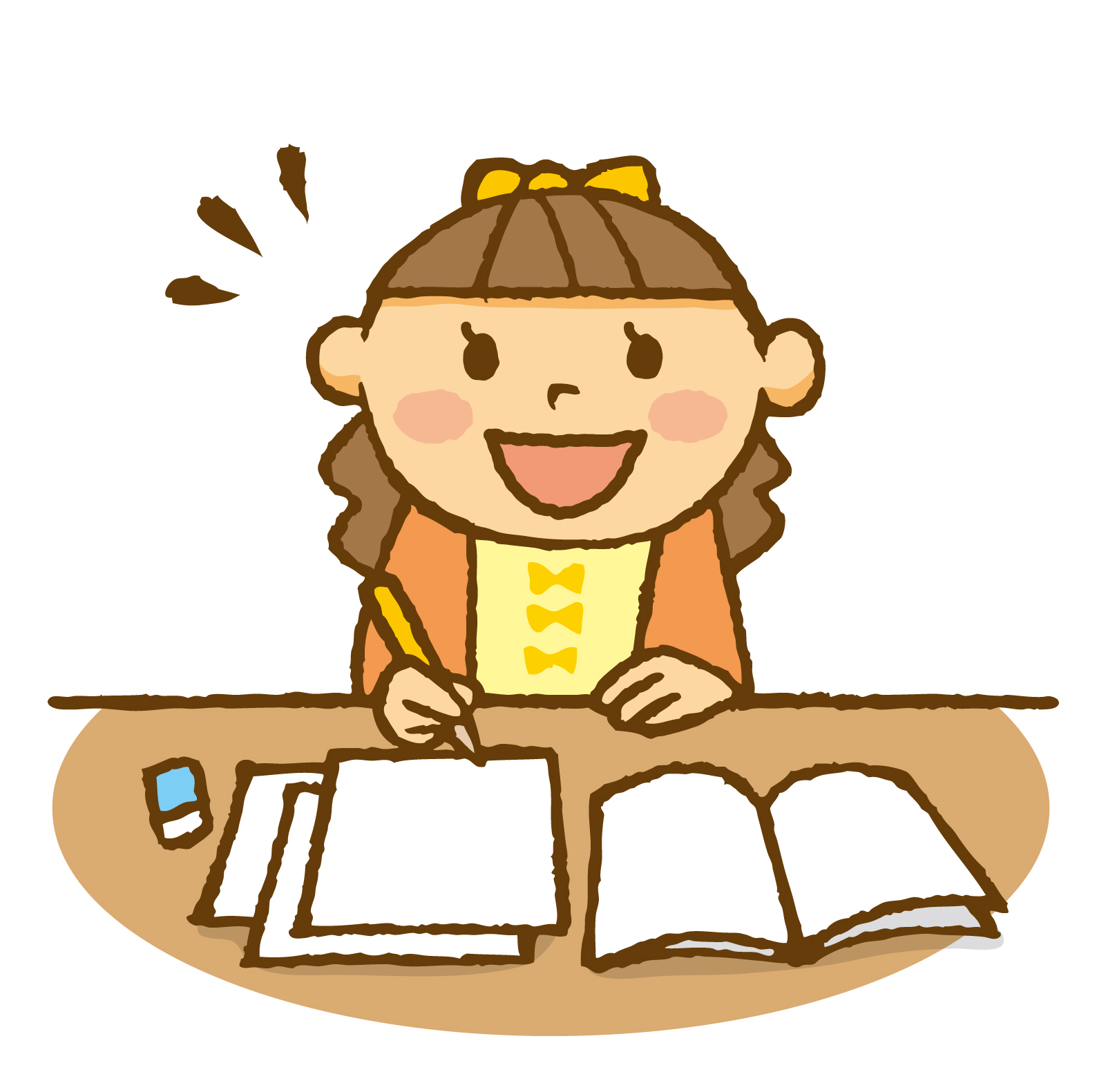
「ひえやあわ!それがお米に変わったから、米の需要が増えたんだ。」
なぜ食生活が変わったのか

「ではなんで今までひえやあわを食べていたのに、お米を食べるようになったの?」
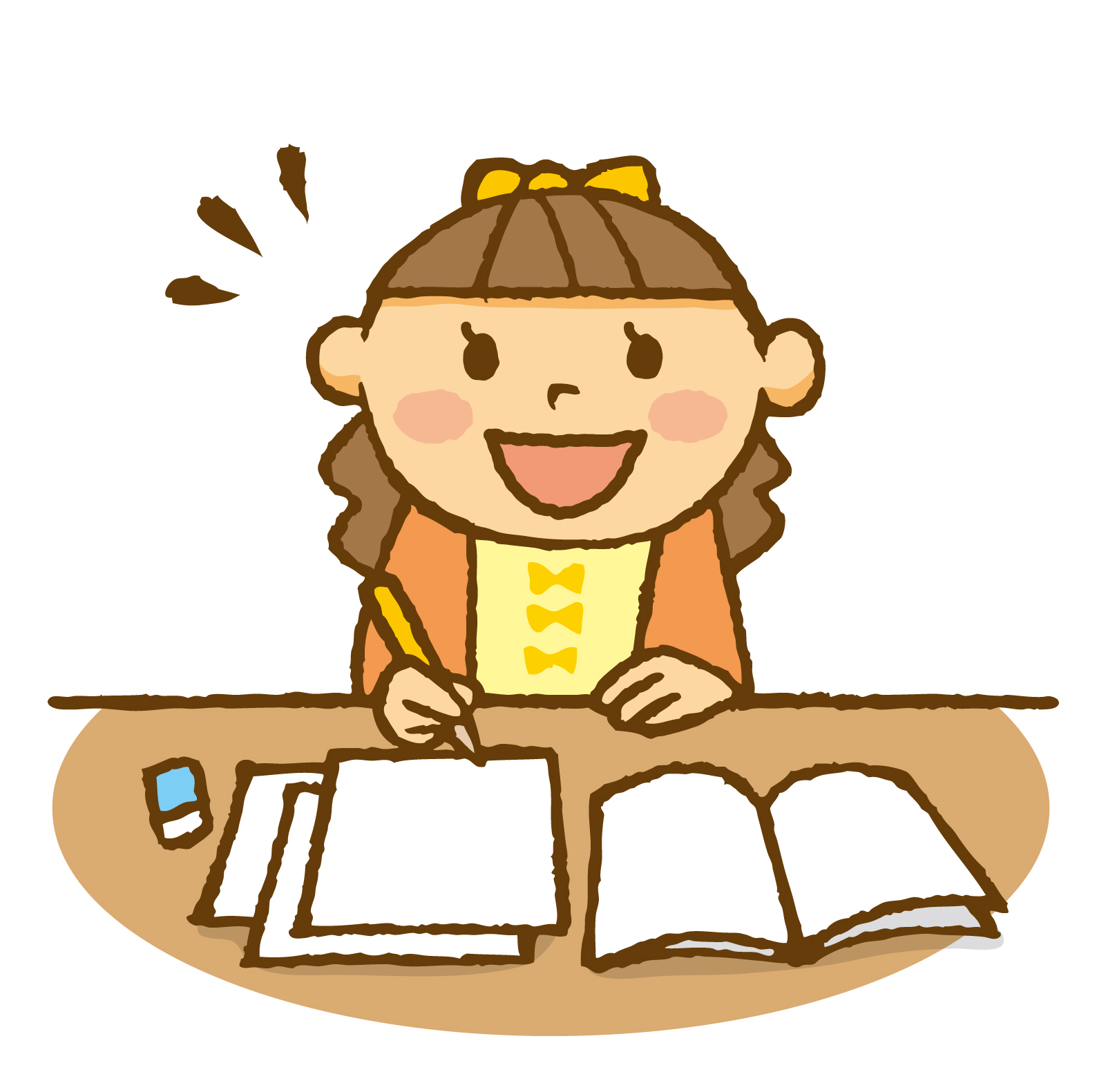
「お米のおいしさを知ったから?」

「たとえおいしさを知っていたとしても、昔の農民はお米を食べられなかったかな。」
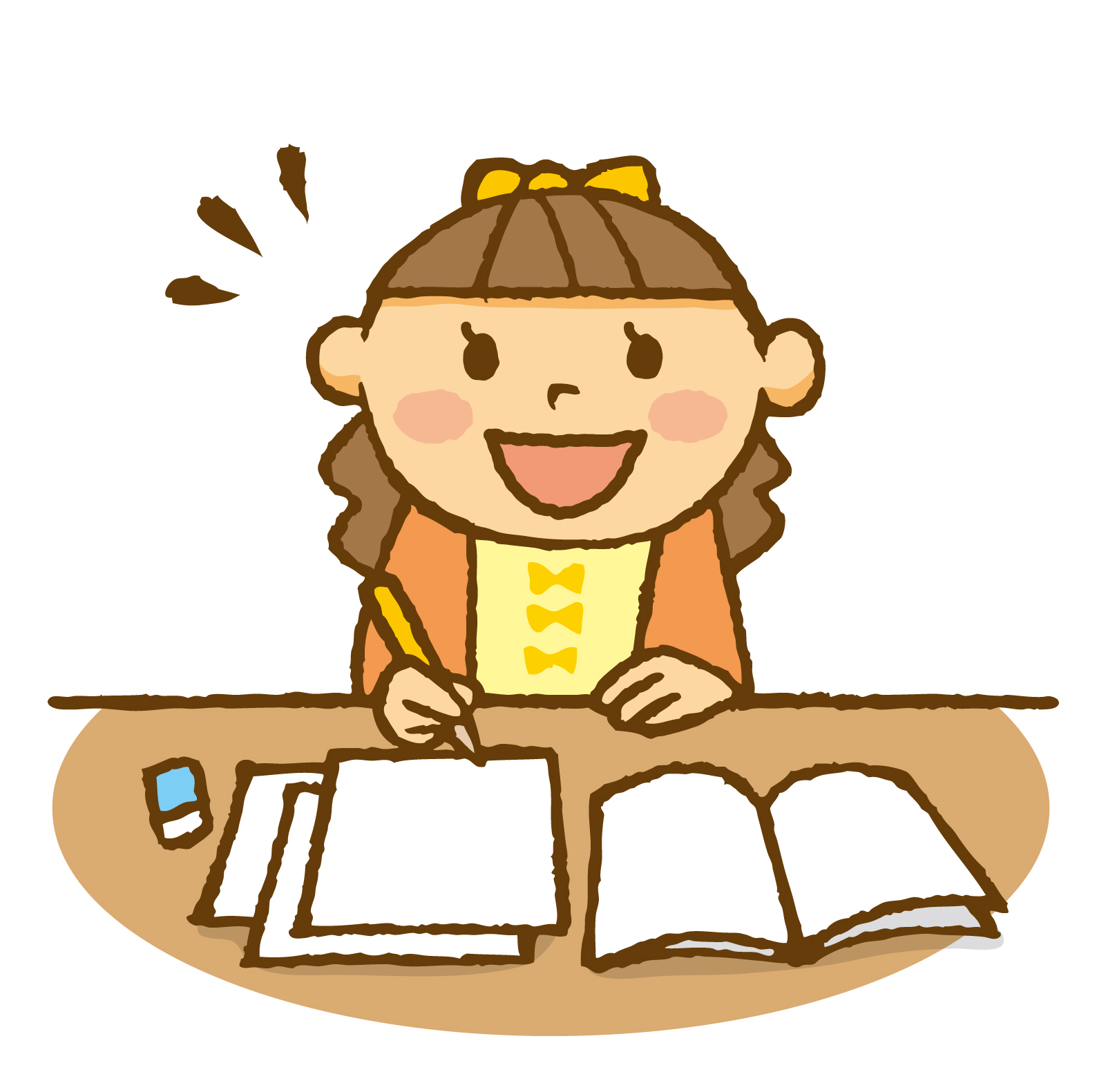
「なんで?買えなかったから?」

「そう、買えなかった。じゃあなんで買えるようになった?」
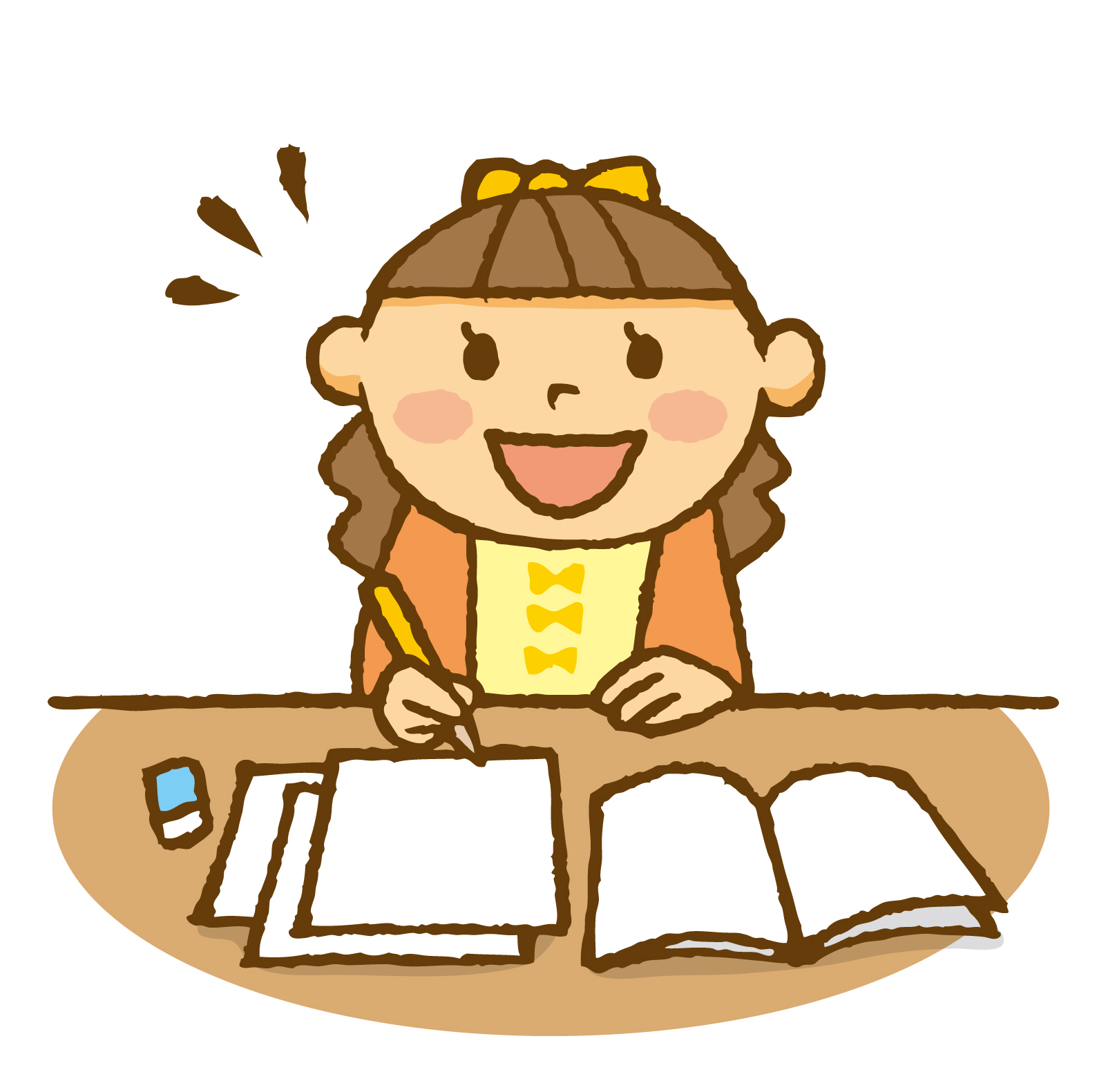
「稼げるようになったから?」

「そう、なんで?」
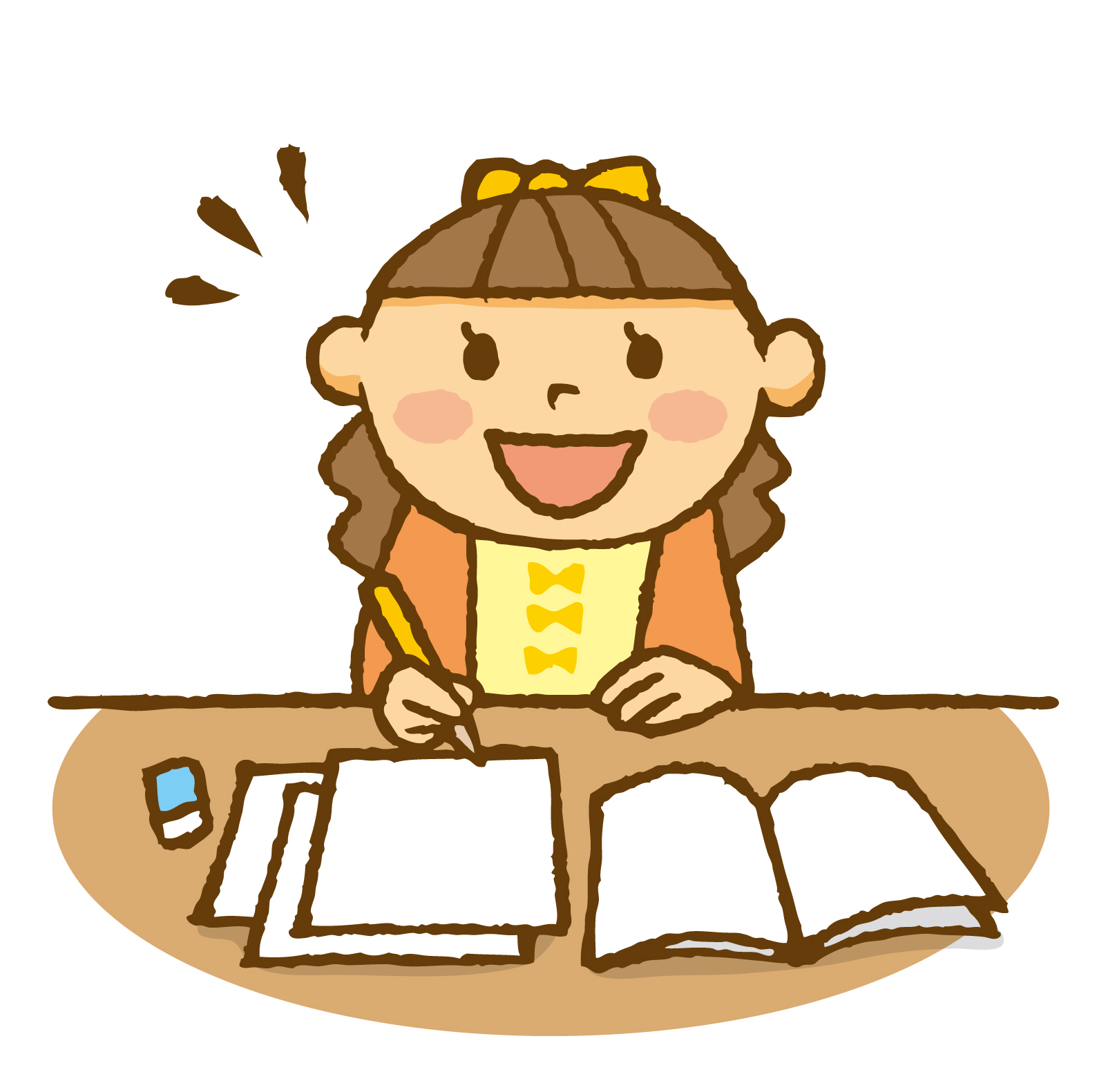
「んー。技術が向上したから収穫量が増えた?」

「それ以上に国全体が儲かる出来事があったからかな。」
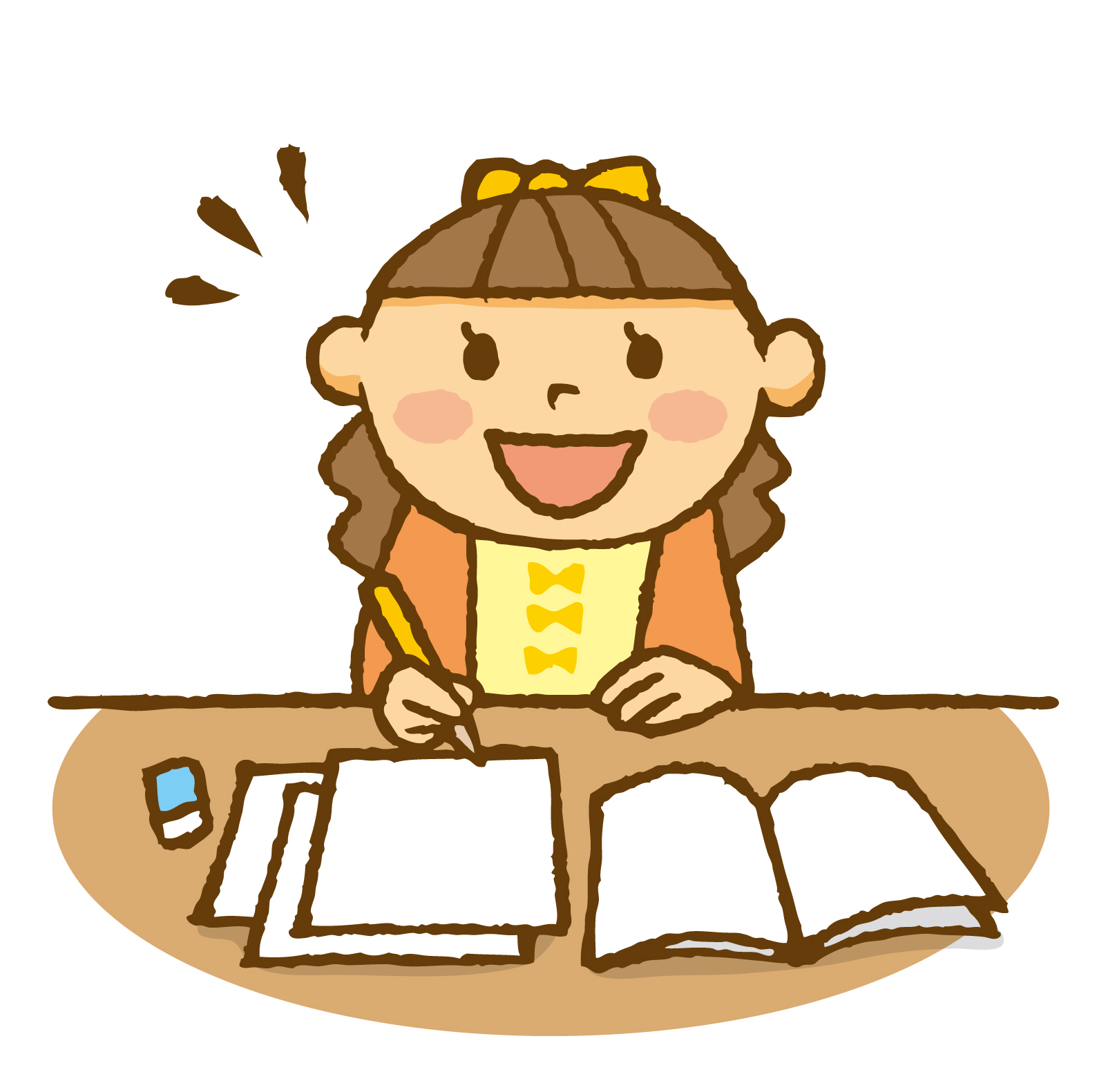
「その前というと、第一次世界大戦?」

「そうそう。」
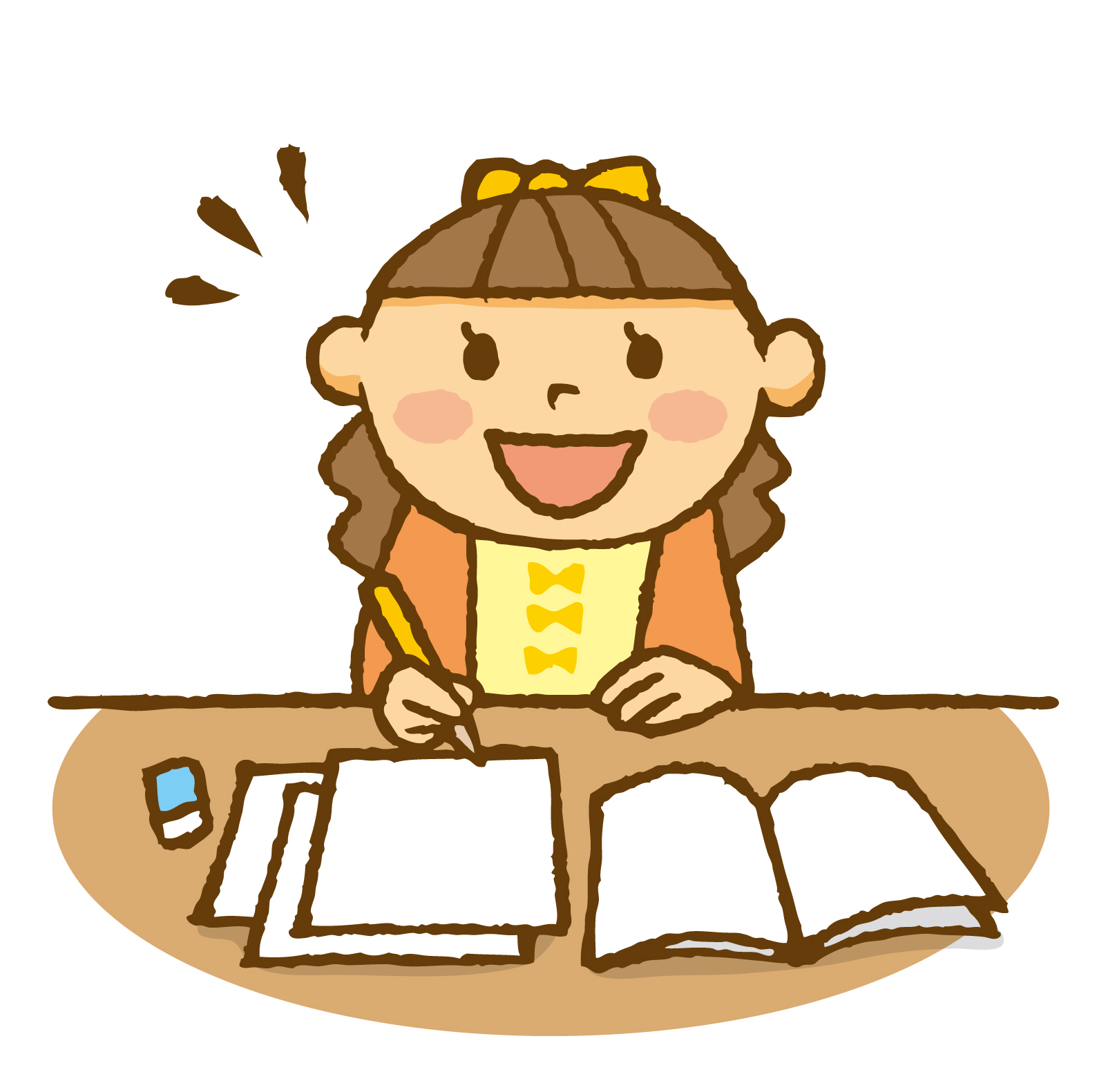
「あ、わかった。第一次世界大戦で日本はそんなに被害を受けてないけれど、物資で儲けられたんだ!だからお米を食べられるようになったんだ!」
物の価格は気持ちで動く

「じゃあ話を戻して、米が足りなくなると価格はどうなる?」
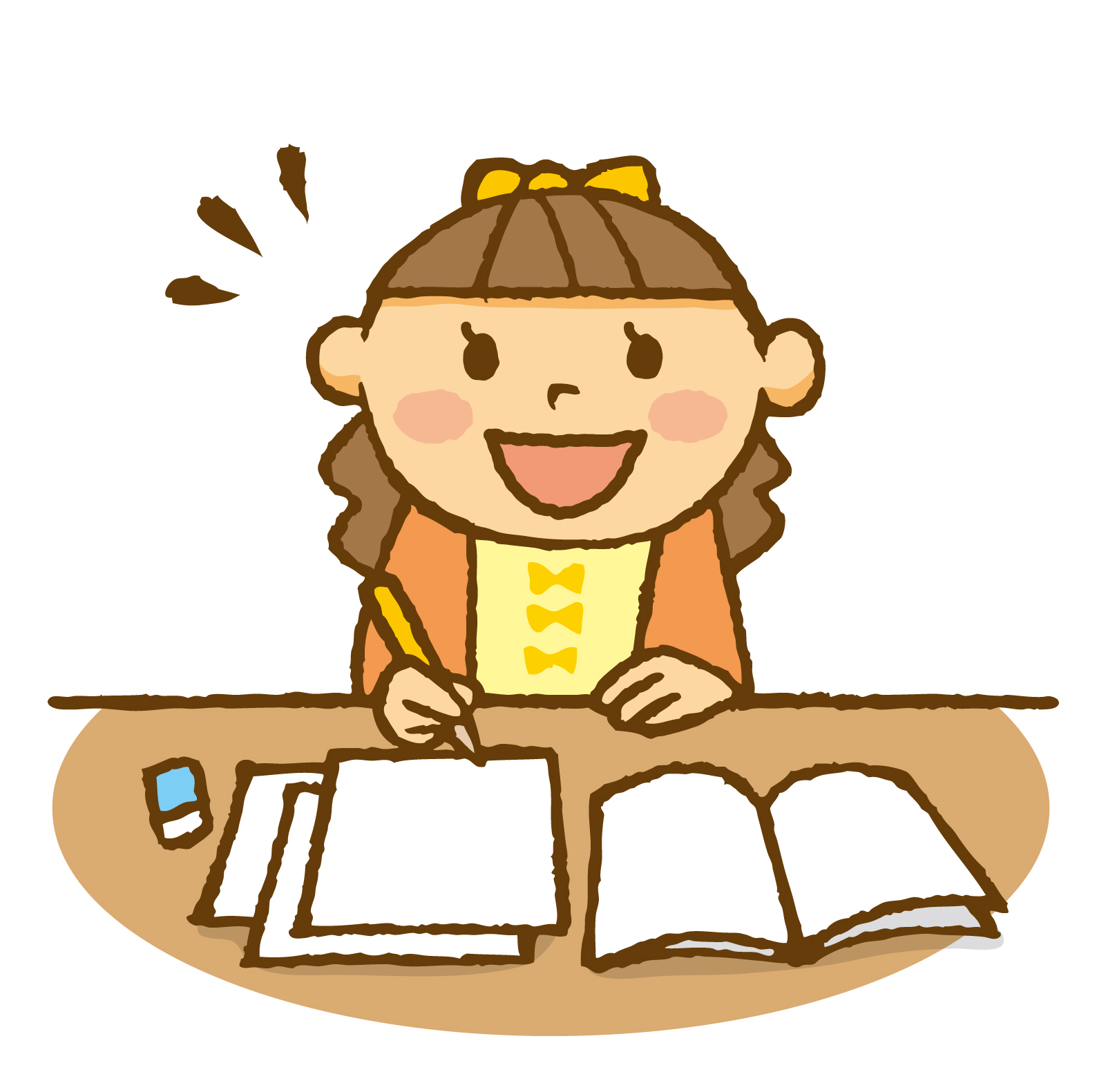
「価格が上がる!」

「そうそう。そしてこれからシベリア出兵が行われることがわかったらお米屋さんはどうする?」
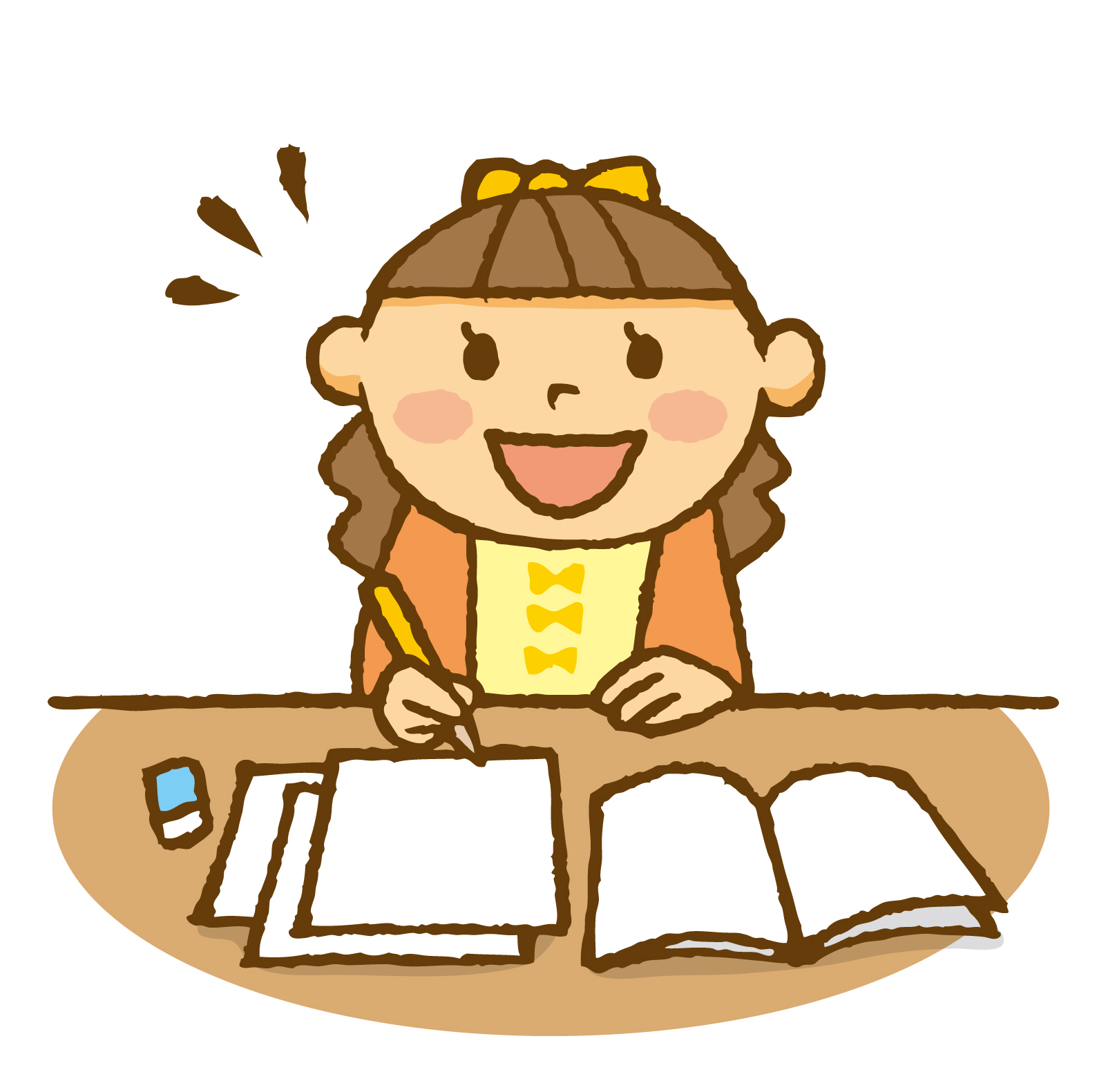
「売れるってわかってるから、値段を上げる!」

「そう。もうわかるよね?なんで米騒動が起きたの?」
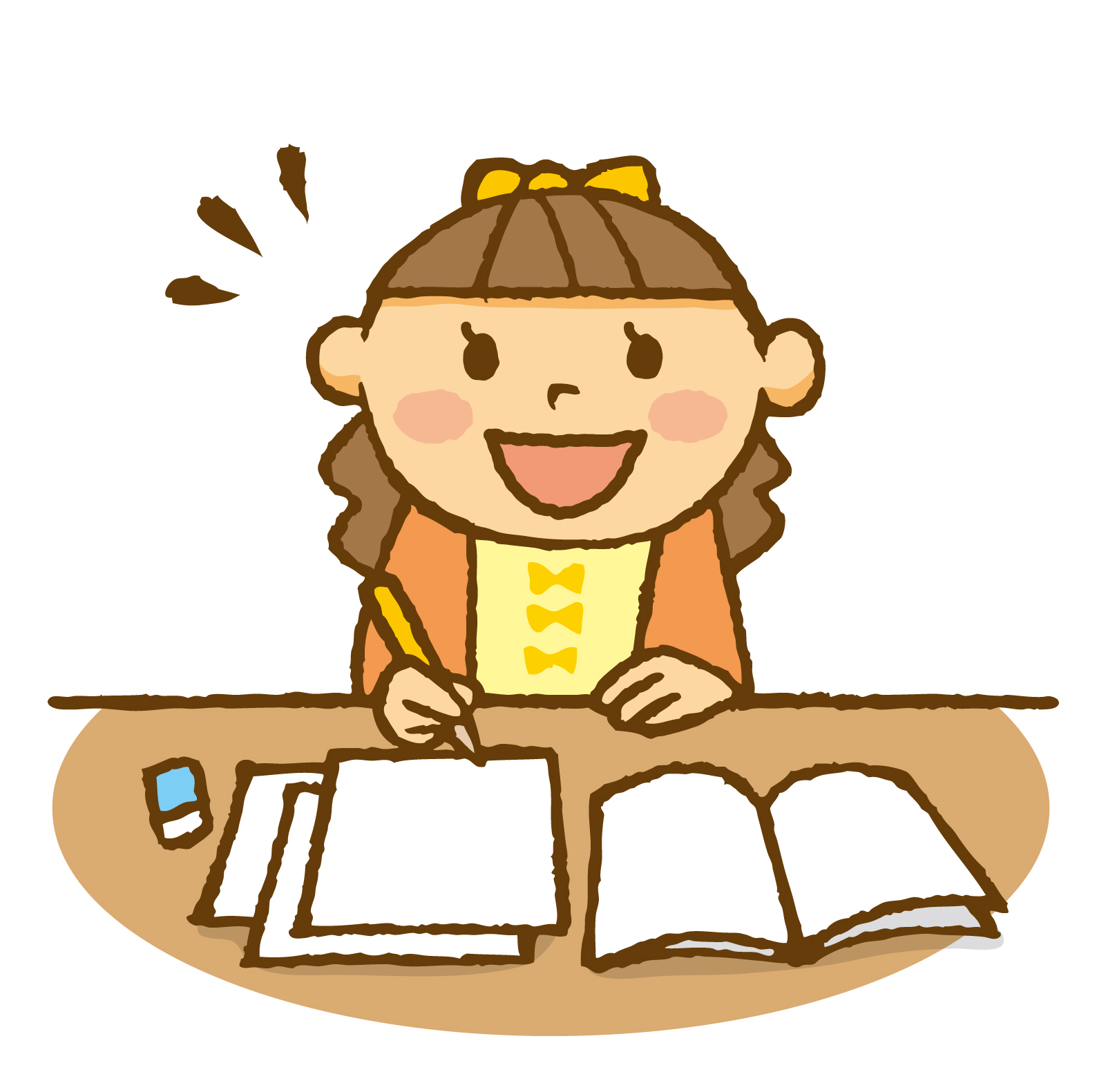
「値段が高くなりすぎて、農民がお米を買えなくなったから!」
配給は何のために行われたのか

「実は政府もシベリア出兵を決める前から米の価格が上がりすぎていることを気にはかけていたんだ。だけど止めることができなかった。そのことから第二次世界大戦時にはある制度を取り入れていたんだけど、それは何?」
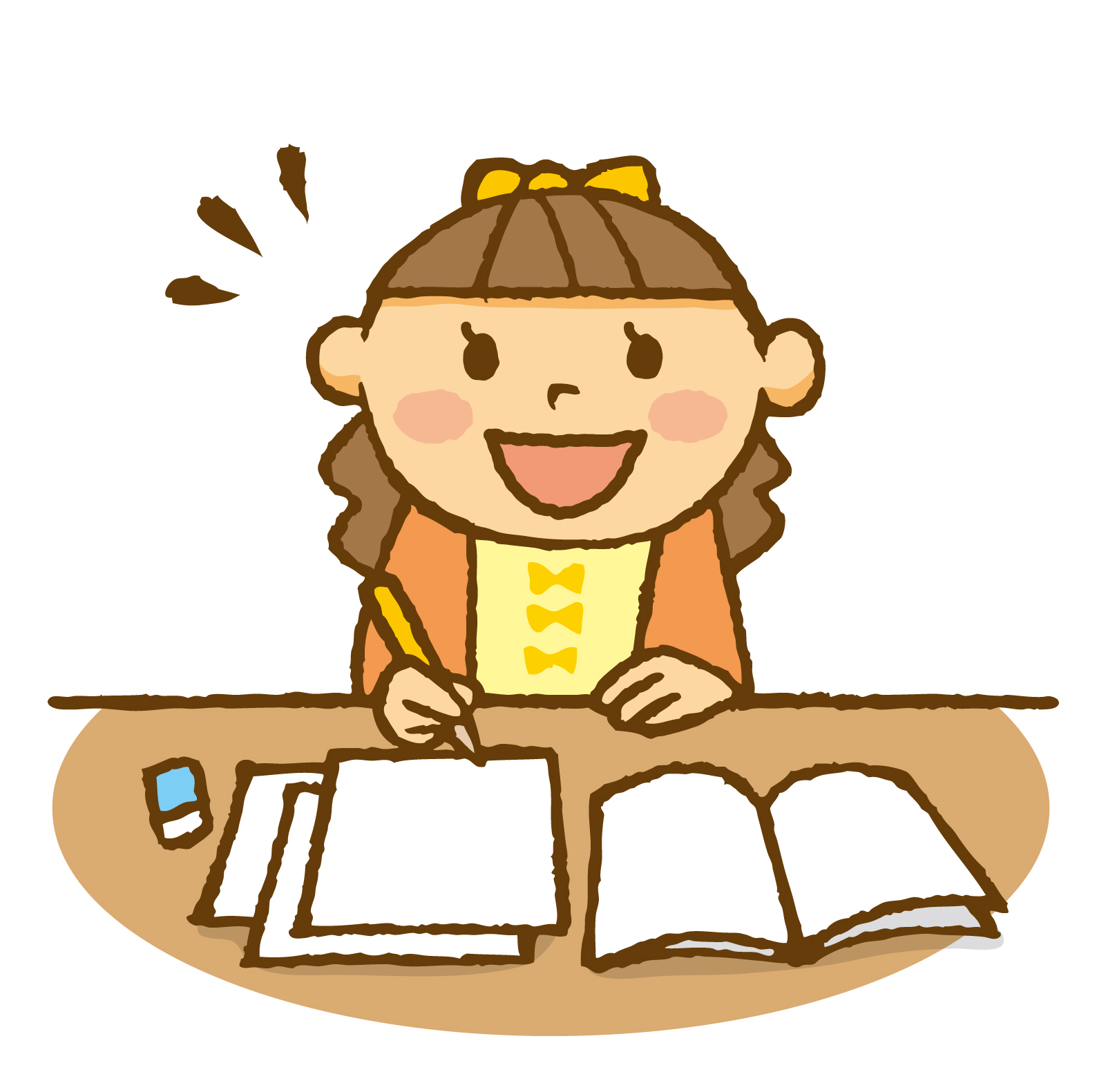
「配給!」

「そう、配給って?」
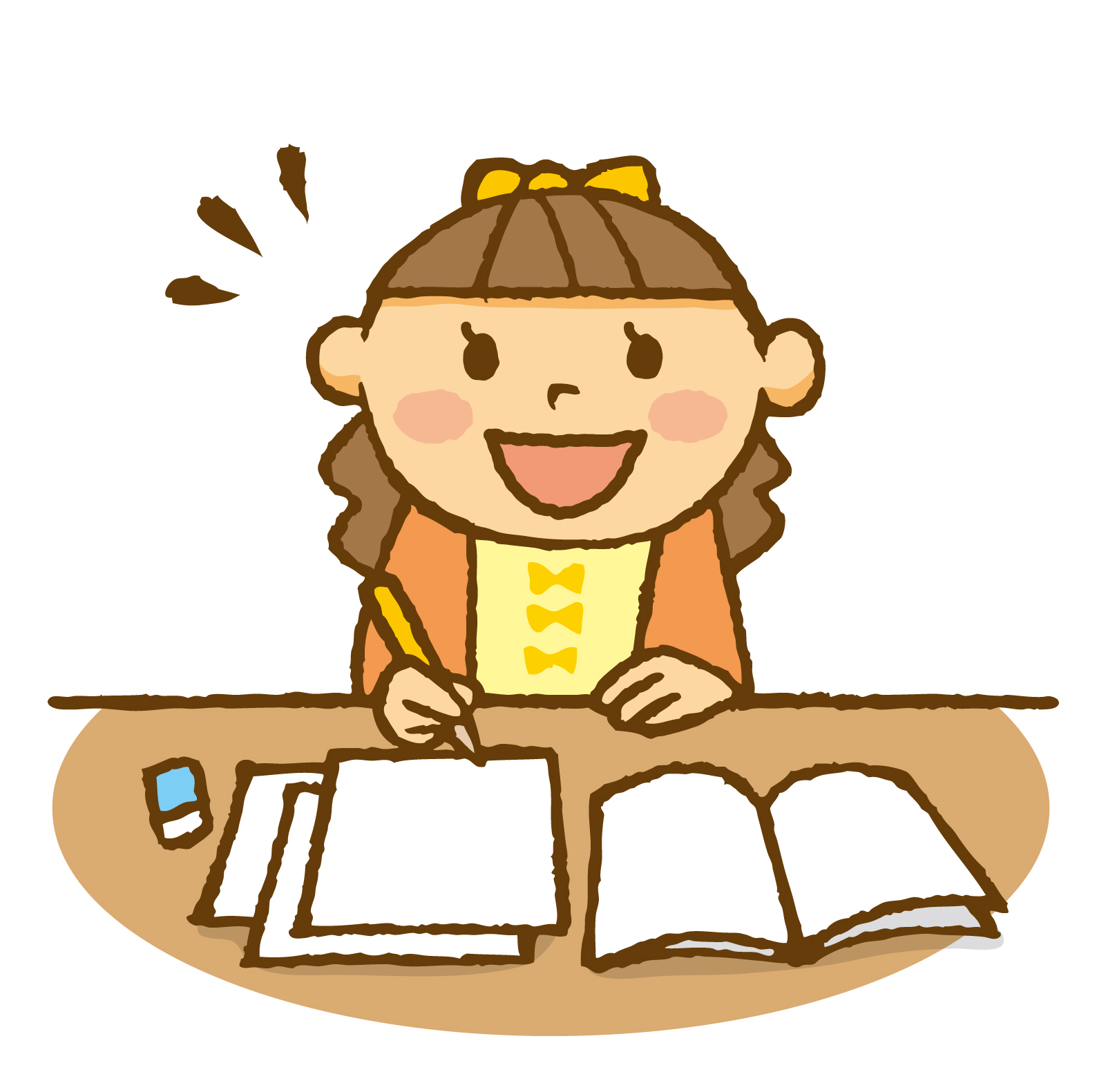
「引換券でお米と交換できるから、価格に左右されずに米騒動も起きなくなるってことです。」
子どもはお金の話が大好き!
歴史に続き、公民の単元に入ったときに、既に社会を嫌いになっている子も少なくありません。
しかし、本来子どもは歴史も公民もネタとしては好きなのです。
それゆえ、シベリア出兵から米騒動の流れは比較的簡単に理解できる子が多いので、単に暗記させるのは勿体ない。
この流れが理解できれば、そのまま公民の経済(需要と供給)の理解につながるのです。
また、あまり焦点を置かれることがありませんが、戦争において物資の供給は重要な戦略の要となります。
地味なのであまり注目されませんが、これがわかると戦争を理解しやすくなります。
先日もオンライン教室の男の子が、とあるYoutubeを見た話をしていました。
その内容は、戦争において物資の供給が戦略よりも重要だというもの。
なかなか難しい内容ですが、子どもは興味があれば難易度に関わらず取り込んでしまいます。
これがわかると、ナポレオンがどうしてロシア遠征に失敗したのか、日露戦争でなぜ日本は勝てたのか、なぜ日本は太平洋戦争で負けたのか、こういった部分が見えてきます。
日露戦争は東郷ターンが有名で、そちらに興味を惹かれる子も多いのですが、それだけでは日英同盟の意義が見えて来ません。
社会の授業は丸暗記だと思っている方が多いのですが、ファイではこのような授業をしているので、丸暗記は出てきません。
しかしこれで前後関係がわかるので、点が取れてしまいます。
例えばこんな問題。
- 米騒動
- 第一次世界大戦
- ワシントン会議(日英同盟廃止)
- ロシア革命
第一次世界大戦で特需→ロシア革命でシベリア出兵を決定→米騒動→アジアへ進出するため、日英同盟廃止(ワシントン会議)
という流れがつながるのです。
年号なんて覚えていなくても、背景がわかっていれば、このようにいくらでもつなげられるのです。
暗記で限界を迎えているなら、勉強方法を変えてみませんか?
ファイのオンライン教室は、保護者の方も子どもと一緒に受けられるので、親子一緒に楽しめますよ(^O^)





















「なんで米騒動が起きたの?」