目次
関連動画
勉強の計画性がないのは親の責任
勉強は計画的にさせたい。
計画通りに勉強してもらいたい。
そのお気持ちは十分わかります。
しかし計画性を身に着けさせるのは、塾や学校でも至難の業です。
なぜ難しいのでしょうか?
なぜなら計画性を必要とする生活をしていないからです。
例えばあなたが
「これから来る可能性が高い食糧難に備えて、昆虫食で生活する練習をしなさい。」
と言われて、今日から昆虫を捕まえて調理して生活する事ができますか?
子どもにとって計画とは、これと同じぐらい無意味な物なのです。
計画性は自然に身につくものなのか

「勉強の計画ではないにしても、日々の生活で計画は必要じゃないですか。時間割も学校行事も、計画に基づいて行われますよね?その中で生活しているのですから、計画性は放っておいてもそれなりにつくと思うのですが。」
おっしゃる通り、世の中は計画で動いており、学校行事や塾の授業も、基本的には計画で進んでいきます。
しかし、運動会や合唱コンクールなどの校内イベントはそういう力を育てる場になるとはいえ、ほとんど大人の立てたイベント計画に乗っているだけなのです。
塾に行けば宿題はみんな一律。
習い事の予定も時間が決まっているから、それに合わせて動くだけ。
しかも忘れてしまっても困らない。
実際小学生の半数ぐらいは自分の習い事の予定すら把握していないですからね。
中学生でも把握していない子は多いものです。
自分で計画を立てなくても、枠にはまって動くだけで生活できてしまうのですから、計画性を持って行動しろとか、計画を立てろとか、口でいくら言っても立てられないのです。
計画性とは何か

「ものすごく頭が良くなって欲しいとは思いませんが、せめて計画通りに勉強して欲しいと思います。計画通り勉強すれば、成績もそれなりに取れるでしょうから。」
日能研 小5 母
計画的に勉強すれば成績が上がる。
よく聞きますが、そこには大切な条件が付きます。
自分に合った勉強法を知っていることです。
いくら計画的に勉強しても、勉強法が合っていなければ、効率が上がらず、成績にも反映されません。
計画的に動けること自体は大切なスキルですが、成績をそれなりに取ることを求めるのであれば、計画通りに勉強してくれれば十分とは言えないっでしょう。
そもそも、計画的な勉強とは、どういう計画なのでしょう。
毎日コツコツとやる事ですか?
逆に毎日コツコツやっていれば「計画的に勉強しなさい」とは言いませんか?
親は欲深いもので、勉強しない子にはコツコツ勉強して欲しいと願い、コツコツ勉強している子には効率的に勉強して欲しいと願い、効率的に勉強している子にはもっと勉強して欲しいと願います。
つまり親が求めている計画性とは、いつ何をやるかという計画性ではなく、単に結果を求めているだけなのです。
言い方を変えれば、計画的かどうかはともかく、望んだ結果さえ出してくれれば満足なのです。
しかしそれが満足のいく結果にならないので、漠然と「計画的ではないから結果が出ないんだ。」と考えがちになります。
この場合、子どもに計画性を求めるよりも、まず親として、子どもの教育計画を見直すべきですね。
結果を求めるのであれば、その結果を達成できる具体的な計画を見せてあげるべきです。
先程も話した通り、子どもは計画性とは無縁の世界にいます。
口先だけで計画的にと言ってもわかる訳がありません。
そこで重要になってくるのが親の教育計画なのです。
本当に計画性をつけさせたいのか、それとも単に結果を出させたいだけなのか。
単に結果を出したいだけなら、計画性がなくても結果は出せます。
結果が出せるやり方をやりさえすればいいだけですから。
計画性が必要となるのは、生涯に渡って必要なものとして身につけさせておきたい時です。
もし身につけさせるとすると、とても大変で、とても時間がかかります。
計画性が成績向上に影響してくるのは早くても3か月。
1~6年かけてやっと結果が出るという子も少なくありません。
もし本当に計画性を身に着けさせたいと思うのなら、長期戦で挑む覚悟が必要なのです。
変わるまで待つか、変えるまで粘るか
まず、子どもに計画性を持たせるためには、その必要性を感じさせる事がポイントになります。
先程「今日から昆虫食にしなさい。」と言っても難しいという話をしましたが、昆虫食にしなければ生きていけない状況になれば話は変わってきます。
つまり、計画を立てていれば防げたことを、しっかりと認識させることが重要だという事です。
ここが一番難しいところですね。
多くの子どもは「今度は気を付ける!」で済ませてしまいます。
これを「今度は」ではなく、「二度とさせない」。
それぐらいの意気込みで指導する必要があるのです。
しかし何度言っても忘れたり、繰り返したり。
そんなすぐには変わりません。
結局ガラッと変わるのは、命の危険を感じた時ぐらいです。
計画を意識させる方法

「計画の必要性を意識させるためには、どんなことをすればいいのでしょうか。」
中学受験予定なし 小4 母
「計画を立てていれば防げた」という経験を沢山させ、実感を持たせることが大切です。
ここで重要なのは、経験させるだけではなく、実感を持たせるというところです。
ちょっとダイエットを考えてみましょう。
なぜ突然ダイエットの話なのかというと、オンライン授業の塾生に聞かれたからです(笑)
年頃の女の子は、体型を結構気にしていますからね。
そしてこのダイエットの話、根本的には勉強計画と同じなのです。
ダイエットをしたいと思っている人は多いでしょう。
その経験を思い出してみて下さい。
どんなダイエットが成功しましたか?
どんなダイエットが合うかどうかは人それぞれでしょう。
しかし、ダイエットに成功した事がある経験を持つ人には、ある共通点が多くあります。
それが体重計に頻繁に乗る人です。
体重計に乗る人は、それだけこまめに自分の体重を気にします。
こまめに気にするから食事や運動も気になります。
結果的にやせられるのです。
自分の体重を見たくないからあまり見ない人も多いでしょう。
でも本当に何とかしようと思っているなら、気になって見てしまいますよね。
要するに、ダイエットしようと手段をあれこれ考えなくても、目標を意識して体重計に乗る人は、それだけで体重を減らせていける素質があるのです。
逆に現実を見たくなくて体重計に乗らない人はなかなか成功しません。
どのダイエット法を取るかは次の問題なのです。
まずギャップを知る。
だから計画が活きて来るのです。
目標と現実とのギャップを直視する力
勉強も同じです。
ただ漠然と目標だけ掲げても、それをこまめに意識するようにしないとなかなか持続しません。
月一回程度の試験では、その試験の時にはあれこれ反省しますが、日々の勉強には生かされません。
点を取りたいなら、常に点数を意識して、常に目標とのギャップを確認する。
逆に言うと、それだけで成績はあげられるのです。
あとは方法ですね。
どうやって勉強するか、がハッキリしていなければ、いくら勉強しても成績には結びつきません。
ファイのオンライン授業では、点数も成績も求めていませんが、塾生が求めるのであれば、サポートしています。
ちなみに使っているチェックテストは、無料で公開しているオンラインテストですから、ちょっと試してみて下さい。
このレベルのことが理解できるなら、点を取りたいという気持ちと、方法が一致すれば、勝手に成績が上がります。
最も、これが嫌なら無理にやらせる必要はありません。
無理矢理体重計に乗せた所で意味がないのと同じです。
ショック療法にはなるかもしれませんが、それ以上の効果は見込めません。
どんな参考書を使うかとか、誰の授業を受けるかなんて、実はたいした問題ではないのです。
いくら言っても意味がない子
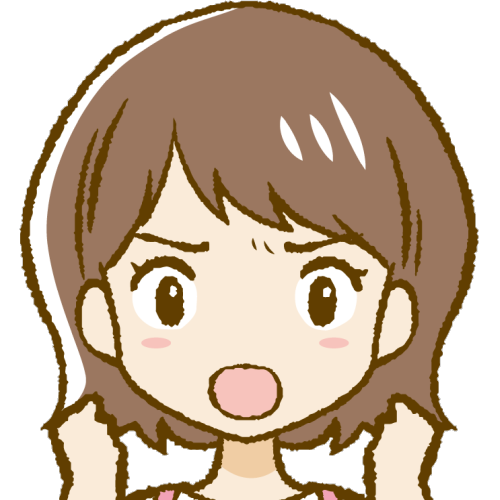
「何度も言って、既に1か月くらい経ちますが、一向に変わる気配がありません。チェックテストもやりません。もう言うこと自体に疲れてきました。いい加減気付いて欲しいのですが、無理なんですかね。」
早稲田アカデミー 中1 母
ファイのオンライン授業では、時々命の危険を感じたのかガラッと変わる子もいますが、本当に命を危険にさらしている訳ではないので、怒って効く子もいますが、効かない子はいくら言っても効きません。
そこでどうするか。
とにかく続けるしかないのです。
本人が「あ、言われた通りだったな。」と思った瞬間に初めて計画の必要性を認識するものなので、そのタイミングが来るまでひたすら言い続けて待つしかないのです。
だから長期戦なのです。
オンライン授業での指導例
ファイでは計画性を立持たせたいとき、以下のような指導しています。
- 1週間の予定を指導のたびに考えさせる。
- どの宿題をいつやるか決めさせる。
- 1日の勉強時間がどれぐらい取れるか考えさせる。
- 立てた予定を検証し、修正させる。
- 予定をチェックし、子どもと話をする。
特にこの最後の先生がチェックし、子どもと話をすることは重要です。
この話の中で計画の重要性が刷り込まれていきますから。
そして、立てた予定の検証まではやると思いますが、「できなかった」で終わりにする方が非常に多いですね。
「どうするか」まで考えさせて修正させることも重要になります。
ここまでのレベルに達していない場合でも、最低限1週間先までの予定の記入はやってもらいます。
やってみればわかりますが、子どもたちは意外と自分の1週間の予定なんて把握していません。
子どもは一週間先の予定すら把握していない。
子どもに「来週1週間の予定を書いてごらん?」といって書かせてみて下さい。
明日の予定すらわかっていない子が多いのではないでしょうか。
これが書けない、わかっていなかった子は計画性が初期レベルだと思って間違いありません。
つまり、計画性を身に着けさせようとすれば、相当時間がかかるということです。
では頑張って計画性をつけさせようと思っても、最初に話した通り、計画性がある親の場合、子どもはその指示通りに行動すればいいだけなので、計画性を必要としないのです。
計画性の必要性を気付かせる上でも親は計画性を持って行動しなければなりませんが、子どもに指示してはいけません。
指摘しなくても気付けるようにうまく誘導する必要があります。
例えば、

「車で送るの時間になったら教えてねー。」
「迎えが必要なら言っておいてねー。」
とか。
親が何時なのかを管理するのではなく、子ども自身に時間を管理させるようにしていく必要があるという事です。
計画を立てるより重要なこと
さて、計画性を持たせる方法はいかがでしょうか。
こんなにあれこれ考えながら計画性を立てさせるのは無理、と思う方も少なくありません。
実際、計画性を持たせるのは、とても大変なことなのです。
今回のテーマが計画の守らせ方なのでそこに焦点を当ててお話しましたが、実は計画を守らせるよりも重要なことがあります。
それが、計画を修正する力です。
計画を立てもやらなければ意味がありませんが、修正することを知っている子は、それをどこでどう補うかがわかっています。
そのため、計画をリカバーし、目的を達成することができます。
極端な話、計画自体はザルでも、臨機応変に必要なことができるように修正していくことができる子の方が伸びやすいのです。
そしてもう一つ重要なことがあります。
それは塾の宿題を100%こなすための計画にはしないこと、です。
塾の宿題はちゃんとやらないと成績が伸びない、と思いがちですが、実はそんなことありません。
9割捨てても、自分に必要なことをやっている子は伸びるのです。
これについては計画性の話ではないので割愛しますが、これに基づいて計画を立てると、通常の計画とは全く異なる性質の計画になります。
すなわち、どこを捨てていけば効率がいいか、をわかりやすくするための計画です。
これがうまくなると、計画性はなくても効率よく実行できるようになるため、成績が上がりやすくなります。
ファイのオンライン授業でも、これらを意識して声かけをしています。
例えば、こっちは予定をわかっていても、あえて「明日何時からだっけ?」とすっとぼけて聞く、みたいにあの手この手で自主性を持たせるための声掛けをしています。
もし計画性を身につけさせたいと本気でお考えなら、時間をかけてゆっくりと取り組んで下さいね。
ご家庭で難しいようなら、月1万円で計画の持っていき方のアドバイスをしています。
どう声かけをして、どう接すればいいのか。
実際の生活に基づいたアドバイスができるので、迷わず進められるでしょう。
-1024x576.png)





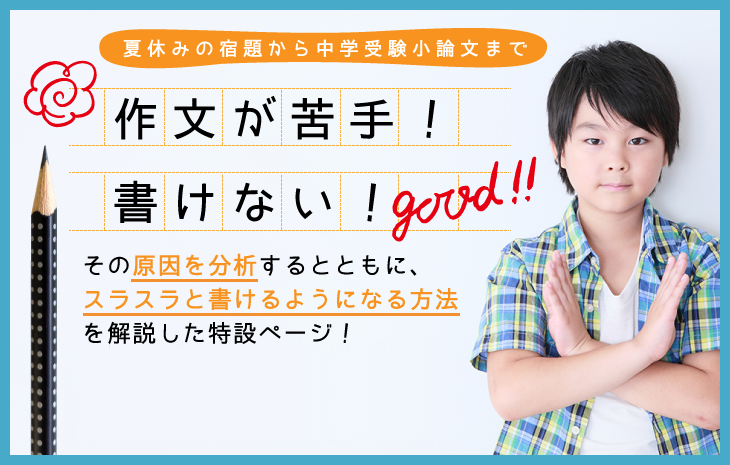
-3.png)

-1-150x93.png)
-7-150x93.png)
-9-485x300.png)
-25-485x300.png)
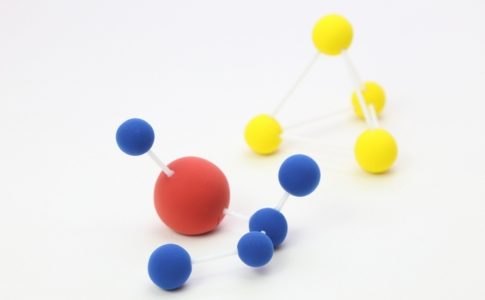

-2-485x300.png)
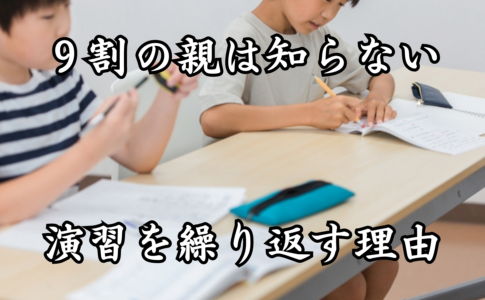







「何度計画を立てても、全く計画通り勉強できません!それどころか、最近は開き直って、計画を見ようとすらしません。何とか計画性を身に着けたいのですが、どうすればいいでしょうか。」
サピックス 小6 母