目次
衆議院選挙と参議院選挙の仕組み
解散があるかないか、で揺れてますね。
オンライン授業でも選挙は大人気の話題の1つ。
衆議院選挙のたびに話す事なのでまとめておきましょう。
選挙があると入試にも出題が一気に増えるぐらい重要な内容です。
一方中学受験でも高校受験でも、選挙を扱うのは公民の最後の方。
つまり受験直前。
しかも身近なこととはいえ、選挙権がないため全く実感がない。
それどころか、サピックスや日能研、早稲田アカデミーに通っている子は、宿題の量が膨大で、他のことに目をやる時間もない。
だから以外と弱いのです。
公民は、習う前にどれだけ政治に関する話題に触れていたか、がそのまま成績に反映される単元です。
触れる機会があったら、一旦宿題を右においてでも、すかさず話題にしていった方が、授業の吸収率は上がります。
小学生でも、親が興味を持てば結構食いつくものですよ!
なので、小学生にもわかりやすく話しているオンライン授業を元に、ポイントをお話ししましょう。
衆議院、参議院とは
衆議院と参議院は日本の立法機関である議院です。
中学受験に出る主な違いは以下の通り。
| 衆議院 | 参議院 | |
| 議員定数 | 465人 | 248人 |
| 任期 | 4年 | 6年 ※3年ごとに半数を改選 |
| 被選挙権 | 25歳以上 | 30歳以上 |
| 解散 | あり | なし |
| 優越 | あり | なし |
ここでよくわからなくなるのが、被選挙権という言葉。
「被」とは「かぶる」という意味の漢字なので、選挙を受ける権利、つまり立候補をする権利という意味です。
選挙の日
衆議院は参議院とは異なり、解散があります。
解散というのは、総理大臣が「解散する」と宣言するものです。
よって、首相が解散の宣言を出すか、任期満了となる前30日以内に行われることになります。
とはいえ、現行の日本国憲法下における選挙で衆議院が任期満了となったのは1度しかないので、任期満了前に解散となりそうな気もしますね。
なぜ解散するのか
衆議院はなるべく現時点での国民の意向を取り入れることを目的としているため、現在の議員の考え方と、現在の国民の意見にずれが生じていると考えられる場合には、解散して選挙をしなおします。
このことを「民意を問う」と言われることがあります。
ではいつ解散するのかといいますと、内閣総理大臣が解散を宣言したとき、になります。
しかしそれでは内閣総理大臣の一存で政治が運営されてしまいますので、内閣総理大臣に圧力をかける方法もあります。
それが「内閣不信任決議案」の提出です。
これはあくまで案の提出なので、賛成か反対か、議決を取ります。
その際、出席議員の過半数の賛成が得られれば、内閣不信任決議案の可決となります。
可決されると、内閣は10日以内に衆議院を解散させるか、総辞職をしなければなりません。
最も、衆議院を解散するということは、解散総選挙後には内閣総辞職となるため、いずれにしても総辞職になります。
しかし現在の内閣は自民党と公明党の連立政権で、合わせれば過半数の議員となっているため、身内に裏切者がいない限り、可決されることはありません。
もし否決されれば、今の内閣はそのまま存続するため、総理大臣の解散宣言にゆだねられる形になります。
なお、民意を問うとは言いますが、実情は現政権に不利な話題が出ていない、有利なタイミングで解散して、政権維持を狙うのが一般的です。
スキャンダルとか、不利な話題が出ている時に解散すると、敵の政党に票が流れてしまいますからね。
衆議院選の投票方法
衆議院の定数は465人で、その内289人が小選挙区制で選出し、176人が比例代表制で選出します。
この小選挙区制と比例代表制がまたややこしい・・・
自分が住んでいる地域の選挙で話をしなければ、あまりイメージが湧かないのです。
そのため、オンライン授業では塾生の住んでいる場所をピックアップしてお話はしていますが、それぞれ各自住んでいる地域で調べてもらうようにしています。
すごく難しく感じるかもしれませんが、親として話して欲しいのは興味を持たせることであり、テストに出る内容を教えることではありません。
とりあえず全く知らないことには話せないので、小選挙区制と比例代表制について簡単にまとめておきます。
もちろんこれはオンライン授業で話していることと同じ内容です。
なお、サピックスαクラスの子の中でも、開成に受かる子は、大人と同レベルで選挙の話をできる子が多いですね。
しかしサピックスのテキストだけではそんなところまで学べませんから、やはり日常からそういう話題が多いということになります。
やはり机に縛り付けてなんとかしがみついていられるαクラスではなく、知識も精神も余裕を持った形で学びたいところですね。
小選挙区制
日本全体にまんべんなく人が散らばっていればいいのですが、現実的には人口が集中しているところと、少ない所とがあり、まばらです。
そのため、人口が同じくらいになるように全国を区分けして、その地区ごとに選出する方法を小選挙区制といいます。
どう区分けするかは10年ごとに人口を見直して決めています。
例えば、主要都市の人数は以下のようになります。
- 東京:25人
- 千葉:13人
- 埼玉:15人
- 神奈川:18人
- 大阪:19人
- 兵庫:12人
- 京都:6人
そしてこの人数で、さらに細かく選挙区をわけていきます。
例えば、東京の場合は東京全体で25人なので、東京の中で人数が同じくらいになるように25個に区切り、それぞれの地域で1人ずつ選出します。
千葉県なら13人なので、13区に、埼玉県なら15人なので15区に分けて、それぞれ1名ずつ選出していきます。
衆議院議員465人の内、小選挙区では289人を選ぶということですね。
そのため、選挙では立候補している「人」に対して投票していくことになります。
これを割とわかっていない子が多い(^^;
なので、オンライン授業では、実際に投票に連れて行くことを強く勧めています。
小学生くらいなら一緒に連れて入っても何も言われませんので。
比例代表制・ドント式
人ではなく、「政党」に対して投票し、ドント式という計算方法で議席数を配分します。
このドント式というのが入試でも定期テストでもよく狙われますね。
最近は、ドント式と答えさせるのではなく、手順が説明してあり、それを元に実際にやってみよう、というタイプの入試問題が増えてきました。
知識ではなく、考える力を試す出題方法に変わってきたということですね。
簡単に説明すると、以下のようになります。
それぞれの党が獲得した投票数を÷1,÷2,÷3,÷4,÷5…とした数を書き並べ,数字が大きい順に定数分だけ議席を党に割り振る方式です。
例えば議員定数を6人として考えた場合,以下のようになります。
| A党 | B党 | C党 | D党 | |
| 得票数 | 150 | 90 | 50 | 40 |
| ÷1 | 150 | 90 | 50 | 40 |
| ÷2 | 75 | 45 | 25 | 20 |
| ÷3 | 50 | 30 | 16.6 | 13.3 |
| 獲得議席数 | 3人 | 2人 | 1人 | 0人 |
このようにして全国の政党に対する投票を集計し、政党ごとに何人当選させるかを決めていきます。
これはオンライン授業も時間があればやるようにしています。
これもサピックスや日能研の難関クラスの子の食いつきはいいですね。
興味を持てない場合は、興味を持てるところへ持っていくところから始めていきましょう。
さて、当選人数が決まると実際に誰が当選するのか。
これは衆議院選の場合、政党が予め提出しておいた候補者名簿に記載された順番通りに当選していくことになります。
これを拘束名簿方式といいます。
ここまでは入試で問われませんが、オンライン授業では、突っ込んで聞いてくることが多いため、簡単に解説しています。
衆議院選挙で採用されている拘束名簿方式というのは、名前を書いた順番通りに当選していくことになります。
それに対して参議院選挙で採用されている非拘束名簿方式は、個人にも投票できるため、個人に対する投票数で順位を決めて当選していくことになります。
なお、政党としては絶対に当選して欲しい人を当選させるために、拘束名簿方式のように予め順位を決めて優先的に当選者を決めることもできます。
この枠のことを「特定枠」と言います。
小選挙区制、比例代表制のメリット・デメリット
選挙制度が違うということは、それぞれメリット、デメリットがあるということです。
ただ丸暗記するのではなく、これをしっかり押さえておきたいところ。
⇒ 開成中でもこの部分を問う問題が出題されました。
小選挙区制のメリット・デメリット
小選挙区制は全国各地、それぞれの地域から確実に1人ずつ選ばれることになります。
つまり、日本全体としてみたら話題にもならないようなローカルな問題でも、その地域から当選した議員が取り上げて問題にしてくれる可能性があるのです。
また、人口が集中しているところからの議員ばかりではなく、日本全国にまんべんなく議員がいることで、一部地域に偏った政策を防ぐことができるようになります。
逆に全国を区分けするということは、どうしても議員の数が多くなってしまうということでもあり、人数を同じくらいにして区分けするということは、人口が少ない地域は広い範囲で1人しか出せないことになります。
こういう部分はサピックスのαクラスの子でもなかなか答えが出ません。
一方オンライン授業に昔からいる子は強いですね。
知識も大切ですが、知識だけではカバーしきれない思考力もあるということです。

開成中で出題されたのは、まさにこの部分についてでした。
イギリスの下院は小選挙区制のため、全国各地から選出することになります。
そのため、スコットランドという地域では、スコットランド国民党が圧倒的な支持を得て、議席数を大幅に伸ばすことに成功しました。
もしこれがイギリス全体での投票となれば、スコットランド国民党を支持する人は少ないでしょう。
これは小選挙区制度、かつスコットランドという地域で圧倒的な支持を集められたことが要因です。
比例代表制のメリット・デメリット
政党というのは、同じ政策、同じ考えを持った集団です。
そのため、自分と同じ考えの政党が議席数を確保してくれれば、政治にその意見が反映されやすいことになります。
ところが、小選挙区制だけでは小さな政党は全国各地に立候補者を擁立することが難しく、小選挙区で勝った人しか当選できないとなると、大政党には太刀打ちできません。
そこで「政党への投票」という制度を取ることで、人数が少なくても政策や考えに賛同してくれる人の票を集められるようにしたのです。
これにより、例えば5人しかいないような小さな政党であっても、全国から政党に対する支持が集まれば当選できるようになります。
デメリットとしては、小さな政党が乱立すると、政治が不安定になりやすいこと。
最も小さな党は影響力も少ないので、なかなかそういうデメリットを感じるようなことにはなりませんが(^^;
参議院選挙との違い
任期は6年で、3年毎に半数を改選
参議院の任期は6年で解散はありません。
つまり、一度当選すれば、余程の事情がない限り、6年間は続けるということです。
これは、参議院が長期的視点でぶれない運営を目的としているからです。
1年毎に解散してコロコロ変わってしまっていては、安定した政治にはなりません。
だから、世論を反映は衆議院に任せ、長期的に安定した政治にすることを考えるのは参議院というように役割を分けているのです。
しかし一気に全員変えるのではなく、3年ずらして、半数改選という形をとっています。
- 2019年の選挙で当選⇒任期は6年後の2025年まで
- 2022年の選挙で当選⇒任期は6年後の2028年まで
- 2025年の選挙で当選⇒任期は6年後の2031年まで
任期は6年だが、半数改選なので、3年毎に参議院選がある。
3年ずらす理由
6年毎に全員総入れ替えをしてしまうと、6年毎にがらりと変わってしまうため、それも安定とは言えません。
そこで、3年毎に半分ずつ入れ替えることで、一気に変わらないようにしているのです。
そしてもう一つの大きな理由が、選挙です。
選挙は公示してから実際に選挙が行われ、当選してから引き継ぎをするまでに1か月以上の時間を要します。
もし万が一衆議院選挙と参議院選挙が同時に行われることになったらどうなるでしょうか。
1か月近く国会議員が不在の状態となります。
さらにこんな時に国家規模の有事が起きたらどうするのでしょうか。
そんな事態に備えて、国会議員が全くいない状態を避ける目的も兼ねて、3年毎に半数改選としているのです。
具体的には、参議院の定数は248人なので、次の2022年の参議院選挙ではその半数である124人が改選となります。
半数改選の目的
・ガラッと変えずに長期的視点で運用するため。
・国会議員不在の空白期間を作らないため。
与党と野党
オンライン授業で選挙の話の時に、よく質問されるのが与党と野党についてです。
ニュースでよく耳にするものの、イメージがつきにくいんですね。
なのでできれば実際の与党議員、野党議員を例に話をして頂きたいところです。
まず与党について。
与党は実際に政権を担う党と言われますが、これが子どもにはよくわかりません。
まず大前提として、国会は多数決で法律を決めるところということを押さえておく必要があります。
つまり、多数決で勝てるだけの人数が集まれば、法律を制定できるのです。
その多数決で勝てるだけの人数が集まった党を与党、集まらなかった党を野党といいます。
なので、仮に自民党が全議員の半数以上を占めれば、自民党の掲げた政策や法案は多数決で通しやすいため、与党と言われます。
しかし、実際には現状半数はいません。
そこで、自民党は公明党と手を組むことで、過半数の票を獲得することにしているのです。
この状態なら、自民党と公明党の両方が与党となり、それ以外が野党となります。
このように手を組んで与党になる政権を連立政権といいます。
野党の存在意義
多数決では勝てないとわかりきっている野党ですが、だからといって不要なわけではありません。
与党が政権を取ったからといっても、与党の全員が賛成するとは限らないのです。
あくまでその地方の1議員として選ばれているため、たとえ党員だったとしても、やっぱり駄目だなと思えば反対票を投じることもあるのです。
そのため、野党は与党の考える法案に対して、本当にそれでいいのか、どんな問題が起きるかといったことを考え、追及し、与党の好き勝手にさせないように、揺さぶりをかけ、よりよい法案になるようにしていく役割があります。
最も党内の圧力や上下関係が厳しいと個人の意見は殺されてしまうため、結局与党が強引に法案を通してしまうことができるのですが…
ただ最近はこの風潮も変わってきているようですね。
今の若手議員は上下関係にあまり捕らわれず、自分の意見で投票してしまうようになってきたようです。
最高裁判所裁判官の国民審査
衆議院選挙では、同時に最高裁判所裁判官の国民審査が行われます。
これは司法機関の最高権力である最高裁判所の裁判官を、適任かどうか審査するもので、不適任だと思われる人物の名前の上に×を書いて投票します。
しかし、この制度ができてから現在まで、一度も罷免されたことがなく、裁判に対する関心の低さと、裁判官がそれぞれどんな裁判にどんな判決をしたのかわかりにくいところが原因と考えられています。
なお、同時にやる理由は、国民が裁判官を罷免させる機会を作ることと、費用を抑えるためです。
参議院選挙のしくみ
参議院選挙も衆議院選挙と同様に、選挙区制と比例代表制で行います。
ただし、その選挙方法には細かい違いがあります。
選挙区制
まず選挙区は衆議院選挙の時の小選挙区とは異なり、より大きな区分けで選びます。
人数も地域ごとに1人とは決まっておらず、その地域の人口により当選者数が異なります。
そのため、鳥取・島根からは合わせて1人、徳島・高知からも合わせて1人ですが、東京からは6人選出されます。
このように、2県またいで選挙区をくっつけることを合区と言います。
この選挙制度を、通常そのまま選挙区制度と言っていますが、衆議院選挙の小選挙区と区別するために、大選挙区と言うこともあります。
比例代表制
参議院選挙の比例代表制の選挙の仕方も、ほとんど衆議院と同じような感じで、ドント式も同じです。
しかし厳密にいうと異なります。
まず党名での投票だけではなく、個人名で党へ投票が可能です。
つまり、「〇〇党の中でも〇〇さんがいい!」といった投票が可能なのです。
衆議院選挙の場合は、党に投票し、その党から誰を当選させるかは、党が予め決めておいた名簿順に決まりますが、参議院選挙の場合は、個人名での投票も兼ねているため、その党の中で人気があった順に当選していくことになります。
これを非拘束名簿式と言います。
こうなると全国的に名前が知れ渡っている人の方が有利なため、スポーツ選手やタレントといった知名度がある人を選挙に出す傾向が強くなるのです。
なお、参議院選では選挙区選挙と比例代表選挙のどちらにも出馬する重複選挙はありません。
どちらの形式で出馬するかを選ぶ形になります。
よって選挙区選挙で落選したのに比例代表で当選するといった復活当選はありません。
特定枠制度
非拘束名簿式の比例代表制で選ぶと知名度順になってしまうため、党が当選させたい人を当選させられない可能性が出てきてしまいます。
そこで特定枠という制度が作られました。
これは通常個人の獲得した票数で順番通りに当選となりますが、それぞれの党が予め提出した名簿の順番通りに当選が決まる制度です。
つまり、拘束名簿方式を部分的に取り込んだ形ですね。
一応これは、合区となった鳥取・島根から1人では全ての都道府県から議員が選出されなくなってしまうため、予め党の方で名簿の上位に入れておくことで、合区から2名以上を確実に当選させることができるようにという配慮から作られたもの、と説明されています。
しかし実際には鳥取と島根にいる自民党員から1人しか出せないとなると、どちらにするか選べないため、どちらからも当選させることができるようにして、自民党員を少しでも増やせるようにしたシステムだとも言われています。
結局勝者(過半数の議席を獲得した政党)が自分たちの都合のいい法改正で選挙制度を作ることができるため、あえて自民党が不利になる選挙制度は作ることはないでしょう。
オンライン授業でよく出る疑問
オンライン授業で塾生たちが疑問に思うことも参考として載せておきます。
このような質問をしてくるのはサピックスのαクラスの子かと思いきや、全然そんなことはありません。
全く成績的には高くない子でも疑問に思っているようです。
なので親が学力で決めつけて教える内容を制限しないようにしたいところですね。
内閣総理大臣は選挙に出るのか
内閣総理大臣は国会議員から選出することになります。
そのため、選挙を経て国会議員になり、そこから内閣総理大臣に選ばれることになります。
ちなみに衆議院議員からばかり選ばれていますが、参議院から選んではいけないという法律はありません。
つまり、現在まで参議院議員からの内閣総理大臣が0人なのは法律による縛りが原因ではありません。
基本的に党首は民意を反映しやすい衆議院議員から選ぶことが多いため、必然的に衆議院議員が内閣総理大臣になっていると考えられます。
総理大臣は落選するのか
総理大臣でも落選することはあります。
しかし一般的には総理大臣になるためにはまず衆議院議員か参議院議員になり、さらに与党の党内選挙で党首とならなければ総理大臣になれないため、選挙で国民から選ばれないような人が総理大臣になることはまずありません。
落選するとすれば、在任期間中に国民の怒りを買うような政策をした人ということになるでしょう。
しかし、その場合解散してから選挙という流れになるため、その時点では元総理大臣ということになります。
つまり、厳密にいえば、総理大臣として選挙に出ることはないため、総理大臣が落選することはないとも言えます。
なので、直前まで総理大臣だった元総理大臣でも落選することはある、という言い方が正しいでしょう。
投票率
2019年の参議院選挙は48.80%の投票率となり、投票率の低さが話題となりました。
50%を下回ったのは24年ぶりとのことです。
投票率が低いと、一部の人間の意見でのみ選ばれた代表ということになります。
そして若者が投票しないと、政治家は票を稼ぐために高齢者が投票してくれそうな政策を打ち出します。
そうなると票になりにくい若者のための政策が行われなくなってしまうのです。
政治家は票のために活動していますからね。
投票率が低いのは何が問題なのかというのは入試でも問われるため、ちょっと話題にして考えさせてあげるといいでしょう。
なお、たとえ白紙でも投票すれば、その年齢の投票としてカウントされます。
つまり、若者としての投票は「誰も信頼して任せられないよ!」というメッセージの発信になるのです。
なので、たとえ白紙でも、投票には行く子にしたいところですね。
選挙の仕組みは複雑で小学生にはわかりにくいとは思いますが、そのわかりにくさが今の大人たちのよくわからないから投票へ行かないという現状を作り、参加しないから子ども達もよくわからないという悪循環に陥っています。
世界中どこを見ても日本ほど政治に関心がない国はないとも言われ、政治家がいなくても国が回る自動運転の国などとも言われています。
そして中学受験では、みなが苦手としているからこそ狙われます。
政治を理解できる一部の人間だけが政治に参加し、自分たちの都合のいい仕組みを作り上げていきます。
その政治を理解できる側にするか、できない側のままにして搾取される側にしてしまうかは、ある意味親として政治にどれだけ関心があり、どれだけ話してあげられるかにかかっているのです。
ちなみに塾のテキストに沿った政治の授業は体系化されていて教えやすいのですが、子どもの興味があるのはもっと別なところにあるものです。
大人が教える都合上作り上げたテキストが必ずしもいいわけではないということです。
オンライン授業の社会は、学校やサピックスの授業よりも断然楽しいと言う子が多いのは、テキストを全く使っていないからです。
カリキュラムも科目も無視して、塾生が興味のあるところへ進んでいく。
だから楽しいんですね。
こうして政治に興味を持つと、あとは勝手にニュースから話題を拾ってきては授業のネタにしてくるため、放っておいても社会の点数は取れるようになっていきます。
これがろくに授業をしていなくても点数が取れるようになるカラクリです。
開成中 社会の出題内容 2021年
選挙の仕組みを、用語も含めて深く知っていなければ答えられないため、一般的には小6で公民を勉強した子でないと答えられないでしょう。
しかし、原理自体はそこまで難しくないため、選挙のときに子どもと話してある程度知っている子なら、小6前でも答えられるでしょう。
社会-02-09-01-1024x1004.jpg)
特定の地域で多数の支持を得られている
開成中 社会の出題内容 2020年
社会_大問1-問6-1024x785.png)
ク
子どもと話すときのポイント
選挙に関心がない理由として、根が深い大きな問題が一つあります。
それが、日本の教育制度です。
学校の先生は特定の党や立候補者をひいきして話してはいけません。
それゆえ、その部分を回避して話そうとすると、漠然とした話をせざるをえなくなるのです。
そして塾もトラブル防止の観点から、特定の党や立候補者に入れ込んだ話をすることを禁止してる場合が多いのです。
つまり、選挙について、子どもは本音を聞く機会はもちろん、身近に感じられる仕組みを学ぶ機会すら奪われているのです。
ではその部分を補えるのはどこか。
それが唯一家庭だけなのです。
今回の開成中の入試では、イギリスの選挙だけではなく、アメリカの選挙制度も題材として出題されました。
このように聞くとイギリスやアメリカの選挙制度も勉強しておかなければいけないのかという気がすると思いますが、実はそうではありません。
確かにイギリスの選挙について予備知識があるに越したことはありません。
しかし、問題の本質はあくまで小選挙区制であり、イギリスの下院の選挙も日本と同じ小選挙区制だったので、題材にされただけです。
つまり、日本の選挙をしっかり理解できていれば、イギリスの選挙制度であっても解けるようにできているのです。
ちなみに先程の開成の問題は、ファイに小6秋に転塾してきたサピックスや日能研の子は答えられていませんでしたが、オンライン授業の受験未定の小5が正解していました。
結局、習っているかどうかよりも、普段からどんな話をしているかの方が大切だということです。
そして、これは親にしかできない教育なため、やっている親とやっていない親には大きな差が生まれるのです。
なお、今回の試験で題材にされたのは、時事問題との関係もあったためです。
つまり何もないところに降ってわいた問題ではなく、時事問題として話題になっていたから入試でも題材にされたのです。
ファイがオンライン授業で扱っている時事問題は、入試問題を予想しているものではなく、あくまで本質的な学習を目指すための一環ではあります。
しかしそれらの中から出題されることも多く、

「ファイのブログに書いてあることが出たよ!」
という嬉しいメッセージを多数頂いております。
ぜひご活用下さい。
もし時事問題をうまく話せない場合はファイへご連絡下さい。
月1万円でアドバイスをしています。
時事問題に興味を持つと、机上の勉強程度はカバーできてしまうくらいの知識が手に入りますよ。
-1024x576.png)





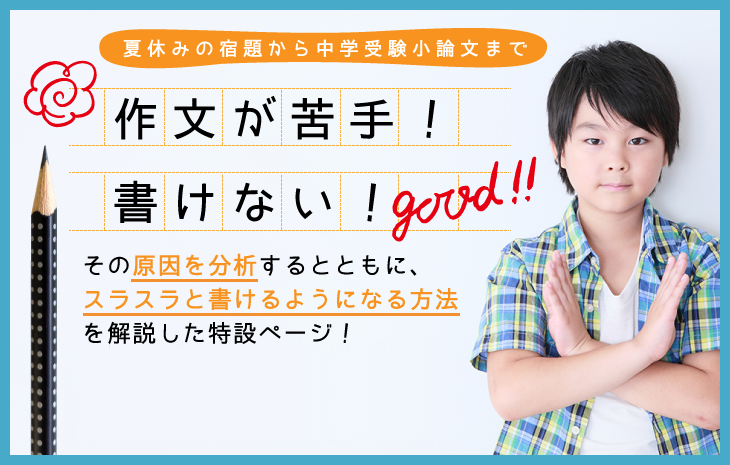
-3.png)


-13-150x93.png)

-33-485x300.png)

-36-485x300.png)







開成中でもオンライン授業と同じ内容が出題されました!
イギリスの下院の選挙が題材として出されており、その中で小選挙区制についての問題が出題されました。
この問題は、ファイの時事問題とこの選挙に関する記事で全く同じものを取り上げていました。
ファイが扱っているオンラインテストは無料で公開しています。
この中に選挙制度に関するチェックテストも用意しています。
ぜひ合わせてご利用下さい。