目次
中学受験に出る春分と秋分
ファイのオンライン授業では、身近なイベントを基に学んでいくことを推奨しているので、日々こういう質問が塾生からも出てきます。
今回は春分の日・秋分の日がテーマです。
春分(しゅんぶん)と秋分(しゅうぶん)は、受験勉強を通過してきた人なら、理科で必ず聞いたことがあるはずです。
天体の単元で重要な位置づけのため、春分と秋分がわからないと天体の半分が理解できないと言っても過言ではありません。
とはいえ、それほど専門的な内容を理解している必要はなく、ごく基本的なことさえ押さえてあれば大丈夫です。
できれば暗記ではなく、経験的に知っておいて欲しいネタなので、イベントを機に意識させておくといいでしょう。
春分、秋分の日は何が特別なのか、を理解しておくと、中学受験に有利になります。
春分の日・秋分の日
春分、秋分ともに二十四節気の1つです。
春分は毎年3月20日~21日に設定される祝日で、秋分は9月22日~23日に設定される祝日です。
3月と9月というのが重要です。
結構入試問題にも3月と答えさせる問題は出題されています。
そしてこの日は昼と夜の長さが同じになる日でもあります。
この昼と夜の長さが同じというのが、天体の単元でよく出てくる重要事項です。
そして、この日は太陽が真東から昇って、真西に沈む日でもあります。
これも同じく重要事項です。
透明半球で太陽の動き(黄道)の図を書く時に、一番最初に書く線です。
春分:3月
秋分:9月
どちらも太陽が真東から昇り、真西に沈む日
春の始めが3月になった理由

「なぜ春は3月からなの?1月にすればキリがよかったんじゃない?」
これも毎年質問する子がいる子どもの定番の疑問です。
春分はその名の通り、これから温かくなる春の訪れを感じられる季節です。
農耕民族が芽吹きを生命の誕生、つまり始まりとして認識していたなら、春が1月から始まるのが自然です。
実はその通り、春は1月からスタートしていました。
ところが、とある事情から、春を3月にずらしてしまったのです。
その疑問を解くためには、暦の始まりからお話しなければなりません。
その昔、暦が誕生した最初の頃、1年の日数は約300日でした。
この時の暦を「ロムルス歴」といいます。
足りない約60日は、農耕ができない冬だったので、カレンダーも作られず、空白にされていました。
しかし空白では翌年の1月をいつ開始すればいいかわからないため、空白の約60日を「11月」「12月」としました。
この時に11月の名前として用いられたのが、Januariusです。
これは他の月の名称と同じく神の名前から取っていたのですが、Januariusの語源となった神はJanus(ヤヌス)というローマの門神の名からつけられたものでした。
ところがヤヌスは始まりの神でもあったため、「始まりの神なのに、11月って変じゃない?」と考えられるようになりました。
こうして11月を1月にしちゃえ!ということで、月をずらしたところ、元々1月だったMartiusが玉突きで3月へとずれ、春の開始が3月からとなってしまったのです。
昼と夜の長さが一緒になる日
地球は地軸を公転面に対して66.6°、公転面に立てた垂線に対して23.4°傾いて公転しています。
そのため、夏は太陽の方に傾き、北半球は日の光を浴びやすくなるため、夏になります。
一番太陽が高く昇る日を夏至(げし)といい、この時太陽は北回帰線の真上を通っており、昼の長さは一年で一番長くなります。
太陽が北側に来るから暑くなるということです。
しかし逆に冬になるときは、太陽は南半球の上に来ます。
そして一番低くなる日のことを冬至(とうじ)といい、この時太陽は南回帰線の真上を通ります。
このとき昼の長さは一番短くなります。
北回帰線は北緯23.4度、南回帰線は南緯23.4度のところにあるため、夏至と冬至の間にあたる春分と秋分は、緯度0度の場所、つまり赤道の真上を通るのです。
そして昼と夜の長さは同じになる、ということです。
春分、秋分は昼と夜の長さが同じになる日
日時計の影が一直線上を移動する日
中学受験では影の動きもよくでます。
「水」の漢字のような形になると覚えている子も多いでしょう。
当然これは日本での影の話なので、赤道や北極に行けば影の動きも変わってきます。
それを考えてもらうことで本当の理解度を確かめることもできます。
また、なぜ夏至の日は東西の線をまたいで移動するのか、を説明できるかどうかも理解度の確認に役立ちます。
夏至の日は太陽がどこから昇り、どこを通り、どこへ沈むのか、がわかれば簡単ですね。
日本では夏至の日、太陽は真東より北側から登り、真南を通り、真西よりも北側に沈みます。
影は反対の方角にできるので、朝は真西よりも南寄りにできて、昼には真北を通り、夕方には真東より南側に影が伸びます。
もうおわかりですね。
夏至の日は太陽が北よりから南にいき、また北よりに戻ってくるため、影も東西の線をまたいで南から北へ移動し、また南へと戻るのです。
さて、ではこれは説明できるでしょうか。
なぜ春分と秋分の日の影は一直線上を動くのでしょうか。
夏至と冬至の影の動きを説明できれば、連続変化であることからその間と推測でき、そこから直線になることを説明できなくはありません。
そういう考え方でも理屈は通っているので問題ないでしょう。
では図形的にはどうでしょうか。
これは真東から見た図を書けばわかるでしょう。
春分・秋分の日は、真東から登り、真西に沈みます。
この時の太陽の動きは球の半径と同じ長さを半径とした円周上の移動になります。
そして太陽は地球からとても遠く離れたところにあるため、光は平行光線として考えられます。
地面に立てる棒は太陽に比べてとても小さいので、棒を立てた地点に棒の先端があると考えてもわかるでしょう。
こう考えると常に太陽の位置と棒を立てた地点が、太陽の軌道を表した直線状を移動していることがわかります。
だから影の先端もずっと同じ直線状を動くのです。
ここまで説明できれば、春分・秋分の日の太陽の動きは理解している考えて間違いありません。
日時計の影の先端が一直線上を動く
春分・秋分の日の太陽の動きはオリオン座の三つ星の軌道と同じ
オリオン座の三つ星は、真東から昇り、真西に沈む星座として有名です。
中学受験では、それを知っていること前提に問題が出ることも多々あります。
春分・秋分の日の太陽の動きも真東から昇り、真西に沈みますね。
だから春分・秋分の日の太陽の動きと、オリオン座の三つ星の軌道は同じになるのです。
春分、秋分の日の太陽の軌道は、オリオン座の三ッ星の軌道と同じ
祝日になった理由
日本の祝日は天皇が行う宮中祭祀と大きく関わりがあります。
それを知っていれば、宮中祭祀で、春と秋を大切にしていた理由も推測できるでしょう。
日本は長い事農耕を営んできたため、植物が芽生える春はとても重要な節目だったのです。
そして秋はその収穫が終わり、生命に感謝するタイミングだと考えられます。
実際、祝日法には
- 春分の日:自然をたたえ、生物をいつくしむ。
- 秋分の日:祖先をうやまい、なくなった人々をしのぶ。
とあります。
これがわかれば、なぜ夏至と冬至が祝日にはならなかったのかも推測できるでしょう。
お彼岸
春分・秋分の日とその前後3日間の合計7日間のことをお彼岸(おひがん)と言い、お墓参りをしたり、お供え物をしたりします。
元々農作物に対する信仰から、太陽に対して願う「日願(ひがん)」というお祈りと、仏教で三途の川の向こう側(あの世側)にある岸を「彼岸」と言ったこと、それらが合わさって春分・秋分の日に先祖を敬う行事としてお彼岸が誕生したと考えられています。
春分・秋分の日あたりは農作業にゆとりができやすかったことも一因かもしれません。
お供え物として、春分の日は牡丹餅(ぼたもち)、秋分の日は御萩(おはぎ)が用いられますが、これらは全く同じ料理で、春に咲く「牡丹(ぼたん)」と秋に咲く「萩(はぎ)」の花に由来しています。
ただ、これには諸説があり、地域によって牡丹餅と御萩は解釈が異なりことがあります。
共通しているのは、どちらも小豆(あずき)ともち米を使用している点です。
これは小豆には邪気を払う効果があると考えられているためです。
太陽や火は文明の発展において重要な役割を果たしてきましたから、赤い色は縁起がいいと考えられていたのでしょう。
そのため小豆は羊かんや最中(もなか)などの和菓子、お汁粉や赤飯などの料理にも用いられてきました。
ちなみに現在は小豆は90%以上が北海道で収穫されていますが、以前は日本各地で生産されていたようです。
春分・秋分を受験に役立てるための実践
春分の日は国民の祝日の1つになっており、自然をたたえて生物を慈しむ(いつくしむ)日、将来のために努力する日、となっています。
また、名前の通り、春(もしくは秋)を分ける日です。
節分などと同じように、季節の一つの境目なのです。
よって、この日を境に暖かくなってくると言われています。
というわけで、二十四節気の1つである春分、秋分の意味を考えさせてみるといいでしょう。
オンライン授業でもよく聞いていますが、漢字さえ知っていれば、簡単に推測できます。
そこから、二十四節気に派生させて、調べさせてもいいでしょう。
日本の祝日との関係が見えてきますし、知っている行事との関連もできてくるでしょう。
そして何より可能なら理科につなげたいところですね。
先程お話したように、春分と秋分は太陽の動きと大きく関係してきます。
そして昼と夜の長さとも関係してきます。
春分と秋分に関しては、昼と夜の長さが同じになりますね。
なので、日が出る時間と日が沈む時間を推測させてみれば、6時と18時になることがわかるはずです。
そこで実際に意識させてみると、ズレていることに気付くはずです。
この原因は標準時子午線と経度の差にあります。
これは計算でも出せるんですね。
計算して一致すると結構感動するものですよ。
さらに、太陽の動きが、真東から昇って真西に沈むことから、太陽がある場所と時刻から、方角がわかることになります。
これも実際に試してみるといいでしょう。
なお、春分と秋分の日の太陽の南中高度は、日本では「90ー緯度」で計算できます。
北緯35°地点なら、90-35=55°ですね。
tan55°≒1.4なので、12時の時の影の長さの1.4倍が身長ということになります。
このように春分、秋分だからできる計算や体験を通して考えることで、イメージしやすくなるため、テキストとにらめっこして覚えなくても理解できるようになっていきます。
春分と秋分は1年に各1回ずつ、6年間で12回もあります。
これだけチャンスがあるのに、天体が苦手な子が多いのはどうしてでしょうか。
このチャンスを活かさず、机に縛り付けているからに他なりません。
それでできるようになるなら構いませんが、何度やってもできるようにならないのなら、他の方法を考えませんか?
受験程度の勉強は、泣きながら机に座らせなくても解けるようになるのです。
ファイのオンライン授業では月1万円で、身近なことと関連付けていく方法をアドバイスしています。
机に座らせることに限界を感じている方は、ぜひお問い合わせ下さい。
-1024x576.png)





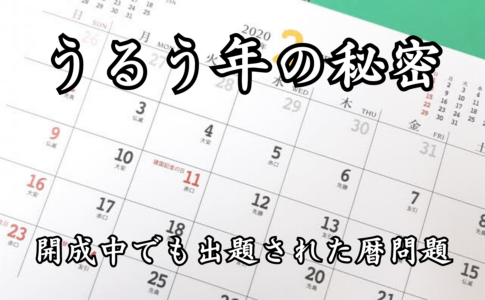
-12-485x300.png)
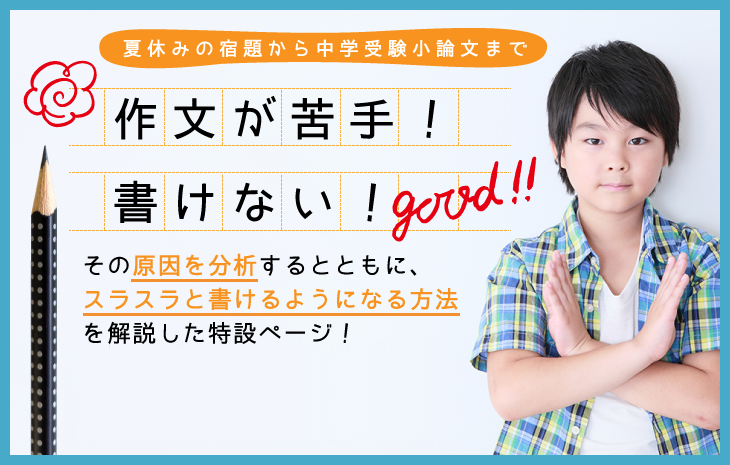
-3.png)



-5-485x300.png)

-34-485x300.png)


-3-485x300.png)
-32-485x300.png)
-36-485x300.png)





「春分の日に関することで、中学受験に関係することはありますか?」