目次
イベントは中学受験ネタの宝庫!
今回は中学受験に使えるお正月関係のネタを、オンライン授業で話題にしてきたものをベースに紹介しましょう。
実際に塾生が興味を持って食いついてきたネタなので、そのまま受験勉強にも通じやすいでしょう。
最近は日本の文化を経験しているかを確かめる問題が増えてきています。
また入試に直接関係していなくても、関連事項が出題されることも多々あります。
覚えさせる必要はありません。
興味がありそうな話題を、受験と関連付けるために使って下さい。
お正月とは
正月というのは、旧暦において1月を正月と呼んでいたものの名残です。
旧正月と呼ばれるのが旧暦のお正月です。
元々の語源は政治一筋だった秦の始皇帝の誕生月を政月(政治の月)と呼んでいたことに由来すると言われています。
古来日本からある和風月名では、1月を睦月(むつき)といい、家族がそろって仲良く過ごす月と言われています。
仲睦(むつ)まじいという漢字が使われていますからね。
以前は1月全てを表す言葉でしたが、現在では三が日(1月1~3日)を指す言葉として使われています。
なお、事実上休みになっていることが多いのですが、祝日扱いなのは1日(元日)のみです。
初日の出に関する中学受験ネタ

「なんで初日の出って千葉県が一番早いんですか?北海道の根室の方が東にあるから、そっちの方が早くないですか。」
そうなんですよ。
初日の出が一番早く出る場所として有名なのは、千葉県の犬吠埼(いぬぼうさき)なんですね。
でも根室の方が東側。
これはとても大切で、中学受験でもひっかけ問題としてよく出てきます。
そして、オンライン授業でも毎年誰かが聞いてきます。
そこから結構授業が広がるので、その話も紹介しておきましょう。
考えるときのポイントは、以下の通りです。
・太陽は東から昇る。
・お正月(冬)は南に行くほど日が長い。(オーストラリアは夏)
・高い所ほど地平線がより遠くまで見える。
- 北海道納沙布岬:北緯45度,東経145度
- 千葉県犬吠埼 :北緯35度,東経140度
- 東京都南鳥島 :北緯25度,東経155度
- 東京都沖ノ鳥島:北緯20度,東経135度
- 富士山山頂 :北緯35度,東経139度
- 兵庫県明石市 :北緯35度,東経135度
- 沖縄県与那国島:北緯25度,東経125度
数値は概数
日本で一番日の出が早い場所
以上を踏まえて考えると、日本で一番東(東経154度,北緯24度)に位置する南鳥島が一番早く、日の出は5時27分です。
南鳥島は日本本土よりも赤道に近く、高さをカバーできるぐらい東に位置しているのです。
なお、南鳥島には研究者が住み込みで働いているのみで、定住者はいません。
離島を除いて一番早く昇る場所
では離島を抜かしたらどこが一番早く昇るのでしょうか。
ここで引っ掛かる子が多いのですが、離島を除けば一番早いのは富士山の山頂、6時42分です。
標高が3776mもありますからね。
富士山は高さでカバーしているのです。
離島と山を除いて一番早く昇る場所
では富士山といった山を除いた平地で考えるとどこが一番早いのでしょうか?
これも一番東に位置する北海道の根室の先っちょ、納沙布岬(のさっぷみさき)だと思う子が多いのですが、実は千葉県の銚子の犬吠埼(いぬぼうさき)が一番早く、6時46分に昇ります。
これは冬は北に行けば行くほど日が短くなる、つまり日の出も遅くなるということになるため、南側かつ東に位置する千葉県が一番早くなるのです。
ちなみに納沙布岬は6時49分。
3分しか差はないけど(笑)
初日の出フライト
なお、この原理でいけば飛行機が一番高く、かつ東に飛んでいけるため、場所によっては飛行機から見る日の出が一番早くなります。
しかし、初日の出フライトは富士山をバックに日の出が見られるように飛行経路が取られることが多いため、初日の出の時刻は富士山の日の出とあまり大差がありません。

日本で一番日の出が遅い場所
日本で日の出が一番遅いのは、一番西に位置する沖縄県の与那国島になります。
これは場所と名前さえ知っていれば答えられるはずです。
そこでもう一歩踏み込んで、

「日本で一番日の出が遅い場所での日の出の時刻は何時?」
と聞いてみましょう。
これは今までの話から簡単な計算で導けます。
そんなに難しくありません。

北に行くほど日の出ている時間が短くなってしまい、日の出の時刻にズレが生じてくるため、同じくらいの緯度の場所、南鳥島で比べます。
・東京都南鳥島 :北緯25度,東経155度
・沖縄県与那国島:北緯25度,東経125度
なので、経度の差は約30度。
太陽は24時間で地球を一周(360度)回っているため、時差(南中する時刻の差)は1時間につき15度、30度では2時間分の差。
よって南鳥島の5時27分より2時間遅い、7時半頃。
となります。
簡単でしょ(笑)
オンライン授業でもやらせてみますが、結構計算してくれるものですよ。
実際には7時31分ということなので、ほぼ計算通りになりましたね。
誤差は数値が概数を用いているために生じているものです。
日の出と月の出の時刻の基準

「日の出は太陽が出たときでわかるんですが、月って形が変わるじゃないですか。新月だとそもそも見えませんし。でも月の出って言いますよね?月は何を基準にしているんですか?」
これは中学受験でも問われるので押さえておくといいでしょう。
日の出は、地平線から太陽が出始めた時刻です。
ちょこっとでも顔を出せば日の出ですね。
月の場合は満ち欠けしてしまうためそうもいかず、月の中心を基準にして月の出の時刻を出しています。
もし見た目の月を基準にしていたら、新月の時の月の出がないことになってしまいますし、三日月のように欠けていると正しく計算できなくなってしまいますからね。
日の出:太陽が出た時の時刻
月の出:月の中心が出た時の時刻
初日の出の由来

「なんで初日の出を見に行くんですか?日の出なんて時間が変わるだけで、いつ見ても同じじゃないですか。わざわざ寒い中見に行かなくてもいいのに。」
これもファイのオンライン授業で毎年誰かが言っています。
そんな可愛げのないこと言わなくてもいいのに(^^;)
でもこんな話でも、ちゃんと受験に通じてくるものです。
まず暦がなぜ誕生したのかを考えさせてみましょう。
暦(こよみ)は作物を育てるためのカレンダーとして誕生したものです。
そして作物の育成には太陽の光が欠かせません。
よって、1年の始まりに太陽に拝むことで、その年の豊作(五穀豊穣)や幸せを祈っていたのです。
ただ「綺麗だから」見ているわけではないのです。
綺麗な日の出なら、1年中見られますからね。
元々は天皇が元日に行っている四方拝(しほうはい)というお祈りの儀式に習って、庶民の間でも初日の出を拝む風習が広まって行ったものです。
四方拝は覚えておく必要はありませんが、日の出を拝む理由については、ちょっとした予備知識があれば推測できるので、考えさせてみるといいでしょう。
また、日の出はニュースの中継であちこちから出る日の出をやりますから、時間のずれを意識させてあげるだけでも地理の感覚が身につけられるでしょう。
折角のお正月ですから、勉強としてではなく、家族行事として、様々な経験を通して学ばせてあげて下さいね。
オンライン授業でも、テレビでいいから見ておきなと話しています。
ガツガツ勉強させなくても、こうやって身近なところから中学受験の勉強はできるのです。

元旦と元日の違い

「元旦と元日って何が違うんですか?一本線が入っているだけで紛らわしいんですけど。」
元旦とは初日の出のことです。
「旦」の字が地平線から日が昇っている様子をそのまま表しています。
それに対して元日は1月1日のことを指します。
元旦:初日の出
元日:1月1日
お年玉の由来

「お年玉ってなんで玉なんですか?玉がお金だったんですか?」
なんて無邪気に聞き出すと、男の子には大うけしますが、まぁこうやって自分なりに考えるのは大切ですね。
面白い答えが出ても馬鹿にしないようにしましょう。
でもちょっとヒントを出すとすぐに気付くものですよ。

「いい考えだね。昔は何がお金だったか考えればわかるんじゃないかな?」
オンライン授業でもこんな感じでヒントを与えると、芋づる式に考えて答えにたどり着きます。
さて、お年玉はもともとお餅のことです。
農業の国だった日本にとって、太陽は神様。
その太陽によってつくられたお餅は魂だと考えられ、それを分け与えることで活力や幸福につながると考えられていました。
そして日本は江戸時代までお米がお金の役割を持っていました。
ところが明治時代以降、税金もお米(年貢)からお金に変わっていきました。
そしてお餅がお金だった時代には、目上の人から目下の人へ与えていたものでしたが、次第にその対象が子どもへ変化していったのです。
それが現在の形になったお年玉です。
よって子どもにお年玉をせがまれたら、お餅をあげておきましょう(笑)
なぜ凧を上げるのか

「お正月って何で凧揚げするんですか?」
簡単に言うなら、「立春に空を見上げるのは健康にいい」と言われていたためです。
寒くて家の中で縮こまっているのはよくないから、外で空を見上げるのがいいということでしょう。
そのため、健康療法を遊びとして取り入れた、という感じですね。
現代でいうところの「スマホばかり見ていると視力が下がるから、外で遊んで来い」というのと同じですね。
ちなみに現在は凧揚げと言われていますが、元々はイカノボリと言われていました。
下につけたバランスを取るための尾の部分は、タコというよりイカの触腕ですよね。
ではなぜイカだったものがタコになったのかというと、江戸時代にイカのぼりが流行り過ぎたことが原因です。
あまりに流行り過ぎて、喧嘩や事故が多発したのです。
大名行列に落ちたり、怪我や死人が出たりするほどだったといいます。
そのため、幕府は1655年に「イカノボリ禁止令」を出しました。
しかし急に趣味を奪われた庶民は、「これはイカではなくタコだ!」と屁理屈をこね始めました。
こうしてたこ揚げとなったのです。
そして「凧」の漢字は中国にはない日本オリジナルの漢字で、「風をはらむ布」のイメージを漢字にしたもので、「いかのぼりじゃないよ」ということを明確にするために漢字が作られて広まっていったと言われています。
なお、たこあげの由来については諸説があり、地方でも様々です。
年賀状の由来と役割

「年賀状を出す宿題があるのですが、先生に出してもいいですか?」
年賀状は日本の伝統的な文化ですからね。
学校でも教えていますし、その文化に触れておくのもいいでしょう。
こういう時には、こんな話題を振っています。

「年賀状っていつからある文化だと思う?」
年賀状は小学校低学年で習うものなので、日本の歴史はまだ知りません。
でもこんな話題を振ってしまいます。
それでいいのです。
これをきっかけに由来に興味を持ちだすことが結構あるのです。
さて、年賀状の歴史は古く、平安時代には既にあったといわれています。
元々は電車やバス、メールなどといった近代文明がない時代に、滅多に会えない人に対して近況報告を兼ねて送るものでした。
そのため、正月明けにすぐに会える人には送っていません。
現在ではイベントの一環として続いている伝統行事ですが、本来の意味から考えれば、休みあけにすぐに会える人には送らないものなので、送らないのが失礼に当たるわけではないはずですが…
でも職場関係では送らないと失礼に当たるという雰囲気がありますね。
これは文化を誤解したハラスメントな気もしますね。
また、近況報告という意味でもSNSが発達していて、会えなくても近況が分かるため、年賀状の本来の意味は失われてしまいました。
まぁイベントなので、話すきっかけにして楽しむのもいいでしょう。
また、やはり手書きは味が出ますからね。
最近は印刷がメインですが。
年賀状反対派という訳ではありませんが、電子化を否定するつもりもありません。
時代に合わせて変わっていってもいいでしょう。
お節料理を用いた食育

「おせち料理ってダジャレみたいな由来があって面白いですよね。あれ、全部にあるんですか?」
お節料理は非常に奥が深い、究極のダジャレ集とも言える作品です。
そして究極の食育ともいえる料理集です。
これを逃す手はありません。
ここではオンライン授業でも人気な、中学受験に関わる知っておくと得するネタを紹介しましょう。
細かい部分は地方によっても異なりますし、全部説明しているとキリがないため、興味を持ったものは親子一緒に調べていくといいでしょう。
おせちの構成
おせちは正式には一の重~五の重で構成されています。
- 一の重:甘めのおつまみ系
- 二の重:焼き物系
- 三の重:煮物系
- 与の重:酢の物系 ※四は忌み数字
- 五の重:今後の余地を願った控えの重(空の重)
最近は食べきれないこともあるため、減らした一の重~三の重の3つで構成されているものもあります。
- 一の重:甘めのおつまみ系
- 二の重:海の幸
- 三の重:山の幸
最近はさらに簡易的なおせちも多くなり、雰囲気を楽しむように変わってきましたが、基本的にメジャーな縁起物は同じです。
次に中身の縁起ものについてお話しましょう。
縁起物が表す、げんかつぎの意味
メジャーなものを中心に紹介しておきます。
中でも中学受験に通じてくる派生のネタは色をつけてあります。
ぜひ話題にしてあげて下さい。
- 栗きんとん:黄色を黄金に見立てた願い。栗の構造。
- 黒豆:まめに働くように。豆の構造。
- 昆布巻き:よろこぶ(よろこんぶ)。加工前の姿。
- 数の子:ニシンの卵を二親(にしん)とかけた子孫繁栄。魚の卵。
- 伊達巻き:巻物に似ていることから知識が豊富になるように。伊達政宗。
- 田作り:カタクチイワシ(干鰯:ホシカ)を肥料にしたところから五穀豊穣。
- かまぼこ:日の出のイメージと紅白。日の出の定義。
- 鯛(タイ):めでたいのダジャレ。魚の構造。
- エビ:背中が丸くなるまで長生き。長寿。甲殻類の構造。
- ブリ:出世魚であることから出世できるように。青魚の特徴。
- ハマグリ:ピッタリ重なる殻は1つしかない事から、夫婦円満。貝の構造。
- ごぼう:ごぼうのように、代々深く長く根を張る家系になるように。キク科。
- 里芋:一つから沢山できるので子孫繁栄。サトイモ科、こんにゃくのつくり方。
- レンコン:先が見通せるように。地下茎・通導組織。
- 紅白なます:水引をかたどっているところから平和を願う。大根のように家の土台がしっかり根を張るように。アブラナ科とセリ科。
- 梅干し・干し柿:梅、柿は長寿であることから。種の構造、バラ科、種の構造。
これらを覚える必要なんてありません。
大抵、説明書きがついています。
それを読み、由来や特徴を意識しながら食事を楽しむだけでも全然違います。
まさに食育ですね。
これだけの料理が一度に触れられる機会はなかなかありませんからね。
やはり知っている子はおせちネタから産地や名産、植物や動物の構造、特産品といった話につなげやすくなります。
一つを掘り下げるだけでも十分話題が広がりますので、ぜひ触れてみましょう。
鏡餅を用いた食育
鏡餅の上のみかん ← 違うよ!

「鏡餅って何?なんでみかん乗せるんだろう?」
1月11日~20日頃に食べる鏡餅。
オンライン授業でも毎年出る鏡餅の話題。
そこから鏡餅の上に乗っている果物の話になると、必ずと言っていいほど「みかん」と言われますが、鏡餅の上に乗っているのはみかんではありません。
あれは橙(だいだい)です。
まぁ同じミカン科ですからどちらでもいいと言われればそれまでですが、お正月は縁起物のオンパレードですからね。
橙も当然縁起を担いでいるわけです。
オンライン授業ではここでちょっと疑問を投げかけてみます。

「なんでミカンじゃなくて橙を乗せているんだろう?」
子どもも大好きなダジャレですから、すぐわかります。
橙(だいだい) ⇒ 代々
つまり代々続くことを願って置いているのです。
みかん = 未完
じゃまずいでしょ?(笑)
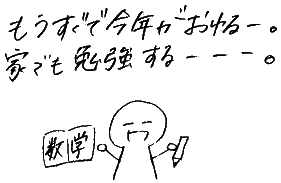
みかんと橙の違い
みかんと橙の違いは、まず大きさ。
橙の方が一回りぐらい大きく、皮が厚い。
そして味も酸っぱめ。
さらにみかんは冬になると実が落ちてしまいますが、橙は実を着けたまま春を迎えられます。
「みかん(未完)は落ちるけど、橙(代々)は落ちない!」
のです。
ちょっとうまいこと言った(笑)
そして不思議な事に皮の色がまた緑に戻るのです。
なお、鏡餅は当時神聖だった銅鏡をイメージしていると言われており、鏡餅の文化自体は平安時代にはすでにあったらしいという事がわかっています。
みかんの英語は「さつま」
ちなみにみかんのことをイギリスでは「さつま(Satsuma)」と言います。
これは薩摩藩が貿易でイギリスにみかんを輸出していたため。
ただの鏡餅ですが、その中にもこのように学べる事が沢山あります。
要は興味を持つか持たないか。
親が興味を持たないものを子どもに興味を持てというのは無理な話。
知っている必要はありませんが、一緒に調べて話すだけでも学びのきっかけにつながります。
鏡開きを用いた食育
鏡開きの日

「鏡開きって何?何でお餅なの?」
オンライン授業では毎年誰かが疑問に思うこの質問。
ファイのブログではオンライン授業で塾生たちが興味を持ったものを中心に載せています。
ということは、高確率で子どもは疑問に思うという事です。
それを使わない手はないでしょう。
特に食べ物に関するものは中学受験にも通じる食育になりますからね。
さて、鏡開きとは、関東では1月11日に、関西では1月20日に行われることが多い行事の1つで、飾ってあった鏡餅を食べる日です。
鏡餅は年神様を迎えた時の依り代(居場所)となるもので、大きく丸い形が神具である鏡に似ていることから、お餅を鏡に見立てて神様が宿る場所と考え、お供えしました。
お正月に、この年神様の依り代となった鏡餅を片付けることで、神様を送る意味合いがあります。
- 関東:1月11日
- 関西:1月20日
鏡開きの方法と食べ方
神様が宿る場所なので、刃物を向けることは許されません。
そこで、お餅を叩き割ることで食べやすくしていました。
これが鏡を割っている様子と一致することから、鏡割りと呼ばれるようになりました。
しかし、「割る」という言葉が縁起がよくないとのことで、「開く」という言葉が使われるようになりました。
ちなみに酒樽のふたを木槌でパカーンと割る儀式も鏡開きと呼ばれますが、あれは「鏡割り」「鏡抜き」とも呼ばれます。
調理は一般的にお雑煮、お汁粉にして食べます。
神様が宿っていたものなので、エネルギーがあると考えられているため、残さず食べるのが良いとされています。
お餅が膨らむ原理

「普通のお米ともち米って何が違うんですか?普通のお米をついてもお餅にはならないんですか?」
これはぜひ実際にやってみて下さい。
普通のお米をもち米と同じようについてみるとどうなるか。
こういう違いを実際に感じることが、中学受験にも通じてくるんですね。
さて、やってみればわかりますが、普通のお米をついてもお餅のようにはなりません。
一般的に食卓に並ぶお米はうるち米といいます。
うるち米はいくらつぶしても叩いても、お餅のように伸びません。
これはお米に含まれているデンプンの違いによるもので、もち米はよく伸びるアミロペクチンのみで、うるち米に20%程度含まれているアミロースがありません。
- うるち米:アミロース(20%)+アミロペクチン
- もち米:アミロペクチン(100%)
※アミロペクチンは炊くと粘り気が出るでんぷん
そしてお餅はつくことによって、水と空気をたっぷり含みます。
言い換えると、水と空気をたっぷり含ませるためについているんですね。
これを焼くと、お餅の中の水分が水蒸気となり体積が増加。
そしてお餅(アミロペクチン)は伸びやすいので風船のように膨らみます。
これがお餅が膨らむ原理です。
ちなみに煎餅(せんべい)も餅という漢字が入っていますが、基本的にはもち米ではなくうるち米を使っています。
これは餅という漢字が元々小麦粉をこねたものに使われていたことに由来しています。
また、うるち米からアミロースを除いてアミロペクチンのみにし、もち米のようにすることも可能です。
とても面倒ですが(笑)
化学的方法で分離するなら、まずお米のでんぷんを完全糊化する必要があります。これはお米のでんぷんにはアミロースと脂質の複合体が多数存在するためで、簡単には分離できないためです。よって、一般家庭でこれを再現するのは中々難しいでしょう。
アミロペクチンの割合を増やすことで、疑似的にもち米に近づける方法としては、あみろペクチンの割合が多い白玉粉(もち米でんぷん)や片栗粉(馬鈴薯でんぷん)、コーンスターチ(トウモロコシでんぷん)を使う方法があります。
また、アミロースは熱水にわずかに溶けるという性質があるため、熱水に溶かして上澄み液を捨てる、という作業を繰り返すことにより、アミロペクチンの割合を増やすことができます。
中学受験は机上で完結するな!
中学受験真っ只中だと、ついついお正月でも勉強させようとしがち。
しかし、お正月にはお正月にしかできないことがあります。
そして、家族で過ごす年末年始のイベントも、お正月ならではの食育も、1年を通じてこの時しか楽しめません。
そういったものを無視してまで受験勉強をさせる意味、本当にありますか?
ファイのオンライン授業では、冬休みに勉強しろとはいいません。
年末年始特訓講座、お正月合宿みたいなものもやりません。
やる必要がないのです。
そんなことしなくても、後れを取らないから。
何度も同じ問題を解かなくても、できなくならないから。
そんな冬休みを遊んだだけでできなくなるような勉強法は教えていません。
むしろ家族と一緒に遊んだ方が、勉強にも通じるというものです。
その一端がこの記事にも書いた通りです。
こうやって身近なものから学べる子にとって、受験勉強なんて大したことではありません。
もっと難しい勉強をしていますからね。
何度繰り返しても伸びなかった。
正月も親が張り付いて勉強させないと合格できない。
そんな状態では、仮に合格できたとしても、中学生になって落ちぶれてしまうでしょう。
旧態依然とした勉強スタイルがうまく行かない方は、ファイのオンライン授業をご検討下さい。
-1024x576.png)





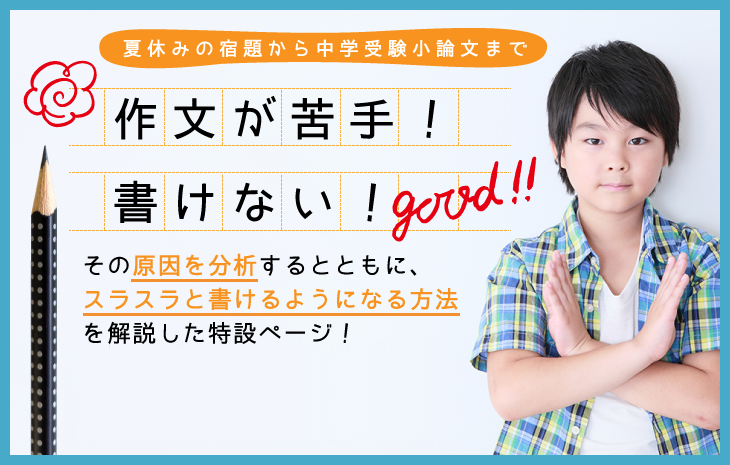
-3.png)


-34-150x93.png)

-5-485x300.png)
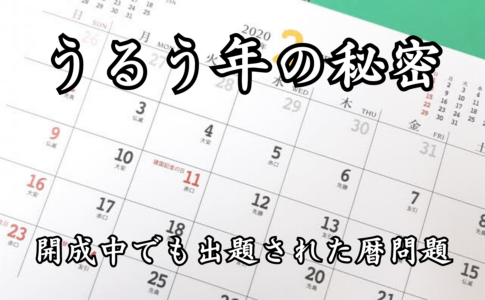


-10-485x300.png)

-36-485x300.png)





「お正月ってなんで『正しい月』って書くんですか?他の月は正しくないんですか?」