目次
自由研究に関する動画
自由研究の題材
はじめに
ここでは自由研究の題材、ネタとして子どもがよく聞いてくる疑問を載せておきます。
また、実際に受賞した作品の例もいくつか紹介しておきます。
しかし、あくまで題材のヒントとするものなので、それをそのまま自由研究にしようとしても、ただの調べ学習で終わってしまいます。
また、子どもだけで行うにはハードルが高いので、保護者の方が誘導しながら行ってあげて下さい。
※ファイの塾生は先生に相談しながら進めていきましょう。
ぜひじっくりと、自分なりに取り組み、実のある研究にして下さい。
絶対にやらない方がいいのは、結果ありきの研究です。
これは研究でもなんでもありません。
自分で予想し、試してみて、考察する。
このスキルがそのまま勉強のスキルにも通じてくるのです。
以下に自由研究の題材の例を紹介しましょう。
なお、この中には実際に受賞しているものもあります。
身近な疑問と生活の知恵から考える自由研究の題材
いわゆるおばあちゃんの知恵袋的なものを調べ、体系化していくのも十分研究になります。
- なぜ綿あめは時間が経つとしぼんでしまうのか。
- ホコリはなぜ灰色しかないのか。
- 日傘の構造と日よけ効果の検証。
- 子どもをチャイルドシートから載せ降ろししやすい傘の研究
- 美しいオーシャンブルーになるための条件についての研究。
- ポニーテールが揺れる理由。
- 空気の流れと効率的なエアコンと扇風機の使用法。
- 風紋(ふうもん)はどうやって形成されるのか。
- 抹茶はなぜダマになるのか。
- 酸性雨により溶けているものを調べる。
- コナン君のトリックは、実際に使うことができるのか。
- たき火の煙は、なぜ風上に向かうのか。
- 夏を涼しく過ごすための工夫について。
- 温暖化の原因になっているものをマッピング調査し、その影響を実験により調べる。
- 光と熱で除草する方法を考える。
- バナナの皮は本当にすべるのか。
- なめこの味噌汁はなぜ冷めにくいのか。
- 財布を軽くする支払いの知恵。
- スーパーの野菜の産地とその特色を調査し、なぜそのような特色が出るのかを調べる。
- 野菜や果物を日持ちさせる工夫とその原理。
- 横断歩道で車に止まってもらうための工夫(ナッジの研究)。
- 果物や野菜の種の配列を調べてみる。
- 髪を効率よく乾かす方法を考える。
科学的な自由研究
SDGsやESDという形で時事問題の題材にもなることが増えた環境問題とも関連がある電気。この自由研究も人気が出てきています。ただし、既にわかっていることを実験で確認するだけでは研究として認められません。それを活用する提案とセットで研究するといいでしょう。
- ボルタ電池による発電実験。
- コイルを巻きつけた筒の中に磁石を入れて振ることで発電する実験。
- 自然エネルギーを用いた発電実験。
- 燃料電池に関する実験。
若干実験器具が必要になりますが、最近はネットショップで簡単に手に入るので、実験自体にはそこまで苦労しません。ただし、実験器具を使うと実験結果や考察も画一化しやすくなるため、実験内容や題材自体に工夫が必要になります。
- 虹ができる条件を考え、虹予報を作成する。
- 金属が虹色に見える理由。
- 物質の屈折率を調べてみる。
- 合わせ鏡の原理を活用する研究。
- ペーパークロマトグラフィーを活用する研究。
いわゆる物理に関するものは、大抵実験器具から入るものですが、それを身近な現象の中から説明していくと、それだけでも研究になります。
- チョークの折れ方。
- 地震に強い構造。
- 転がる水滴の形。
- スーパーボールロケット(弾性力)の原理を用いた実験と研究。
- 起き上がりこぼしや振り子の重心を用いた実験と研究。
- ダイラタンシー現象を用いた実験と研究。
- マグネットを用いて空中へ浮かせる原理を用いた研究。
- 無線通信の原理の研究。
十円玉を綺麗にする実験に代表される自由研究ですが、十円玉の研究自体がいけないわけではありません。無難すぎて結果もわかってるものを研究にする姿勢が評価されないのです。よって、一般的ではない方法なら評価される可能性は十分あります。例えば、酸で溶かす方法は一般的ですが、酸化還元反応を用いて元に戻す方法はあまり載っていません。
- 十円玉を綺麗にする。
- 身近な液体の性質を調べる。
- 重曹は本当に汚れ落としに効果的か。
- 水の硬度による違いの比較と、そのメリットを活かした活用法の調査。
- 様々な汚れを落としやすい水溶液を探す。
- 透明な氷をつくるための工夫とその原理。
- バタフライピー(色が変わる紅茶)の原理と応用。
- シャボン玉の構造と原理の応用に関する研究。
- 保冷剤の原理と活用方法に関する研究。
※硬貨を破損させたり加工したりする行為は貨幣損傷等取締法に抵触する可能性があるので、オススメはしません。
生命体に関する研究は一朝一夕ではできません。しかしそれゆえ思いもよらぬものを発見することもあります。例えばアリジゴクや蚊に関する研究で、専門家の定説を覆したのは小学生の自由研究です。
- アリジゴクの生態。
- 蚊に刺されやすい人の条件。
- カビが生える条件とその予防法。
- カビはどこからくるのか。特定の場所に残る菌が掃除されずに残っていて、常に増えていく可能性の研究。
- 変形菌の研究。
- 音を出す動物たちの生態。
- 羽の不思議。
- ダンゴムシの歩き方に関する研究。
かなり時間がかかる上、すでに解明されていることが多いテーマにはなりますが、逆に言えば入試で狙われるような題材を実際に自分の目で確かめてみることができます。また、身近であっても誰も気に留めなかったような思いもよらないネタは評価されやすい傾向にあります。
- 化石の発掘。街中の石材から化石を探す。
- 天体観測、気象観測・空の研究。
- 雨の日にシャボン玉が割れにくい理由。
- 砂が作る泡の研究。
- クモの糸にできる水滴の研究。
- ストームグラスにできる結晶の形と天気の関係について。
ドライアイスを用いた実験は多くありますが、単に実験するだけでは自由研究とはいえません。また、既に知られた原理を解明するだけでも研究とは言えません。そのため、これを何かに利用できないか考えるところまで含めて自由研究と考えることにより、価値のある研究にすることができます。
- ドライアイスにコインを刺した時に音がなる原理を用いる研究。
- ドライアイスをアルコールに入れると霧が発生しにくい理由の研究。
- ドライアイスを机の上で滑らせたときに摩擦が軽減することを用いる研究。
- ドライアイスが気化した気体を集めてシャボン玉を浮かせられることを用いる研究。
- ドライアイスが気化するときに体積が膨張することを用いる研究。(ドライアイスエンジン)
仕組みに関する自由研究
- エスカレーターは、1列?2列?
- 大根おろしで紙は強くなるのか。
- 糖分含有量が多い飲料・食品とその傾向。
- ゴミの活用法。
実在するもので、すでに大きさがわかっているものであっても、まだその大きさや計測の仕方を知らない小学生には十分研究となります。
- 月のうさぎの大きさはどれくらい?
- 東京タワーとスカイツリーが同じ高さに見える場所はどこ?
工作系の自由研究は、作るだけではただの工作になってしまうため、その原理について調べ、その応用まで考える必要があります。その点、自由研究にするには方針が立てにくく、難しいところですが、結論の持っていき方さえ決まっていれば、一日で完結させることもできる自由研究になります。
- ストームグラス(天気予報器)の製作 ⇒ 気象と状態変化
- 貯金箱の製作 ⇒ コインの違いによる仕分け
- 宙に浮いて見えるテンセグリティ構造 ⇒ 力学
- ポンプの製作 ⇒ ポンプは種類が多く、自作できるものも多い
- モーターの製作 ⇒ 電気を使わない動力もあります
- 離乳食を早く冷ますアイテム
- 髪を早く乾かすドライヤー
調査・検証による自由研究
調査による自由研究は、一般的には調べただけという扱いを受けるため、自由研究として認められません。
そのため、調査を基にした自由研究を考える場合には、検証と提案をセットにしていく必要があります。
現実に起こる現象を、ミニチュアとして再現してみる自由研究です。教科書に出てくるものを再現することができるので、汎用性があり、受験勉強にも通じやすいでしょう。
- 料理やお菓子を用いたリアス海岸の再現
- リアス海岸における津波の被害拡大の再現
新型コロナウイルスの影響でテレワークが増えたため、今まで当たり前だった文化が大きく変わってきています。それに伴い、本当に必要なのかを調査・検証する自由研究も人気が出ています。
- 世界各国の税金とその影響。
- ハンコ、印鑑の必要性。
- 十円玉を投げた時に側面で立つ確率。
- 雑草の種類と生えてくる場所の特徴、及びその確率。
- 雑草はどこから来るのか、及び雑草が生えないようにするための工夫。
- 「こすらず簡単」は本当なのかの検証。
- レシートに書いてある内容とその必要性の研究。
これならイラスト好きな女の子でも興味を引きそうな内容ですね。
- 目のバランスは人物イラストの年齢に影響する?
- ゆるキャラとその地域の特色の調査。
身近にあるけれど、あまり使わないものが何年分あるか。一生分にするといくらになるかといったものを数字を用いて調査する研究です。
- 家にあるえんぴつは10年分!?
- 散髪とスキンヘッドの費用比較。
- ペットボトルの水の購入費用と水道水の浄水の費用比較。
いわゆるまことしやかに言われている都市伝説的なものを実際に数字を用いて検証してみるタイプの研究です。
- 縦横ぴったり人間は誰だ! ~身長と腕を広げた長さを比べよう~
- おじいちゃん,俳句は絶対なくならないよ –算数が教えてくれたこと-
- 僕たちの未来(身長は,何cmのびるのか)
- 織姫と彦星は本当に遠距離恋愛なのか。
- おばあちゃんの知恵袋は正しいのか。
日本語やひらがなの成り立ちや由来を調査するタイプの研究です。
- 「あ」「め」「ぬ」はそっくり?!
- 街中のユニバーサルデザインや、バリアフリーを調査し、有効性や必要性について調査。
- 口コミの信憑性はどれほどのものなのか。悪い口コミの信憑性の徹底調査。
新型コロナウイルスによるパンデミックの影響から、認知度が急上昇した研究。過去にパンデミックは何度も起きているため、その歴史や終息までの流れ、パンデミックが起きた背景などについてまとめていくと、自由研究としてそれなりにまとめられます。
- 新型コロナウイルスのパンデミックに至る経緯と各国の対応、及びその成果。
- スペイン風邪の流行と終息までの流れ、各国の対応とその成果。
- SARS、MERSによるパンデミック。
- 天然痘の大流行と人類が唯一根絶できた要因。
- ペスト(黒死病)の大流行とその原因。
自由研究を取り組むにあたって
中学受験生となると、自由研究は時間の無駄だから代行を依頼するといった話も聞きます。
しかし、実際そうまでしても受験に成功する可能性はかえって低くなるのが現状です。
なぜなら、そんな時間の確保をしなければいけないような状態なら、すでに負けているからです。
もっと抜本的な改善をしなければ、まず逆転できません。
確かに自由研究は入試に直接関係ないものですが、昨今の入試では、実体験に基づくものが出題される傾向にあります。
そしてその中には、自由研究がテーマになっているものも少なくありません。
つまり、自由研究程度の時間を確保できない子が、受験で成功する確率は、年々下がっているのです。
よって、今現状で受験勉強がうまくいっていないのであれば、もう一度冷静に考えてみて下さい。
自由研究は、推測・施行・考察で成り立っています。
これはそのまま勉強のスキルに通じてくるのです。
逆に言えば、このスキルがないから受験勉強がうまく行っていないとも言えます。
今のまま突き進んで、うまくいくと思いますか?
うまく行く確信があるならそれでもかまいません。
しかし、うまく行く可能性がないのであれば、今のうちに方針を転換すべきです。
慌てず、ぜひじっくりと、お子様と一緒に自由研究に向き合ってみて下さい。
そうすればきっと、どうすればいいかが見えてきますよ!
もしどうすればいいかわからないようなら、学習法診断をお受け下さい。
入会不要です。
あなたのお子様が、性格的にどんな勉強法が合っているのか、ハッキリとわかりますよ(^^)/
-1024x576.png)





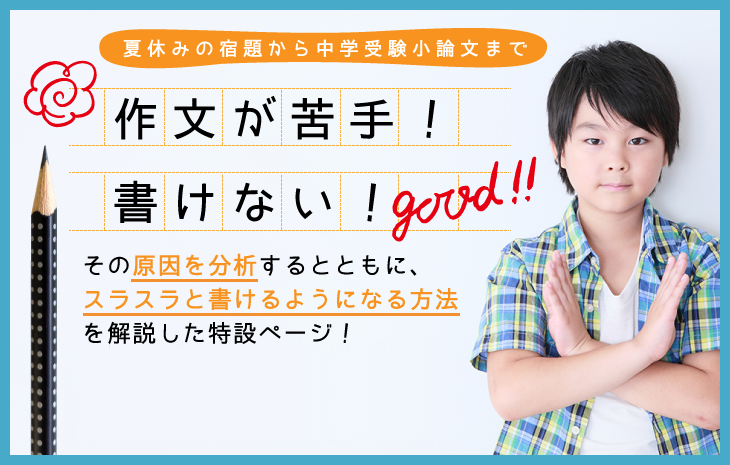
-3.png)



-485x300.png)
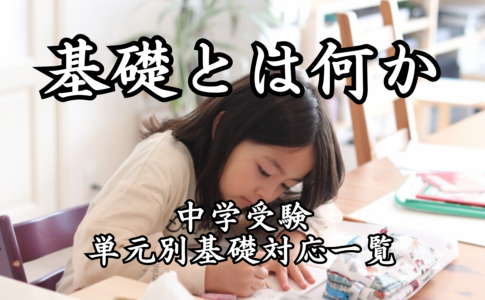
-14-485x300.png)

-11-485x300.png)
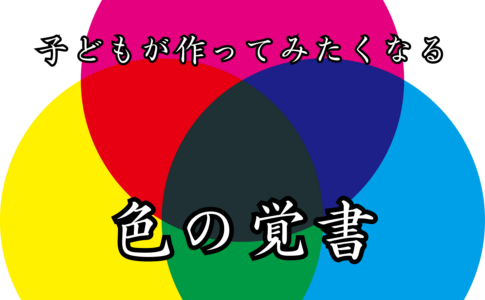






コメントを残す