目次
中学生になると勉強しなくなる
中学受験が終わった後のこの相談、かなり多いのです。
中学受験なら親がついて教えていることも多く、とりあえず勉強の土俵につけることはできます。
しかし中学生になると親も手を緩めてしまいます。
そのため、中学生になると「勉強しない!」という相談が急増するのです。
なぜ小学生の内は勉強していたのに、中学生になると勉強しなくなるのでしょうか。
実はものすごく簡単な理由なのです。
このご相談者さんを例にお話ししましょう。
勉強習慣が身についていたわけではない
小学生の内はちゃんと勉強していた。
それは事実でしょう。
しかし、それと勉強習慣が身についていたかは別問題なのです。
実は、親に言われた通り勉強する習慣がついていただけの可能性があるのです。
この場合、親が中学受験の時と同様に勉強の管理をしなければ、やるわけがありません。
そしてもう一つ。
塾のシステムに乗っていただけの可能性があります。
確かに塾のシステムは合格に向けて直球で点数を上げていけるようにカリキュラムが作られています。
そのため、それ通りに勉強していけば、成績が伸ばせるのも事実です。
しかし、そのシステムやカリキュラムにおんぶにだっこしていると、与えられたものをやるだけという習慣が身についてしまうのです。
すると、与えられなくなった途端にやらなくなってしまいます。
学習法診断を行ったこの子もまさにその状態でした。
自分で何を勉強するか考えたことがなかったんですね。
それでうまく行ってしまったものだから、中学生になっても与えられるものを待っていました。
しかし学校の宿題も大して出ません。
そして合格したのも難関中ですから、放っておいても勝手に勉強する子たちばかりです。
そのため、何をやっていいかわからないこの子は取り残されてしまったんですね。
これは塾業界が生み出した、養殖教育のシステムにはまっている証拠です。
塾がないと困る状況にあえてしているんですね。
でないと塾にお金を落としてくれなくなりますから。
本物の勉強習慣
ファイの子どもは勉強をよくやっているという話を保護者からよく耳にします。
しかし決して強制的にやらせている訳ではありません。
スパルタというわけでもありません。
いや、地元の蘇我やオンライン授業の中ではスパルタで有名ですが(^^;
まぁスパルタの意味が違いますね。
竹刀を持って追い掛け回すような熱血タイプ、根性論タイプのスパルタとは異なります。
ストイックな面でスパルタなんですね。
中学受験は大人度を試す試験です。
なので大人度が高い方が有利なのです。
ファイのオンライン授業では中学受験のために大人度を鍛えているわけではありませんが、自分に厳しくすることが、結果的に中学受験にも通用する大人度につながっていくのです。
では、どういう状態が勉強習慣が身についたと言えるのか、それらがわかる保護者の方々から頂いたコメントをご紹介致します。

「勉強が楽しくなってしまったらしく、もう寝なさいと言うまで勉強してます。今まで全然勉強してなかったのに(笑)」

「社会が嫌で嫌でしょうがなかったのですが、オンライン授業の社会は楽しいと言って授業で聞いた話を私に話してきます。私も社会が苦手だったのですが、こんな授業だったら楽しそうで私も受けたいぐらいです。」

「あれだけ数学の勉強をちゃんとやりなさい!って言い続けてたのにやらず、成績はどんどん下がる一方でした。でもオンライン授業を始めてからは、あれだけ逃げまくっていた数学の勉強を、今は毎日してます。」

「突然○○高校に行きたいと言い始めたかと思ったら、放っておいても勉強するようになりました。」

「いつもリビングにいて、主人が帰ってくると『勉強しろ!』って始まってギャーギャー言い合っていたのですが、突然勉強しかしなくなってしましました。勉強するようになったのは嬉しいのですが、主人としては寂しくなったらしく、たまにリビングに降りてくると嬉しそうに話しかけて、部屋に返そうとしないので、今度は私が困ってます(笑)」

「反抗期に顔を合わせるたびに怒鳴り合っていた息子が、自分から勉強するようになりました。勉強時間は多分他の人と比べたら少ないでしょうが、妹に教えたり家事を手伝ってくれたりするようになりました。成績よりもそれが嬉しいです。」

「オンライン授業でお世話になってからと言うもの、生活がガラリと変わりました。最初は相談する場所が欲しいと思ってお願いしたのに、『サピやめる!受験もいい!切替先生に教えてもらいたい!』と娘が言い出したものですから、正直焦りました。でも結果的に当初予定していた志望校には受かってしまいましたし、おかげさまで進学後も成績がどんどん伸びており、ファイさんと出会えて本当に良かったと思っております。」
いかがでしょう。
この子たちは受験が終わった後に勉強しなくなったと思いますか?
自主的に勉強している感じが伝わってきませんか?
この自主性が本当の意味での勉強習慣です。
実際この子たちは進学先でも伸びて、上位へ入り込んでいます。
親や塾に言われた通り勉強してきた状態なんて、勉強習慣がついたとは言いません。
ではどうして勉強が嫌いだった子が、ここまで変わっていくのでしょうか?
その答えが「放置」なのです(笑)
親や塾に頼って勉強している状態は、勉強習慣がついたとは言わない!
親や塾が離れた途端、勉強しなくなります。
これは塾がお金を貢いでもらうために作り出した養殖教育です。
オンライン授業で用いる「放置」
塾の先生ですら、

「勉強しなさいと声はかけているんですけどね。やってくれないですね。」
とおっしゃっている方がいます。

「言っても勉強してないのはわかってる。じゃあどうすればいいの!?」
この部分が解決出来ていないから何度も言わなければならなくなりますし、言ってもやらないのです。
だから、そういう時、オンライン授業では放置します。
放置というと良い印象を持たない方も多いでしょう。
「何もしてくれないの?」って。
それは違います。
オンライン授業で行っている放置は、戦略的放置です。
例えばこんな感じです。
宿題をやりたくない子

「えー!?宿題多い!」

「ならやらんでいいよ。」

「宿題減らして下さい。」

「オーケーわかった。君の宿題はなし!」

「え!?いやゼロじゃなくても…」

「無し!やらなくてオッケー!」

「いや、これぐらいならやれますから!」

「ダメ!無し!勉強禁止!」
こんな感じで、やっても意味がないと思えば、すぐに勉強禁止令を出します。

「え!?先生!勉強してくれないと困ります!」
と思うかも知れませんが、よく考えてみて下さい。
中学生になって自分で勉強してくれなくなる方が困ると思いませんか?
中学受験で一生懸命になっているさなかは気付かないかもしれません。
でも、中学受験が終われば中学生になるのです。
その時が来た時に考えようと思っても、すでに手遅れなんですよね。
言わずに自分で気付かせる

「宿題は自分で決めて!」

「じゃあこれやってきます!」

「えーっと、次の目標は何だっけ?」

「80点以上取ります!」

「ふーん?」

「足りない…ですかね…」
自覚がない子に対しては、こんなやりとりをします。
やれとはいいません。
自分で決めさせます。
大抵は甘っちょろい宿題を決めてきます。
でも何も言いません。
何も言われないと考えることを見越して、考えさせるきっかけを作るのです。
否定命令法
これは心理学で「否定命令」と呼ばれる手法を活用したものです。
「するな」と言ってしまうと、その「するな」と言われた行動が刷り込まれてしまい、結果「するな」と言われた行動をしてしまうというものです。
だからあえて肯定してしまいます。
すると今度は自分がしたくないと思ったことを肯定されてしまったことにより、その先の自分、その結果おこる自分への変化、つまり反面教師的な自分の姿を見ることになります。
「やらなかったらこうなっちゃうのかな。」
周りがいくら同じことを言ってもウザったいだけですが、自ら考えた事は「暗示」となります。
ここで最後に「やりますよ。」とか「これをやってきます。」とか自分で言い出せば、暗示にかかった証拠です。
暗示というのは耳から聞くのとは違って深層心理に働きかけるので、あとは勝手に変わっていきます。
要するに「放置」することで、自己暗示の手伝いをしているということです。

「先生!本当に勉強しなくなったらどうするんですか!?」
事実全くやらなくなる子もいます。
むしろその方が多いでしょう。
しかし半分くらいの子は半年以内に自分で勉強し始めます。
1年待てば、ほとんどの子は何かしら自分で勉強を始めます。
でも言い続けても自分からやりだす子はまずいません。
なので、実は言い続けるよりも高確率で勉強するようになるのです。
しかも、自分で考えた上でやらないという選択をした子は、自分でやろうと思ったときに強いんですね。
やるもやらないも自分の責任だとわかっていますから。
なのでやり始めれば、あっという間に成績が伸びていきます。
やらせようとしてやらせる方が大変なのです。
やれと言わない方が、高確率で勉強するようになる!
成績を上げる目標設定
もので釣る目標設定

「テストで80点取ったらゲーム買ってあげる。」
よくありがちな子供の釣り方ですが、果たしてこれは効果的なのでしょうか?
これはどの世界で活躍する人間を育てたいかにもよりますが、一般的に物で釣って勉強をさせる場合には資金力がものをいいます。
例えば、

「今回偏差値50取れたから、次は55ね!」
と、目標を上げるとします。
この場合、目標偏差値を5上げたことにより、報酬はどれだけ引き上げるつもりですか?
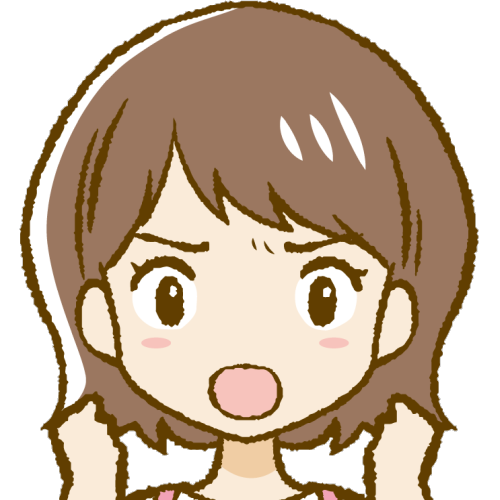
「自分のために勉強するんだから、そんなのない。報酬が上がらなくてもやるものです!」
気持ちはわかりますが、それこそ詭弁です。
自分のための勉強なら、最初から報酬など与えるべきではないでしょう。
なので、もし最初に報酬で釣ってしまうと、偏差値5を上げても手に入れたいと思えるだけの報酬を与えなければならなくなるです。
そのため、目標を上げるのであれば、勝手に上げるのではなく、子どもと話した上で、納得できる報酬を提示するようにして下さい。

「報酬を引き上げなかったらどうなるのでしょう…?」
報酬が引きあがらなくても納得して頑張れるうちはそれでも構いません。
しかしいずれ要求は増します。
資金力が切れれば子どものやる気もそこで途絶えます。
その覚悟はしておいて下さい。
なので基本的にはオススメしません。
もので釣るなら、資金がかかる覚悟すること!
スモールステップの目標設定
ではスモールステップはどうでしょうか。
実はスモールステップにも致命的な弱点があるのです。

「前回+10点で70点の目標をクリアできたから、次は80点目標に頑張ろうね!」
60点を70点にするのに比べて、70点を80点にするのは難しく、仮にこれを達成したら90点を目標にして、最終的には100点を目標にするのでしょうか。
そこまではやらない?
そう、そこなのです。
スモールステップとはいえ、点数が上がるにつれてステップは次第にスモールではなくなります。
これを考慮せずに、点数や偏差値といった数値だけで目標を決めてしまうと、次第に嫌になってきます。
この経験を何度かさせると、目標を1つ達成したらやめてしまう可能性が高くなるのです。
特に目標を達成してすぐに目標の難易度を上げられてしまうと、「もういいや」となりかねません。
スモールステップは、目的がハッキリしていないと終わりが見えないため、すぐに嫌になってしまうのです。
ダイエットをするのに、最終目標を何キロにするか決めずに、1ヶ月に1kg減らす!なんてやりませんよね?
あれと同じです。
最終目的あってのスモールステップなのです。
なので、スモールステップを始めるのであれば、終わりも明確にして始めるようにして下さい。
また、継続することで効果が得られる目標もオススメです。
たとえば、小テストで1ヶ月満点を取り続ける。
一見難しそうですが、小テストであれば十分可能です。
もしいきなりこれが難しそうならば、点数を下げる。
60点でも構いません。
必ず60点は死守する。
そういう目標自体は低くても、継続的に達成可能な目標を立てるのも効果的です。
最終目標を決めておくこと!
努力がお金になることを教える目標設定
例えば、毎回テストの点数×10を毎月のおこづかいにする。
これはかなり現金な子を育てる事になりかねませんが、実業家や経営者、政治家や権力者、プロスポーツ選手といった教育資金が潤沢な方がこういう教育をしています。
成績がリアルにおこづかいに響くので、お金を得たければ努力をしろ、ということになるわけです。
ただし、先程も話した通り、潤沢な資金がなければ難しいでしょう。
小さいうちだけというやり方は通用しません。
やるなら、社会人になるまでやり抜く覚悟で始めなければ、この感覚は身に着けられません。
なのでそれが難しい場合は、成功報酬をお金と連動させるのはやめた方がいいでしょう。
どういう職業にしたいか考えておくこと!
報酬の決め方

「偏差値60取ったらゲームを買う約束をしてしまい、実際に60を超えたのでゲームを買い与えてしまいました。しかしその後ゲームにはまってしまい、今では偏差値50すら切ることがあります。どうしたらいいでしょう…」
サピックス 小5 男の子の母
残念ながら、こうなってしまうと引き戻すのが大変です。
目標を達成したらゲームを与えるという話をよく聞きますが、ゲームを与えて勉強に差し支えは出ませんか?
自分でメリハリをつけられる子ならば構いませんが、ゲームに没頭してそれが勉強に支障が出ることが目に見えているのなら、与えるべきではありません。
これでは本末転倒です。
報酬を決めるときは、それ自体が勉強の足かせになる可能性がないかどうか、よく考えて決めましょう。
実はこの手の相談はかなり多いので、これからゲームを与えようと思っている方は、与え方に十分気を付けて下さい。
報酬としてゲームを与えていいことはほぼありません。
とはいえ、勉強に関係あるものをご褒美にしても、喜んでくれなければご褒美にはなりません。
そのため、その場限りのご褒美がオススメです。
本や雑誌、服やアクセサリー、グッズやライブチケットといった、与えてもその場限りで勉強に対して支障が出ないものならいいでしょう。
また、無形のサービスも使えます。
無形のサービスはその場限りで形に残らないので、勉強にはほとんど支障が出ません。
例えばどこかのスイーツを食べに行くとか、映画やディズニーに行くとか。
家族のコミュニケーションの時間にもなりますし、机では学べない勉強につながる可能性が高くなります。
説得する方法を学ばせる

「散々もので釣ってきてしまいました。もう今となっては要求が大きすぎて、悪いと分かっていながらも、かなり難しい目標設定にしています。そのためやる気を失わせてしまって、勉強しなくなってしまいました。今から報酬以外で釣る方法はないのでしょうか…」
早稲田アカデミー 小5 女の子の母
報酬を与えて引っ張ってしまった場合、もう手遅れと言わざるを得ません。
しかし方法が全くないわけでもありません。
オンライン授業でも教えている方法ですが、おねだりの仕方そのものを学ばせてしまうという方法があります。
子どもはある時期からおねだりをすることで、物を得るという方法を覚えていきます。
しかし、おねだりを受け入れてから約束を与えると、努力せずに先に手に入れてしまうことになります。
後から「約束だったよね?」と言っても子どもには通用しません。
目の前に楽しいものが来てしまえば、それを振り切って約束を守るなんてこともできません。
そこで、おねだりをするときには先に頑張って結果を出しておくことを教えるのです。
これにより先に頑張ってからおねだりするようになります。
ただし、子どもの頑張りに気付けてあげられない親の場合、努力は無駄だという意識を埋め込んでしまいかねませんので、絶対に努力を見逃さないようにして下さい。
そしておねだりを教えるときにもう一つ。
説得の仕方を教えて下さい。
おねだりに対して単に反対するのではなく、どのように説得すればいいかをしっかりと教えてあげて下さい。
実際にオンライン授業で話した例をご紹介しましょう。

「先生、新しい服を買ってもらいたいんだけどさ、前も買ったばかりでしょって言われて買ってくれないんだよね。でもね、あれは秋物で、今欲しいのは冬物だから目的が違うの。なんとか買ってもらう方法ないかな?」
小6 中学受験 女の子
この子、受験生だったんですけどね(^^;)
何ともませたおこちゃまでしたが、まぁ本人が欲しいと言っているのだからしょうがありません。
ちなみにこんなこと言っていても、ちゃんと第一志望には合格しました。
さて、ではこの子にはどんなことを教えたのかと言いますと、
- なぜ新しい服が欲しいのか。
- 古い服はどうするのか。
- いつもちらかっている服はどうするのか。
- 以前買った服はどうなっているのか。
- 新しい服を手に入れることで何が変わるのか。
これらをオンライン授業で一緒に考えました。
中学生のお姉さん達も参戦して(笑)
こうやって一見くだらないことを真剣に考えるのがファイのオンライン授業の特徴です。
そして、こういう議論を通じて、説得する力を身に着けていくのです。
この力は国語力はもちろん、日常会話でも使えるようになってきます。
結果、巡り巡って成績に活きてくることになるのです。
なので、もし既にもので釣ってしまって失敗してしまったのであれば、説得やおねだりの仕方を教えるようにして、その力を勉強に活かせるようにするといいでしょう。
説得の仕方を学ばせることで、その力が学力にも結び付いてくる。
やらせようとするからやらない
ファイのオンライン授業は、基本的に強制はしないスタンスです。
本人の意思に任せます。
そのため、本人がやりたくないと言うなら、

「そっかー!大変だもんね!じゃあやらなくてオッケー!」
と平然と言います。
言葉って不思議なもので、同じ内容でも言われたらやりたくなくなるのに、自分でやると言ったものには多少なりとも責任を感じるものです。
そのため、命令や強制はしません。
オンライン授業でやるのは、本人がやると決めた時に空回りをしない布石を打っておく事です。
本人がいつやる気になるかなんてわかりません。
気まぐれで一時だけやる気になるかもしれません。
半年ぐらいやる気を失っているかも知れません。
でも人の感情なんて波がありますから、放っておいてもいずれは「勉強やらなきゃな」って思う瞬間があります。
その時に空回りをしないように準備をしておく。
これが戦略的放置、布石です。
この「勉強しなきゃ」って思うタイミングを見逃しているから、勉強させられないのです。
そりゃ四六時中「勉強しなさい!」って言っていれば、小さい変化に気付けるわけないですよね?
また、多くの子供達がせっかく勉強しようと思って頑張っても、全然結果が出ずに挫折していきます。
でも冷静に考えれば当たり前だとわかるはずです。
今までのやり方が正しいのなら、そもそも今こんな状態になっているハズもないですからね。
今この現状になったのは、今までのやり方が間違っているからです。
それをまた繰り返して伸びる訳がないと思いませんか?
だから、勉強しようと思ったタイミングで、正しい勉強ができることが大切なのです。
放置している間にやること
気分が乗らない時に勉強をやらせても意味がありません。
だから気分が乗るタイミングを見計らいます。
オンライン授業でも、見守っているだけで、完全に放置なんてしません。
では具体的に何をしているのでしょうか?
オンライン授業では、勉強をやっていない時期の抜けを細かく把握しています。
どの分野でどのように抜けているかが分かっていれば、入試においても遅れを取り戻しやすいですからね。
これはご家庭でもできるでしょう。
いつ勉強をしていなかったかなんて、一番身近で見ていますからね。
さらにオンライン授業では、勉強のやり方がどう崩れていったのかもチェックしています。
どう崩れていったのかがわかれば、どのような勉強法なら続けやすいかの参考にもなります。
個別に勉強法をカスタマイズできるのは、こういうデータの集積があるからなんですね。
だから長期戦になるのです。
こうして勉強やりたいという時期、タイミングを待ちます。
そして塾生から前向きな発言が出て、勉強をやり出そうとしたタイミングで、適切な勉強法を指導します。
タイミングを間違えなければ、すんなり受け入れてくれやすいので、空回りを極力なくして結果を出すことができる、というわけです。
そして、放置について卒業生がこんなことを話してくれました。
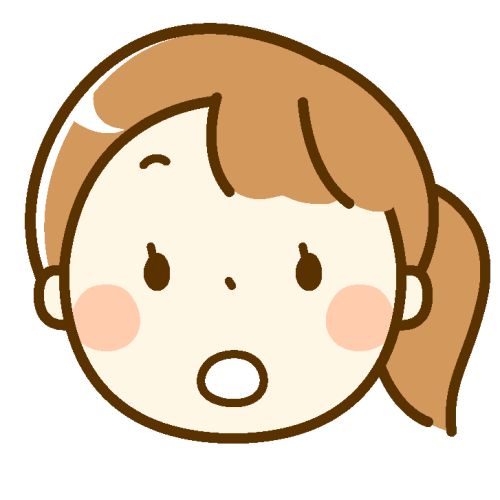
「確かに先生はやれって言わないけど、それ、すっごく怖いんですよ。勉強なんてするかー!って思って塾サボったりもして、でもそんな時って、みんな勉強してるのかな…とか、このまま勉強しなかったらどこ行けるのかな…とか考えちゃって、サボっても公園で結局テキスト開いてみたりして、きっとこのままサボり続けても先生は何も言わないんだろうけど、でもそれって自分からやるって言わないと教えてくれないって事で、まぁ結局自分で自分に追い詰められて戻ってくるんですよ。
戻ってきた途端、みんなの倍以上の課題を出されたのにはびっくりしましたけどwwこういう時って『おかえり』とか『よく帰ってきたね』とか、普通優しい言葉とかかけてくれるものじゃないですか?」
「そんなことするわけないだろ。」と答えたら、「まぁわかってましたけどー。」と言われました(笑)
余程危ない道に手を出さなければ、言われないことで勝手に考えるようになるのです。
それなのに余計な横やりを入れるから思考がストップする。
成績が全てじゃないですから、勉強なんてしなくても放っておきましょ(笑)
子ども達の発言が変わる
最後に子ども達のコメントを紹介致します。

「宿題はめっちゃ多いけど、やりきった時の達成感はすごい。ノートが埋まっていくのが楽しいんです。」
一週間に2冊のペースで使い切っていた子のコメントです。

「最初の頃は頑張って宿題やってるつもりなのに、こんなのやった内にはいらん、とか言われてムカつきました。今にして思うと、無駄な努力ってまさにあの時の勉強のやり方だったと思います。」

「勉強やった、って言うのはどういう事なのかって言うのをファイは教えてくれた。今までのは時間の無駄遣い、今のは結果につながる努力ってハッキリ言えます。」
ついこの前まで勉強から逃げていた子ども達がこんな事を言うようになります(笑)
これは特別な事ではありません。
誰にでも起こりうる事です。
やらせようとする必要なんてないのです。
むしろやらせようとすることが、返って勉強から遠ざけるのです。
あなたの子どもは変われます。
あなたも変われます。
変わり方、変え方を知らないだけなのです。
ファイでは月1万円から、学習法のアドバイスをしています。
声かけに困る方はぜひご利用下さい。






-3-1024x768.png)
-1-1024x576.png)
-12-150x93.png)
-5-150x93.png)
-12-485x300.png)

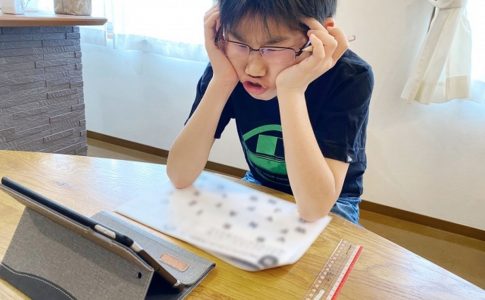


-20-485x300.png)







「中学受験の時はあれだけ勉強していたのに、中学生になった途端、全く勉強しなくなってしまいました。今はまだ真ん中ぐらいにいますが、このままだと落ちこぼれていきそうで、せっかく合格した意味がないと思って焦っています。」
サピックス⇒K中(難関中) 母