目次
どっちの塾に通わせたい?

「やったよ!やったけどできなかったの!」
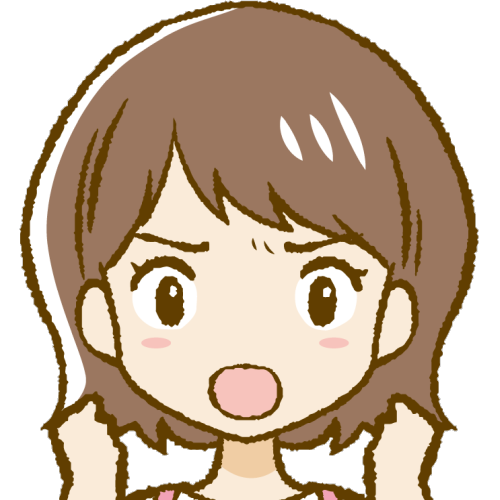
「やってたらできないわけないでしょ!全く同じ問題なんだから!」

「やっても忘れちゃうの!」
ファイのオンライン授業は親子一緒に受講できるので、私の目の前でこのような会話が繰り広げられることがあります。
特に中学受験では割とよくあります。
しかもこれが始まると結構止まらないんですよね(^^;)
酷いとカメラの前で物の投げ合いが始まります。
つまり、勉強に関してそういう喧嘩をする家庭は結構あるということです。
そこで質問です。
以下の2つの塾ならどちらにお子様を通わせたいですか?
- 偏差値が10伸びる可能性はあるが、40%の確率で10下がる可能性がある塾
- 最大でも3しか伸びないが、下がる事はない塾
この質問は、オンライン授業で実際に保護者の方にお聞きすることがあるのですが、ほとんどの方が下がらない方を選びます。
もう一つ聞いてみましょう。
偏差値3下がるのと、3上がるのはどちらの方がインパクトが強いですか?
プロスペクト理論・損失回避の法則
これらは経済学ではプロスペクト理論と呼ばれるもので、心理学では損失回避の法則とも言われるものです。
実際に中学受験を考えている方で、偏差値が3下がった子の親と話すと、

「このままでは合格出来ないんじゃないか」
「もっと勉強させないと」
「ちゃんと授業についていけていないんじゃないか」
と言った不安を口にする方が多くいらっしゃいます。
ところが、この子たちが偏差値3上がって「良かったですね」と話をしても、

「まぁ3上がっても全然届くレベルじゃないですけどね」
「前回下がってるので」
「3なんて誤差の範囲でしょう」
こんな話ばかり聞こえてきます。
このように、成績が上がった時の反応が冷たくなっている人が多いのです。
これはたとえ同じ数字でも、上がるよりも下がる方が損失が大きく感じてしまい、過剰に反応してしまうために起こります。
そしてこういう方は、基本的には損失を嫌う、損失に対して過剰に反応する傾向が強く出るのです。
なぜ親の話を受け止められないのか
このプロスペクト理論は経験から後天的に身につけるものなので、そもそも損失にあたる経験していない子どもには理解できません。
生活の中での様々な経験を通して「損はいけないことなんだ」「損したくない」ということを学んでいくのです。
しかし現段階ではまだ未熟ですから、成績が3上がるよりも、3下がる方が損なんだ、ということを理解できません。
むしろ下がることによる損失、怖さを知らないので、3上がった方を喜んでしまいます。
それどころか、先ほどの塾の選択肢では、偏差値が10上がる可能性がある塾を選ぶんですよね。
中学受験なら、偏差値10違えば学校のレベルもかなりかわってきますからね。
憧れが先行して10伸びる可能性がある方を選んでしまうのです。
だから親とは感覚が逆になり、

「どうせ上がっても褒めてくれない」
という気持ちのズレが生まれるのです。
さて、ここで話を終わらせると「少しでも上がったら褒めてあげて下さいね」という一般的な話しで終わってしまうので、もうちょっと踏み込んだお話をしましょう。
それが、子どもはプロスペクト理論通り、つまり損失を回避しようとは動かない、ということです。
先程も話した通り、プロスペクト理論は経験的に学んでいくものです。
だから親がいくら回避しようと先回りしても、子どもは予想もつかないような方法でリスクを取って失敗をするのです。
本当に大切なのはここです。
リスクをどう学ばせるのか
失敗から何を学ばせるか。
つまり、リスクを取ったことを叱るのか、取ったことを褒めるのか。
例えばテスト前のやまかけはイメージしやすいでしょう。
外せば全然点数が取れませんからね。
スマホで遊ぶのも危険性の一つですね。
YoutubeやLINE、ゲームといった誘惑が沢山あります。
そしてこれら勉強しなくなる可能性があるものに対して、親が先回りして
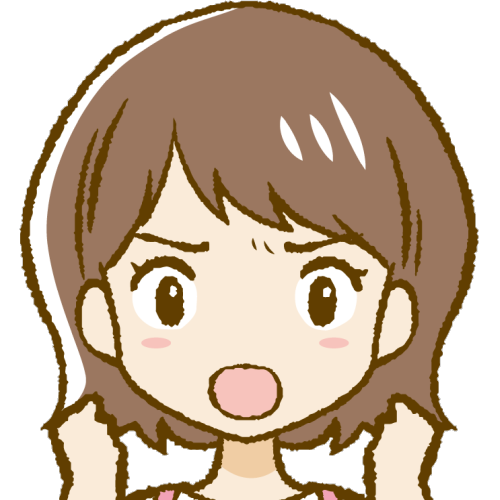
「もっと勉強しなさい!」
とか
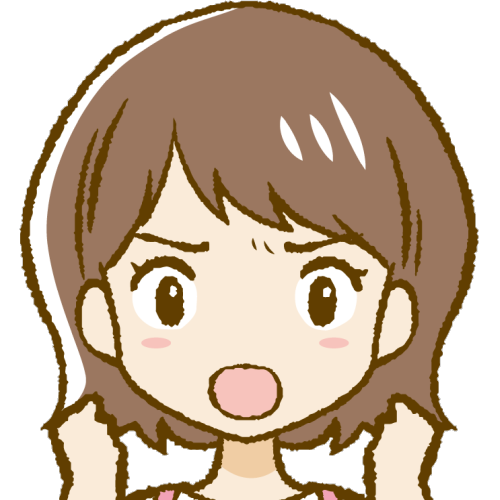
「そんなんじゃ成績上がらないでしょ!」
などと言って釘をさします。
しかしそれでは子どもはリスクだということを学べないのです。
つまり、それをやってしまうと成績が下がるんだ。
下がるとこんな悪いことがあるんだ。
というのを感じられないんですね。
高校受験なら何となくわかってくるかも知れませんが、中学受験なんてまだ小学生ですからね。
社会の仕組みを学び始めたかどうか、という程度の経験しかありません。
だから「損をした」と感じる時間を親が奪ってしまうと、いつまで経っても損に気付けない。
何度繰り返しても「やろうと思ってたのに言われたからやる気がなくなった!」などと言われるのです。
失敗から学べるようにするのが本当の子育て
子どもは、いくら親が先回りして話しても聞いてくれません。
自分が失敗しないと学べないのです。
そのため、成績が下がった時には現状を叱るよりも、

「今、すごく損してるんだ!」
と気付かせる事が重要になります。
オンライン授業だとサボりやすいですからね。
実は結構サボってしまっているというのはニュースにもなっています。
だから授業をサボるのは損なんだ、と思えるようになってくれば勉強します。
なので、逆に

「お母さんがいない間に遊んでおかなきゃ損だ!」
みたいに考えている子は、自分でやるようになるまで非常に時間がかかります。
しかしこういうところから、お母さんがいない間に遊ばないのが損なのではなく、勉強しないことの方が損なんだ、と気付かせることができれば、自分で勉強するようになります。
でもそのためには、親が先回りしすぎないようにすることが大切なんですね。
リスクを取って失敗したら?
次に失敗したケースもお話しておきましょう。
まず勉強に関するリスクには、2つの種類があります。
勉強するリスクと、しないリスク。

「勉強するリスクなんてあるんですか?」
そうなんです。
勉強するリスクというのもあるんですね。
特に中学受験は結構落とし穴が潜んでいるものです。
例えばサピックスに通わせていて、ついていけないから準拠の個別指導塾であるプリバートに通わせるというケース。
これは準拠とはいえ、教え方が先生任せなので、全く違う解き方を教えられて混乱することがあります。
実際かなりいますからね。
子どもがよく取るものといえば、
- テスト直前の山掛け
- 漢字の暗記
- 何度も解いて覚える
- できないものを飛ばす
- 解けないものを放置する
です。
そして勉強しない方としては
- ゲームをする
- テレビを見る
- スマホやタブレットで遊ぶ
- 休憩ばかりでやらない
といったものが多いですね。
これらを選択すれば、簡単に成績は下がります。
だからこういうものは選ばせたくない、という気持ちはわかりますが、やらなければ学びません。
どうせいずれやってしまうなら、今の内にやらせてしまうというのも一つの手です。
特に勉強しようと思っていなら、たとえ失敗しても褒めてあげる方がいいでしょう。
なぜならリスクは大人になるにしたがって取れなくなるからです。
これは説明するまでもなく大人なら経験からおわかりになるはずです。
怖いもの知らずだからこそできることってあるんですよね。
従って取れるうちは取らせておき、様々なリスクの取り方と結果を学ばせる方が、将来役に立つスキルになるのです。
やろうとしたこと自体は褒める
例えば山かけ自体は基本的には勧めませんが、絞って勉強が出来たこと自体は褒めるに値します。
習い事や部活で他の人よりも勉強時間自体が少なくなっているのにも関わらず諦めずに努力している子も褒めるに値します。
思いつきで突然単語帳を作り出して、結局時間がなくなった。
これもやってみて初めて時間がかかるし非効率だとわかるもの。
現状を打破しようと行動したこと自体は評価に値します。
結果は出なくとも、諦めずに頑張ったこととして褒める事ができます。
どんな形であれ、努力を認める
要するに何でもいいのです。
このままだと何も変わらなかった。
それを変えるために努力した。
その努力が必ずしも正しいとは限らない。
だけどやってみようとしてみた。
これがリスクを恐れずやってみる原動力に繋がります。
そしていいリスクの取り方、悪いリスクの取り方がわかってきます。
そもそも親が本当のリスクをわかっていない
最後に親として絶対にやって頂きたくないこと。
それは「ムダだった」と感じさせることです。
ムダを感じる程、無気力になり、リスクを取る取らない以前の問題になります。
特に中学受験で志望校に落ちたことを無駄だと感じたら最悪です。
進学先では大抵落ちこぼれていきます。
それが望みですか?
基本的にはこのリスク管理に重点をおいた指導法は、大抵の状況で使えます。
地味ですし時間もかかりますが、諦めなければ大外れはしません。
ただ問題なのは、親が本当の意味での損失を理解していないことなのです。
- 今ここで小言を言って反発を買う危険性
- 文武両道を夢見て習い事をさせながら成績向上を求める危険性
- ここで成績が上がってしまったことによる危険性
- 試験直前に勉強をやり出す危険性
- 勉強をやり続けることによる危険性
- 成績向上だけを追い求める危険性
- 認めてあげられないことによる危険性
おそらく何を言っているのかわからないものもあるでしょう。
子どもが目先の楽しさに時間を奪われて成績を上げられないように、親も目先の損失を怖がって、将来に大きな損失を与えていることに気付いてない。
「今何をすべきかわかっていない」と怒る親。
しかしその親こそ目先の成績や偏差値にとらわれて、今何をすべきかわかっていない。
この、何が本当の損失かわかっていないことにこそ、大きな問題があるのです。
一番怖いリスクを理解しているか
大人はリスクを取れなくなっていても、子どもはリスクを取ってしまう。
でもだからこそリスクを持って挑んだことが、成功した時に大きく伸びる可能性がある。
どんなに親が外堀を埋めたって、下がる時は下がる。
下がることがない塾なんて存在しないのです。
そして何より勉強が嫌いになるリスクの方が怖い。
こうなると勉強という言葉自体に拒否反応が出てしまい、何をどう誘導してもやらなくなりますからね。
しかも中学受験を通して勉強を嫌いにさせると、まず勉強の世界に戻ってくることはありません。
それならいっそ、嫌いではないけどやっていない状態のままにして、勉強したいと思える機会が巡ってきたときに勉強できるようにする。
極端なことを言えば、勉強するもしないも、本人に任せる。
親が先回りしてあれこれ言う方が危険なんだ、ということを理解する。
その方が親のリスク管理としては楽ですし、現実的なのです。
そしてこれが偏差値10伸びる可能性がある塾で、10伸びる子どもにする秘訣です。
なお、ファイではテストの後に、どのような声かけをしたらいいかといったアドバイスを、月1万円でしています。
成績表だけみて、ついつい感情的に話してしまう方におすすめです。
どんな話し方がリスクになるのかがわかれば、勉強しやすくなる話し方もわかってきます。
まずは学習法診断を受けてみて下さい。
性格も踏まえた上で、どんなやり方がお子様にあっているのか、ハッキリさせることができますよ。






-1-1024x576.png)




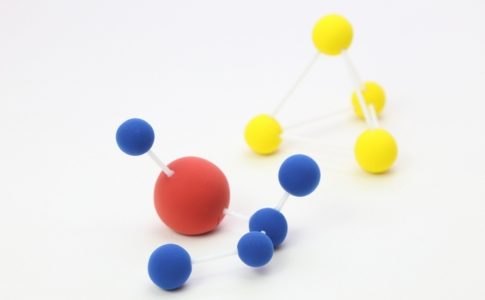



-45-485x300.png)





「だからあれだけここは出るからやっておけって言ったじゃない!」